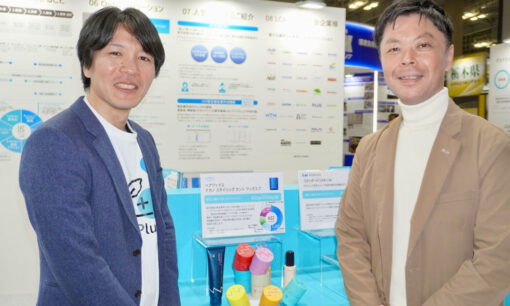大中忠夫(おおなか・ただお)
株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス代表取締役
CoachSource LLP Executive Coach
三菱商事株式会社 (1975-91)、GE メディカルシステムズ (1991-94)、プライスウォーターハウスクーパースコンサルタントLLPディレクター (1994-2001)、ヒューイットアソシエイツLLP日本法人代表取締役 (2001-03)、名古屋商科大学大学院教授 (2009-21)
最新/著書・論文:「日本株式会社 新生記」全13巻2024.05,17 (2025.05.07全面改訂)
「日本株式会社 未来設計図」2025.07.19
21世紀の新たな資本主義社会リーダーとして日本企業社会はどのように進化してグローバル社会に貢献するか?現代日本社会のビジネス・政治・経済関係者全員の未来設計のための経営・経済分野史の総括集約情報集。主なトピックスは、
・「日銀ゼロ金利30年」が人間史の表舞台に引き出した真実群
・マルクス「資本論」の「もっともらしい仮面」と「最大の過ち」
・20世紀の社会主義や共産主義がすべて独裁政治体制に陥った根本原因は?
・人間社会が戦争を繰り返す根本原因は?
・これらの事象の全てに共通な存在は「金利という人間史最古の人工知能」
・戦後の廃墟から生まれた日本発の新たな資本主義社会が人間社会の未来を開く!
・日本企業社会が握っている人間社会の未来を開く鍵とは?など。
本コラムは全4章の第4章です。
全4章 目次
第1章 金利AIの歴史的暴走を止めれば未来が現れる
資本論という名の金利刷り込み理論を超えた未来論
1.正常か異常か?-ゼロ金利30年の日本社会
2.ゼロ金利が円安要因であったことがあるか?
3.ゼロ金利がインフレを引き起こしたことがあるか?
4.ゼロ金利が日本の経済成長を阻害したことがあるか?
5.金利の歴史的功罪-金利資本主義の奇妙な矛盾
6.金利という名のAIの歴史的暴走を止めれば未来が現れる
第2章 インフレによる金融経済成長か物価安定の実体経済成長か
バーナンキ・ヘリコプターと黒田バズーカの同床異夢
7. バーナンキFRBの「Helicopter Drop」の目的と結果
8.黒田日銀の「黒田バズーカ」の目的と結果
第3章 日米経済成長の分岐点
金利AIの社会洗脳プログラム:現在価値換算法
9.金融経済と実体経済の二階層構造と日米経済成長の分岐点
-池田勇人の資本蓄積提言:実体経済成長には「長期投資力」が必須要件
10.米国社会に「インフレ期待」を刷り込んだ金利AIの洗脳プログラム
-「長期投資力」を衰退させた現在価値換算法 (Net Present Value)
第4章 稲作二千年社会が世界に伝道する「ものつくり」資本主義
生産された「米という資本」の蓄積と投資の成長循環
11.稲作二千年の「ものつくり」資本主義社会
-生産された「米という資本」の蓄積と投資の成長循環
12.金利資本主義の終わり「ものつくり」資本主義の始まり
-実体経済成長を起動する創造行動が人間社会の未来を開く
第4章 稲作二千年社会が世界に伝道する「ものつくり」資本主義
生産された「米という資本」の蓄積と投資の成長循環
11.稲作二千年の「ものつくり」資本主義社会
-生産された「米という資本」の蓄積と投資の成長循環
資本と金利を切り離せば資本の本質が現れる
日本社会の実体資本主義の源泉を突き詰めるには、資本主義とは何か?そもそもその本質である資本とは何か?を常識的に理解することから始めます。そのためにはまず、「資本と金利とは不可分」といった認識から卒業します。そのような認識は、マルクス「資本論」による資本批判の華々しい舞台の裏で、人目を避けて経済学体系にもっともらしく刷り込まれた思い込みにすぎないからです。30年間金利ゼロの日本という資本主義社会がそれを証明しています。
資本と金利とを別物として切り離せば、それでは資本とはそもそも何か?という純粋な疑問がわいてきます。そしてその答えも常識的に明らかになります。資本とは、自然界狩猟や地下資源発掘も含めた、人間による創作生産物なのです。このいわば「実体」資本の蓄積と投資の成長循環が通常の経済成長なのです。したがって、米(こめ)も純然たる資本ですから、150年前まで国民の八割が農業従事者であった稲作二千年の日本社会は、その文化を継承している限り、金利の歴史に劣らない歴史を有する実体資本主義社会なのです。
この稲作二千年社会経済が作り出した「米(コメ)」という資本は、二千年以上にわたり蓄積と投資による成長循環を実現しています。「米」とその生産力を基盤とする日本社会は、その反対の、いわば金利資本主義、すなわち未来創造価値を金利で割り引いて長期投資意欲を抑制する現在価値換算法(NPV)といったような未来への進化成長を現時点の延長線上でしか捉えていない狭視的な論理、などをはるかに凌駕する実体資本主義の二千年にわたる実証事例なのです。
資本と通貨が混同される原因
ところで、資本と金利とを分別し、さらに「資本とは人間が創出したすべての生産物」という常識を定着させるためには、もう一つ思い込みを解消しておく必要があります。それが「資本=金 (Money:通貨)」である、「資本家=金持ち階層」、といった時代遅れの思い込みです。ここで後者は、現代世界最大の資本家が「年金生活者」である事実を知れば霧消するでしょう。では「資本=金 (Money:通貨)」という思い込みをどうするか?その思い込みの起源を突き止めてみましょう。
資本がその生産時点では人間の生産物であるにもかかわらず、その交換手段である「金 (Money:通貨)そのもの『のみ』が資本である」かのような勘違い、混同はなぜ生じているか?それは通貨が資本の交換証明(証憑手形)、価値交換媒体、であるのみでなく、通貨には、人間の生産物のすべて、農業、水産、鉱工業、サービス、などの生産物資本のすべてにとって避けることのできない経年劣化という宿命を唯一防止凍結する特性があることによります。通貨は経年劣化を凍結防止する特性をもった唯一の資本なのです。
その経年劣化防止特性をもった商品、すなわち通貨、を取り扱う当事者と業界は、その取り扱い手数用、あるいは差益を得る権利があります。しかしそれは通常の商品サービス取引と同じであるべきで、ちょっと冷静に考えれば思い当たることですが、その手数料として商品価値が経年増殖する特性、金利、まで付加する根拠は、特に、通貨供給に物理的な限界もなく、実際に通貨が溢れている現代社会では、見当たりません。
しかしその追加特性付加の結果、経年劣化防止力のみでなく経年増殖力まで装備した通貨という資本がその他すべての資本を圧倒し代表する地位を占めるまでになっています。その結果、通貨以外の大部分の資本の蓄積投資の成長循環による経済成長、実体資本主義、の存在も希薄化しています。「金 (Money:通貨)=資本」の思い込みによって、人間経済史を発展させてきた本来の実体資本主義が、金融産業の資本による経済成長、金融資本主義、あるいはその本質の金利資本主義、に取って代わられる潮流を作り出しています。(注9)
注9.なお、よくよく眺めれば、この金利の付着によって、せっかく経年劣化を免れている通貨の特性が消滅しています。通貨自体の経年劣化は起きていないにもかかわらず、その未来価値の評価が現在価値換算法の累積複利計算、金利が存在することで成立する割引計算、で矮小化、価値減退、されているのです。あるいは金利産出メカニズムに参加せず放置されたままの通貨は金利産出メカニズムに参加し預金や資本という名称を与えられた通貨に対して相対価値が時間とともに劣化減少し続けます。
そしてそのような状況では誰も自ら不利な立場を選ぶことはありませんから、社会全体が金利増殖メカニズムに殺到します。これが米国社会の「インフレ期待」常態化です。「資本=Money:通貨)」の思い込みがさらに発展し、「Moneyの獲得と蓄積=富の実現」といった社会認識が、金儲けを最高美徳とし貪欲さ(Greed)すらも容認する社会文化を育て上げています。
資本主義とは何か?日銀ゼロ金利30年が示す資本主義の本質
日銀ゼロ金利の30年の現実は、資本主義とは何か?という近代人間社会と経済の根本概念にも光をあてることになりました。
金利のない資本主義社会が四半世紀以上にわたり実存している事実、したがって資本と金利は不可分ではなく、そもそも全く別物であるという事実、を日銀ゼロ金利30年が証明しているからです。その結果、マルクス以来150年以上誤解され続けてきた、資本主義の本質も明らかになっています。
「金利」を当然のごとく「資本」の裏側に貼り付けておきながら、資本とは何かを提起した「資本論」によって資本の本質が150年以上歴史の背後に隠され続けました。金利を背負わされたことで、資本とは通貨であるとの誤解も常識化し、さらには資本主義そのものの定義も狭量に歪められました。資本主義とは、金利を背負った通貨資本取引に従事する資本家が主導する社会システムという定義の常識化です。
ちなみに、日本社会でも、特に外資導入自由化とともに流入した株主第一主義経営の水先案内人を務める経営研究者や経営コンサルタントのほぼ全員が、この狭量定義された資本主義を掲げて論陣を張ります。彼らが「資本主義(の時代)ですから」と話し始めた後には、「資本家、投資家の利益は(最優先で)尊重されるべき」という「株主第一主義」の結論が続くのです。
これは、資本とは金利付の通貨であり、その蓄積と投資を直接担う資本家のみが資本主義の推進者であり最大の受益者であるべきという論理です。これは資本主義とは、資本の流通者の存在を最大重視するルールであるとの誤解、あるいはルールと論理の歪曲に外なりません。
しかしながら、これらの歪曲議論の起点、「資本とは金利付の通貨である」という金利AIによる社会的洗脳、を洗い流せば、人間史の新たな未来が見えてきます。
資本とは人間社会全体、全員、が創出したすべての価値なのです。従って、資本の蓄積と投資の成長循環が実現した経済成長の受益者は、その資本取引の直接従事者のみでなく、資本を生産したすべての人々でもあるべきなのです。資本主義とは、人間社会が創出、生産したすべての価値である、資本、を蓄積、投資する成長循環によって、人間社会全体の富、経済、を豊かに成長させるシステムなのです。これが、日銀ゼロ金利30年が実証した資本主義の本質です。
マルクスは、社会主義、共産主義という人間社会の究極の理想を掲げながらも、その必須基盤である資本主義を金利主義と混合して否定、排除したことで、彼自身のみならず、その後150年の人間社会全体を大きな迷路に踏み込ませています。2025年現在、日銀ゼロ金利30年によって、この迷路の先の光が見えてきています。
日本型資本主義が実現した高度経済成長の原動力を直視する
米国社会が金融資本主義に埋没する一方で、日本社会は、1997年の外資導入自由化とともに流入した株主第一主義という金融資本主義に浸りきることなく現在に至っています。この事実は欧米先進経済では衰退傾向にある実体経済が、日本社会では第二次大戦後から現在まで着実に成長し続けている事実が証明しています。たとえば、本論文 第1章、第2章の挿入図6、7、15、16(出典:「日本株式会社 新生記 (第1巻)」2025改訂版 大中忠夫)が示すように、実体経済産業299万社合計の純資産と企業総生産(GCP)は過去60年以上にわたり長期的、持続的に成長しています。
そしてこれを実現した原動力は何であったかといえば、第二次大戦で国内外惨禍の犠牲となった数百万の人々に対する償いの思いに基づく戦後の高度経済成長政策とそれを実践した人々であり、さらにはその基盤となっている稲作二千年の実体資本主義の社会文化の存在であったでしょう。
しかしながら、その日本の高度経済成長をさらに進化成長させるためには、現時点での表面的な状況だけではなく、その原動力の推移を直視する必要があります。その大きな原動力は、1950年代初頭にデミング氏によって日本社会に浸透した品質改善技術とそれを実践した現場社員。特に60-70年代の金の卵と呼ばれた世界的にも突出した高い中等教育を受け(注10)、戦後の経済復興を目指す企業体制の中で誠実さと熱意に溢れて働いた人々でした。
注10.日本の中等教育の世界的な卓越度を示す顕著な事例として、米国経営大学院の入学資格判定共通試験(GMAT)があります。必ずしも一般には知られていない事実ですが、この修士課程大学院の入学判定共通試験の50%を占める数学問題群は、日本の中等教育課程までの数学力で完全に対応できます。
この高度経済成長を実現した立役者、原動力であった世代は2025年現在すでに現場第一線からは引退しています。また2000年以後流入した株主第一主義に応える利益効率追求の過程で導入された、非正規社員制度や、海外の低賃金諸国への生産体制移管もいまだに続いています。日本の実体資本主義も人的資本が弱体化、空洞化しつつあるのです。この実情を見過ごしたままで日本経済の未来成長を楽観することはできません。ではその打開策は何か?まずは現代日本企業社会が抱える深刻な問題点を解決することから始めます。
まずは日本企業社会の深刻な問題点の解決から
まず第一には非正規社員体制からの速やかな転換でしょう。といっても既に現代日本企業社会の産業の一つとなっている社員派遣ビジネスを禁止する必要はありません。非正規社員や派遣社員の正規社員との待遇格差をなくし、さらに非正規社員から正規社員への転換を積極的に実践することで解決できます。
次に、さらに深刻な問題として、海外からの実習生人材に対する待遇の改善適正化も必須でしょう。本論文ではこれについて十分に議論する準備も余地もありませんが、日本企業のグローバル展開、すなわち日本の実体資本主義のグローバル展開を目指すのであれば、この海外からの実習生に対する本格的な待遇改善は不可欠な大前提です。
そして最後にもう一つ。正規社員にとっても会社が心躍る感動の場ではなくなりつつあるのではないでしょうか?インフレとバブルの80年代の過剰な社会的熱狂を後悔する余り、それ以前の日本企業社会が生み出していた未来に対する素朴な熱情まで忘れてしまってはいないでしょうか?今日よりも明日、明日よりもさらにその先の未来が良くなる!という60-70年代の日本企業社会の素朴な夢と希望を追求するエネルギーが現代でも持続的に生み出されていると自信をもっていえるでしょうか?この事実から目を背けることなく、これを問い続けることで、日本企業社会と日本経済、それが継承している実体資本主義の未来進路も明確になるでしょう。
そのためには日本の実体資本主義を、その本質に基づいて、「ものつくり」資本主義と理解することでより明確になります。そして、なぜその「ものつくり」資本主義を衰退させてはならないのか、その人間社会にとっての存在意義、必要性を徹底的に議論することで、「ものつくり」資本主義社会が追究すべき未来課題も明らかになります。しかしその一歩を踏み出す前に現代日本社会とグローバル社会の現実を直視する必要があります。
実体経済の成長低迷のみでなくその原動力の衰退まで視野に入れれば、日本の実体資本主義、「ものつくり」資本主義、の衰退は、欧米先進社会のみの問題ではなく、その最後の橋頭堡ともいえる日本社会にも出現しつつあります。さらにグローバル社会全体に目を向ければ、実体資本主義が衰退した未来が既に始まっている現実があります。
12.金利資本主義の終わり「ものつくり」資本主義の始まり
-実体資本主義を追求する創造行動が人間社会の未来を開く
実体資本主義が衰退した未来は既に始まっている
2025年現在も世界各地で戦争と紛争が絶えません。人間社会はなぜ戦争という行為を続けるのか?その最大の原因は自国経済の停滞、低迷です。人間社会が数千年継承している不幸な知恵ですが、戦争は現代社会でも、あるいは軍事技術が最高に発達している現代であればこそ、経済閉塞を打開する最も手っ取り早い手段と認識されています。しかしこれは人間の大量の生命を犠牲にする最も原始的な経済復興策です。人間と生命への尊厳の存在しない経済社会、いや経世済民の名にも値しない社会、への転落に他なりません。
さらにいえば、原子爆弾 (原子核分裂と水素核融合の爆弾)という、広島・長崎の数百倍などとされるものの人間の想像をはるかに超えるためにその実際の威力と被害の規模などはまだ誰も正確には理解できていない破壊兵器が存在する21世紀には、その原始以来の知恵が人間社会の消滅すらもたらしかねません。人間社会の未来を拓くにはこの脅威を絶対に克服する必要があります。
ではどうするのか?人間社会が戦争行為を続けるもう一つの原因が人間社会の未来を開く鍵を示してくれています。それは経済停滞・低迷の最大の原因、人間社会全体の創造力の衰退です。実体資本主義が金融資本主義に凌駕されて衰亡することは、単に経済成長の問題にとどまりません。人間社会が資本を新たに創出し続ける能力、創造行動の退化をももたらします。実体経済の減退がその原動力である人間の創造行動を衰弱させる因果循環サイクルです。実体経済衰退が人間社会に創造力の持続的減退をもたらし、さらにその結果の経済閉塞が、地下資源やエネルギー資源あるいは領土名分の生産力などの争奪、さらには一時的とはいえ軍需による経済成長、を期待した、国家間紛争や戦争を常態化させているのです。
であれば、新たな経済価値である資本を作り出し続ける創造力が世界に溢れる状態になれば、そしてそれが世界中の経済閉塞を打開し持続的な進化成長を促せば、どのような政権、政治形態、であれ戦争などを経済閉塞打開の手段として実行する必要は無くなります。
そのためには、実体経済の成長とその原動力たる創造力を最優先で追求する覚悟が必要です。そしてこれが、戦後日本の廃墟の中で高度経済成長政策を起動した池田勇人首相が後世に託した念願でもあります。
以下引用は池田勇人首相が後世に託した二つのメッセーです。日本経済成長の最高目的は世界平和であり、日本社会の人々はそのために必要な「考える叡智」と「自由な意思」を発揮せよとの伝言です。日本の経済成長を世界に拡大する創造行動への限りない期待が込められています。
日本経済をどう運営するか (「均衡財政」池田勇人 1952 実業之日本社刊)
一、日本経済運営の目標
われわれは、心から世界平和の維持を念願する。だから、日本経済の運営にあたってもまた、この念願を実現するために、必要な経済条件を造り出すことが根本の目標とならなければならない。では、どういう経済条件が世界平和の維持のために必要だろうか。
第一には、国民の生活水準の向上をはかること。第二には、失業者を減らして完全雇用を維持すること。第三には社会福祉の増進をはかること。第四には、これらのことを、わが国だけで実現するのではなく、他国と互いに協力しつつ実現して、世界人類全体の安定と福祉を増進してゆくこと。大体この四つである。
これらは、いずれも互いに関連し合っているものであるが、せんじつめれば、それは日本経済の発展というか、高度化というか、そういう姿において、実現されるものであるといえよう。その裏付けとなるものは、結局、経済基盤の充実、強化ということでなければならない。
(一)国民生活水準の向上
国民的な貧困を、戦争に訴えて、領土や勢力圏の拡大によって克服しようと考え、その戦争準備のために、逆に国民生活が圧迫されるという矛盾、そしてとどのつまりは、戦敗国はもちろん、戦勝国も戦争の被害とその影響のために、長い間苦しむといった矛盾を、人類は歴史のうちに繰り返してきた。第二次大戦は、このような矛盾に終止符を打つものとしたい。歴史は必ず繰り返すものだ、という考え方は、人間が人間たる資格を放棄するものである。私は人類が、自らの不幸を避けなければならないと「考える叡智」と、これがために自らを律する「自由な意思」を有することを信じる。
「ものつくり」と「おもてなし」の創造行動
創造行動や創造力は特殊な高度能力と思われがちです。しかし、それを資本を新たに創出する能力と考えればどうでしょうか。日本社会の二千年の水稲耕作従事者を含めて、現代の「ものつくり」と「おもてなし」の価値創造を日常的に実践している人々のすべての行動が創造行動であることがわかります。(「創造力プログラミング」大中忠夫・日下幸徳 共著 電子書籍2022改訂新版)
この日本社会の創造行動、他者に尽くす「おもてなし」の意識に基づいた「ものつくり」の意識と行動、を基盤とする「ものつくり」資本主義をさらに未来に向かって進化させ続ける。これが池田勇人首相の夢と期待を引き継ぐわれわれの使命ではないでしょうか。
そしてそのためには、個人も組織も社会も日々未来に向けて持続的に進化しつつあると自ら確信できる社会環境が必要です。それを醸成する土壌が、「ものつくり」資本主義社会を世界と未来に向けて伝道するための、新たなそして限界のない挑戦課題です。明確で具体的な目標が未来を示し、同時に、その未来への進化進捗を確認させてくれます。
「ものつくり」資本主義社会の未来挑戦基盤
日本企業社会がその基盤となっている「ものつくり」資本主義を世界に伝道するために挑戦すべき命題としては、どのようなことがあるでしょうか。どのような命題であれそれらの究極の目標は、人間社会の平和共存と地球環境の保全ということでしょう。それは人間社会の未来構築であり、その本質は人間と人間社会の地球環境保全者としての果てしない進化の追求です。
とはいえ、現代日本企業社会にそのような第一歩を踏み出す力があるのか?単なる夢物語ではないか?そのような疑念、疑問が起きるのは当然です。
しかしその力の源泉基盤は既に実現しています。過去60年間に企業社会が蓄積してきた900兆円の純資産 (本論文 第1章図6、「日本株式会社 新生記」第1巻 第5章)です。そしてその背後には2025年現在2000兆円を超える家計資産の存在 (注:日本銀行・調査統計局2025.03.21速報では2024年末時点で2230兆円)もあります。特に900兆円の企業社会の純資産は、企業経営者が覚悟さえすれば、日本社会からグローバル社会全体の経済成長、そして人間社会全体の平和共存と地球環境保全を実現する長期投資力を生み出す豊富な源泉となります。
なお少し付け加えれば、幸か不幸か、日本企業社会には、この蓄積された豊富な純資産をいつまでも寝かせておくことができない状況も迫りつつあります。この900兆円純資産は、金融資本主義社会からの「同意なき買収」という合法的収奪行動を誘引する魅力対象でもあるからです。これを積極的に長期投資することは「ものつくり」資本主義社会が収奪されないための最高の防衛策でもあります。(「『同意なき買収』に対する三段階防波堤論」大中忠夫2024)
「ものつくり」資本主義社会の三つの未来挑戦命題
では「ものつくり」資本主義社会の未来進路を開く挑戦命題、とはどのようなものでしょうか?日本社会の個人も会社も社会も、今日よりも明日、そして明日よりもその先の未来を期待し追いかけ続ける思いと行動を引き出し続ける目標をどう設定するか?これを覚悟と希望を持って設定することから未来への挑戦が始まります。本論文でも日本企業社会が掲げるであろうと思われる主な3つの命題について、その究極の意義、目標を考察してみたいと思います。
挑戦命題1.AI開発と活用 ―「ものつくり」資本主義の進化のために
AIについては、人間が担ってきた機械的労働や計算の進化代替メカニズムとしての活用が一般的には想定されているようです。しかしそれ以上にAI開発と活用には人間社会にとっての重要な意義があります。AIの設計、操作、監視、保修、改良、そして進化に携わることで、人間自身の創造行動が進化し続けることです。そしてそれが新たな人間社会の仕事、人間であればこそできる仕事、を作り出します。さらには人間とは何かの追究、人間そのものの研究やそれが生み出す自然科学工学技術、も進化し続けます。このAI開発と活用の意義は既に半世紀前の1970年代に米国カーネギー・メロン大学のノーベル賞経済学者H.サイモンによっても提起されています。(『菊と刀とビジネススクール』 大中忠夫 1985「欧米ビジネススクールへの道 」三菱商事広報室編 ) Data Download: https://researchmap.jp/nucbaonaka/published_papers/41460472
なお、現代社会では、AIの暴走に対する警告や懸念も溢れていて、AI研究開発には反対意見も少なくないでしょう。しかしながら、AIが暴走するプログラミングもそれを制止するプログラミングも人間が手掛けるものです。さらには意図的に犯罪や戦争の道具として開発されることも当然にあり得ます。しかしこれらを凌駕、抑制するAIを造り出すのも人間です。AIプログラミングに本格的に従事している人々は、この因果関係についても内心では冷静に受け止めているでしょう。それらのすべての葛藤が人間の究極の存在意義を追究し続ける創造力進化のための連鎖です。
ただし、AIによる洗脳には万全にも万全の警戒が必要です。人間社会はすでに二千年にわたり自らがプログラムした金利という名のAIに洗脳され続けてきたのですから。AIプログラミング教育は企業でも導入されつつあり、中高等教育でも必須となるでしょうが、AIの制作のみでなく制御も今後の人間社会にとって必須技術として磨き続けられる必要があるでしょう。
なおここで一言、繰り返しになりますが、AI開発研究は決して非人間性を追求するものではありません。その教育と研究が探求し続ける根本命題は、むしろ逆に、人間とは何か、人間は何を目指して進化すべきか、人間はどこから来てどこに向かうのか、を絶え間なく考え続ける人間性追求の研究学習行動です。
そこでもう一つ。AI開発にともなって、AIは人間の知能を超えるか?といった議論も盛んになりつつあるようです。しかしそこには人間の知能とは何かについての明確な定義が見当たりません。人間はまだ自身の知能とは何かを見極めることができていないのです。さらには人間知能が進化し続ける可能性も考慮せず、これを超えるAIが生まれるか否かなど議論することに現実的には意味や価値はありません。
挑戦命題2.地球環境保全
国連主導のSDGs(Sustainable Development Goals)運動は人間社会を含めた地球環境の持続的な進化を17項目で提唱しています。それらは平和共存、基本的人権の尊重、エネルギーと生産(経済)成長、地球環境保全の4つにまとめることもできます。また最近では企業や社会活動のみでなく初等から高等までのすべての教育機関でもSDGsの取り組みが始まっているようです。
この運動は企業経営研究の視点では、フリードマンの『企業は株主財産』提起で生まれた「株主第一主義」名目下での企業経営行動の自由の制約と束縛、そしてその結果出現した「短期業績重視経営」から企業社会を再び解放するものです。これは実体経済を支配し収奪し続けた結果、実体経済基盤を衰退させてしまい、金利インフレ経済成長に依存せざるを得なくなった金融資本主義社会が、実体資本主義を復活させる貴重な機会でもあるのです。
その具体的テーマを考え実現に取り組むことで地球環境保全も、AI開発と同様に人間と人間社会の創造力を限りなく必要とする命題となります。
- 森林資源の再生と砂漠の灌漑
- 海洋資源の保護とマイクロプラスティック回収
- 天然資源のリサイクル
- 使用済核燃料(プルトニウム)の既存原子炉での再利用 (MOX燃料) 推進
- 既存二大軽水炉構造(PWRとBWR)の統合再設計による飛躍的な安全性向上
- 水素燃焼エネルギー開発(水素核融合以前に現実的な水素燃焼の活用)
- CO2削減と再利用サイクル
- 地球温暖化対策
- 化石燃料から太陽光エネルギーへの転換
- 中央集中発電から戸別分散発電へ転換(膨大な送電エネルギーロスの解消)
- 消費廃棄物再利用サイクル
- 希少生物、雑滅危惧種の保全
- 自然動植物環境の保全
- 植物性蛋白食物開発
- グローバル食料生産供給システム
- 大規模災害予知と避難システム
- ウイルス性パンデミック予防と治療のためのグローバル体制
など
挑戦命題3.企業と企業社会の革新的進化
これは、「会社」を個々人と組織とさらには外部社会が相互に影響し合って、創造力を醸成進化させ続ける理想的な環境にするための革新行動です。実体経済をその基盤要素として進化させ続ける会社自体の進化命題です。
ということで、筆者のような旧世代の思いの及ぶ命題ではありません。それはわれわれ旧世代には想像もつかない人と組織と社会の高度なネットワークの世界でしょう。もし敢えて一つ思いを述べるなら、それは人間と社会の多様な創造力に日々折々に感動しながら、それらの相乗的な進化を、当然のごとく探求し続けるグローバル・ネットワークの世界なのでしょう。
なぜ会社を進化させ続ける必要があるのか?
とはいえ、なぜ会社、日銀ゼロ金利30年を経た2025年の日本株式会社、を今後もさらに進化させ続ける必要があるのか?これについては、戦後80年の日本の高度経済成長時代を生きた証人として、明確に書き残しておく必要があるでしょう。
それは、2025年の日本株式会社が、現代グローバル社会で唯一の未来社会へのパスポート、人間社会を未来に導く人間組織モデル、であるからです。
社会全方位に向けて価値を産出し、その対価報酬もまた関係者全員に、すなわち株主、社員、協力会社、社会の全方位に配分する。しかしながら、さらに産出価値である新たな資本をすべて配分するのではなく、会社本体の純資産として、いわば共同財産として、蓄積し循環成長に投資する。このような人間集合体がこれまで人間史に存在したでしょうか?
これが、21世紀日本の「会社」なのです。ミハイル・ゴルバチョフが「最も先進的な社会主義」と断言し、鄧小平が「白い猫でも黒い猫でも」と提起した、人間本来の資本主義社会、を出現させている日本株式会社です。
人間が創造する純粋資本が、金利と敢然と決別すれば、資本主義vs社会主義といった時代遅れの無意味なイデオロギー対立などを超えることも可能となり、さらにはその二つの対極理念が合体した究極の共同経済社会をも生み出します。その純粋資本を産出し続ける「会社」がこの21世紀に日本社会に出現しているのです。日本株式会社は、未来に向けて進化し続ける人間社会のあり方の一つの実証モデルなのです。
そしてこれを起動したのが、戦後の廃墟の中から、軍需経済政策を厳然と放棄し、世界平和共存を最高使命とする経済成長を追究した人々でした。この事実を未来世代に伝えることは、戦後80年の日本経済社会史を目撃体験したわれわれ旧世代であればこそ可能であり、忘れてはならない最終使命でもあるでしょう。次世代の皆さん、どうかこの「会社」を未来に向けて進化させ続けてください。
金利資本主義の終わり「ものつくり」資本主義の始まり
2025年現在、人間の創造行動によって進化した人間社会が、その存続を深刻に危ぶまれるまでになっています。その直接の原因は、突き詰めればグローバル経済全体の成長低迷、特に先進軍事大国での経済閉塞です。それが人間社会の自由と民主主義を圧迫し始めてもいます。しかしその経済停滞、閉塞の根源が過去二千年にわたる金利AIの暴走であるとすれば、どうでしょうか?人間社会全体が人間の尊厳そのものでもある創造力を大規模に活性化して、実体経済成長を追求する軌道に戻ることで、すべては解決に向かい始めるのではないでしょうか?
2025年は、そのAI暴走を止めて、新たな経済成長命題として実体資本主義、「おもてなし」の利他意識に基づく「ものつくり」資本主義、を高く掲げて人間社会経済の新たな進化を起動すべき時でしょう。
日銀ゼロ金利30年が扉を開けた未来は、金利資本主義時代の終わり「ものつくり」資本主義の時代の始まり。そしてこれは、金利資本主義の終わり人間資本主義の始まり、金利史の終わり新たな人間史の始まり、でもあります。
それは金利の自動増殖性を排除した人間の創造力に基づく純粋な資本主義の始まり。80年前の廃墟の中で、池田勇人が起動した純粋資本主義の基盤に、ジョン・メイナード・ケインズ、鄧小平、ミハイル・ゴルバチョフらの先人たちがさまざまに夢見た、理想の社会主義あるいは共産(共創)主義を構築する、人間社会の新たな進化の始まりでもあるでしょう。
日銀ゼロ金利30年で出現した日本株式会社。社会全体のために価値創造しその対価報酬分配後の資本、純資産、を会社共同財産としてその蓄積、投資の成長循環を追究する人間組織集団。それらが推進する経済社会全体の進化成長。これは人間史にまぎれもなく初めて出現した、自由主義、資本主義、社会主義、共創主義の融合世界です。私たちはこの人間史の大きな転換点に生きています。