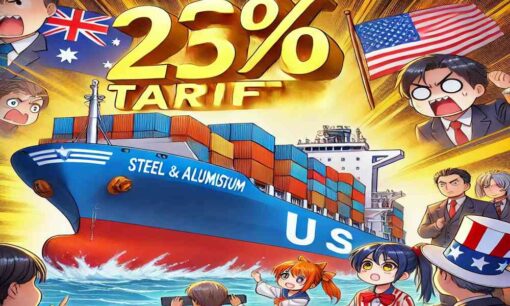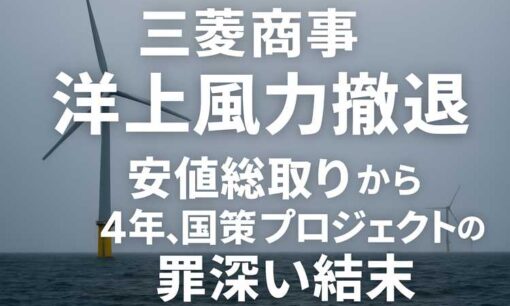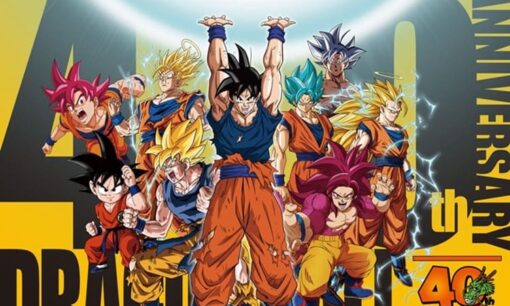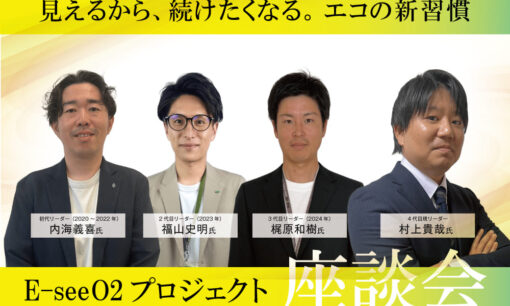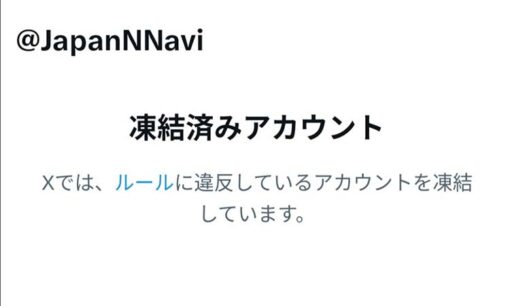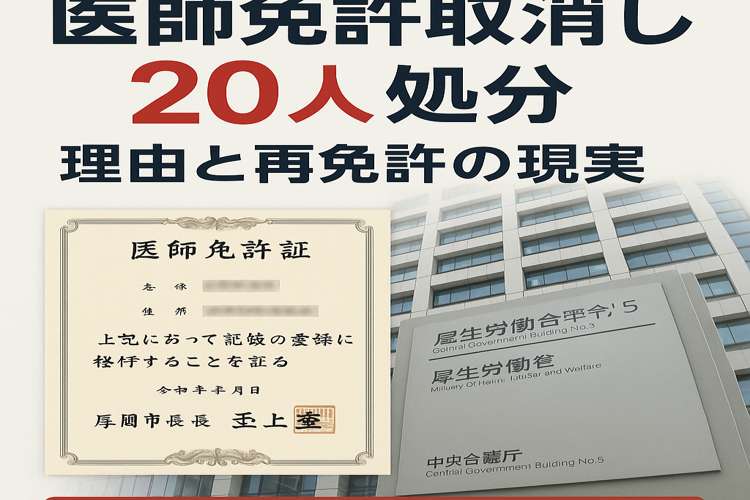
厚生労働省は2025年8月6日、医師12人と歯科医師8人の計20人に対し、医師免許の取消や医業停止などの行政処分を行うと発表した。処分の発効日は8月20日で、今回の対応は年内2度目となる。3月にはすでに22人が処分を受けており、2025年の累計は42人に達した。
医師免許は一生涯の職業資格と捉えられてきたが、その前提が今、大きく揺らいでいる。医療従事者が起こした不祥事に対し、行政処分がより厳格に行われるようになってきた背景には、医師免許制度自体の「自浄作用」と「社会的信頼の維持」という大義がある。
有罪判決や不正行為が処分の主因
今回の20人に対する処分はすべて、厚生労働省の審議機関である「医道審議会」での審査を経て決定された。処分の種類には、医師資格の完全剥奪である「免許取消」、一定期間の診療禁止となる「医業停止」、厳重注意に相当する「戒告」の3段階がある。
処分理由の多くは刑事事件の有罪判決であり、中でも性犯罪や薬物使用に関するものが年々増加している。2025年3月の処分では、詐欺や児童ポルノ法違反による免許取消のほか、複数の性犯罪・薬物関連による医業停止も確認された。
医師特有のリスクと社会的影響
医師という職業は、薬物へのアクセスや密室での診察、患者との信頼関係などの特性から、特定のリスクに晒されやすい。たとえば以下のような犯罪に巻き込まれる可能性がある。
- 薬物犯罪:医薬品へのアクセスの容易さゆえ
- 性犯罪:患者との上下関係や閉鎖空間を悪用
- 税法違反:高収入による脱税や申告漏れ
- 医療過誤:業務上過失致死傷罪への発展
- 医師法違反:名義貸しなどの不正行為
また、医師による犯罪は社会的インパクトが大きく、ベリーベスト法律事務所によれば、実名で報道されやすい傾向にあるという。社会的信用が高いからこそ、転落した際の影響は大きい。
処分後の再起は可能か 再免許制度の現実
一度免許が取消された医師にも、「再免許制度」が存在する。ただし、そこに至るまでのハードルは極めて高い。
再免許の条件は以下のとおりだ。
- 処分理由に該当しなくなっていること
- 原則5年以上の経過(罪状により10年)
- 再教育・倫理研修の受講
- 更生の証明・反省文の提出
- 厚生労働大臣の裁量による許可
条件を満たしても、免許が必ず再交付されるとは限らない。仮に再取得できたとしても、医療機関側が採用を敬遠する傾向もあり、現実的には「職業としての医師」に復帰するのは非常に難しい。
制度は厳しすぎるのか?医師免許取消の国際比較
日本の医師免許取消制度は「厳しすぎるのではないか」という意見もあるが、国際的に見てその位置づけはどうか。欧米諸国と比較すると、次のような違いがある。
- アメリカでは、各州の医師免許委員会が判断し、免許取消後の再取得には再試験・長期研修を義務づけている。処分歴は公表され、誰でも確認できる仕組みがある。
- イギリスでは、GMC(General Medical Council)が医師の行動規範に違反した場合の監督を行っており、誤診だけでなく「患者への態度」なども対象になる。再登録も厳しい基準がある。
- ドイツでは、免許取消はまれだが、医師会による職業規範違反への厳格な監視が行われており、行政処分に至る前の指導が充実している。
日本も、厚労省の医道審議会という独立した制度を持つが、再免許の過程や支援体制は他国に比べて未整備な部分がある。制度的には厳格だが、透明性や情報公開の点ではさらなる改善が求められる。
あなたの医師は大丈夫か?簡単にできるチェック方法
今回のような報道を受けて、「自分が診てもらっている医師が本当に安全なのか?」という不安を抱く患者も少なくない。実際に医師免許の処分歴を調べる方法は存在する。
厚労省・地方厚生局での確認
- 厚生労働省が過去に行った行政処分は、「医道審議会議事要旨」としてWebサイト上で公開されている。
- 氏名・処分日・処分理由などが記載されており、検索可能。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iryou_234153.html
医師・歯科医師の資格検索サイト
- 各都道府県の医師会や医療安全支援センターが提供する検索ページでは、医師の資格確認や所属医療機関を調べることができる。
例)東京都医師会「医師検索ページ」
https://www.tokyo.med.or.jp/
SNSでの口コミや報道も補完的に活用
ただし、ネット上の情報には誤報も多く、一次ソース(厚労省などの公式情報)を確認することが何よりも重要だ。
医師免許取消が問いかけるもの
「医師であれば一生安泰」という神話は崩れつつある。医師免許取消制度は、医療の信頼性を守るために不可欠な制度だが、その一方で、処分の過程や再起のあり方に対しても議論の余地は残されている。
現場の医療従事者が抱えるリスクをどう軽減し、再教育や社会復帰支援をどう設計していくのか。制度の厳格さと寛容さ、そのバランスが今後の医療界の信頼再構築の鍵を握ることになるだろう。