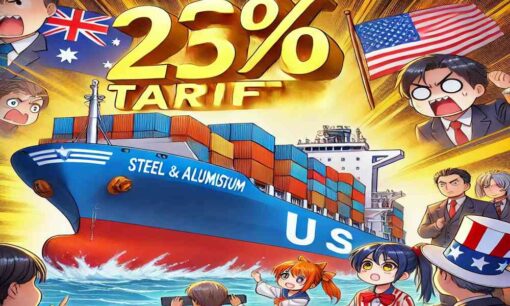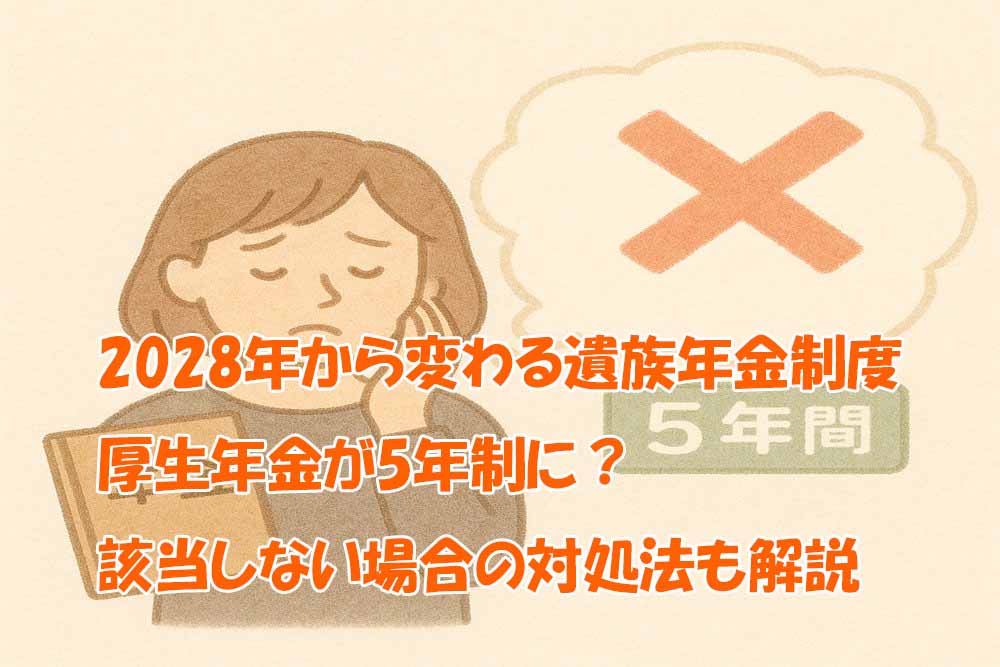
2025年6月、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会で可決された。これにより、遺族年金制度にも大きな見直しが加えられ、特に「遺族厚生年金」の支給ルールが2028年度から段階的に変更される。
本記事では、遺族厚生年金の基本的な仕組み、対象、申請手続き、支給額、そして支給対象外や支給終了後の代替制度についても詳しく整理する。
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者が死亡した際に、その被扶養者である遺族に支給される年金。公的年金制度の「2階部分」に相当し、遺族基礎年金よりも幅広い対象者が支給対象となる。
支給対象と受給条件
被保険者が死亡した場合の条件
次のいずれかに該当することが必要:
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡
- 被保険者期間中の病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡
- 障害等級1級・2級の障害厚生年金受給中に死亡
- 老齢厚生年金の受給資格を有していた人が死亡
遺族の優先順位(支給は1人のみ)
| 優先順位 | 支給対象者 | 要件 |
|---|---|---|
| ① | 子のある配偶者 | 要件なし |
| ② | 子 | 18歳の年度末まで or 障害等級1・2級で20歳未満 |
| ③ | 子のない配偶者 | 55歳以上(支給開始は60歳) |
| ④ | 父母 | 55歳以上(支給開始は60歳) |
| ⑤ | 孫 | 子と同じ要件 |
| ⑥ | 祖父母 | 55歳以上(支給開始は60歳) |
支給額の目安
- 被保険者の報酬比例部分の3/4(75%)を年金として支給
- 例:報酬比例部分が年120万円 → 年90万円支給
申請の流れ
- 年金事務所または市区町村窓口で申請書類を受け取る
- 必要書類を揃える(死亡診断書、戸籍謄本、収入証明等)
- 書類を提出(窓口または郵送)
- 約3〜6か月後に審査・支給開始
制度改正:2028年から「5年打切り制度」導入
改正後の大きな変更点:
- 30歳未満で子のない配偶者に対し、支給期間が5年に制限
- 対象外の配偶者は、終身支給を維持(子がいる、または30歳以上など)
打切り後の代替支援制度
5年支給終了後も、一定の条件を満たせば支援を受けられる。
継続給付制度(収入が一定以下の人向け)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 5年の有期給付を終えた人のうち、収入が少ない人 |
| 所得基準 | 月収約10万円以下なら全額支給。20〜30万円超で段階的に打切り |
| 上限年齢 | 原則65歳まで |
有期給付加算
- 5年間の有期支給期間中、給付額を従来の約1.3倍に引上げ
- 報酬比例部分の満額(100%)を支給する仕組み
死亡時分割制度(将来の老齢年金加算)
- 婚姻期間中の被保険者の厚生年金記録を配偶者に加算
- 65歳以降の老齢厚生年金の受給額が増える
遺族厚生年金の受給要件に該当しないケースと対策
以下に、制度の「対象外」となる典型例と、その際に利用可能な支援策を表にまとめる。
受給要件に該当しない代表的ケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 厚生年金に加入していなかった | 国民年金のみ加入者が死亡。配偶者に子がいなければ遺族基礎年金も不支給 |
| 保険料未納により受給資格を満たさない | 未納期間が長く受給権なし |
| 子のない若年配偶者(支給順位下位) | 子のある遺族が優先されるため対象外 |
| 内縁関係、外国籍で生計維持確認不可 | 実態として扶養が確認できないと不支給の可能性 |
代替となる主な支援制度(ケース別)
| 状況 | 活用できる支援制度 |
|---|---|
| 収入・資産がなく生活困窮 | 生活保護(住宅・生活扶助など) |
| 就労・自立を目指す | 自立支援相談事業、就労支援 |
| 子どもがいるひとり親世帯 | 児童扶養手当(自治体によって加算あり) |
| 子の教育支援 | 就学支援金、奨学金制度(高校・大学進学支援) |
| 雇用保険未加入で減収 | 住民税非課税世帯給付金など臨時給付制度 |
まとめ
遺族厚生年金は、遺族の生活を支える重要な制度だが、2028年度以降は制度改正によって一部支給が「有期化」される。とくに30歳未満かつ子どものいない配偶者には5年の時限措置が適用され、終了後の生活保障は継続給付制度や就労支援制度に委ねられる。
また、制度自体に該当しないケースも一定数存在し、その場合でも生活保護や児童扶養手当などの補完的制度の活用が不可欠となる。
遺族年金の仕組みは複雑で個別性が高いため、早い段階で社会保険労務士や自治体窓口への相談を行い、自身の生活設計と制度適用可能性を確認しておくことが、将来の安心につながる。