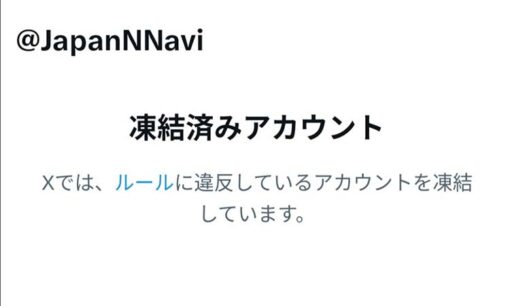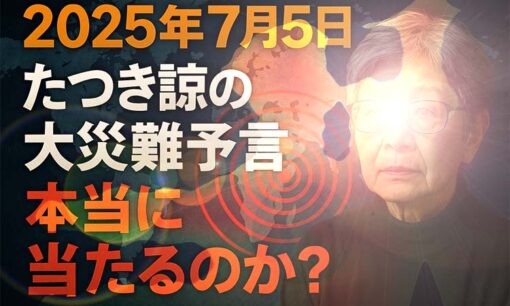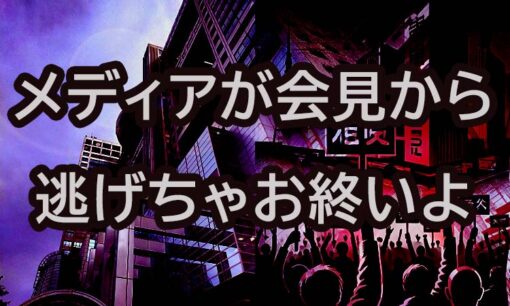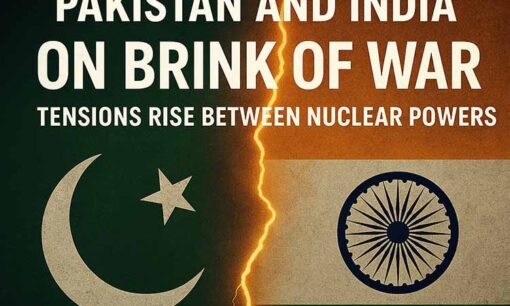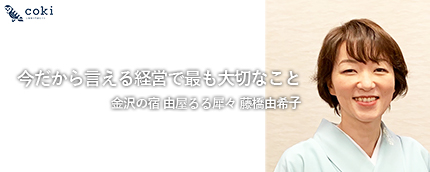YouTubeチャンネルが突如削除 拡大する「BAN文化」と言論の限界
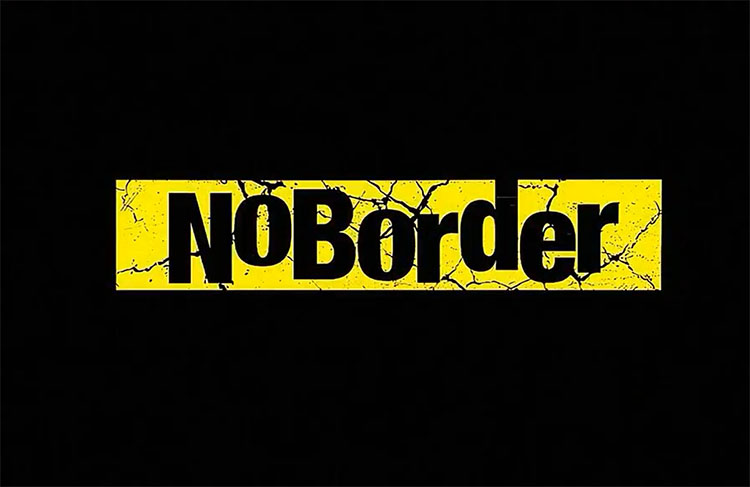
連続起業家であり、格闘技イベント「BreakingDown」のCOOも務める溝口勇児氏(40)が運営していたYouTubeチャンネル「NoBorder」が、7月20日までに全動画削除のうえでチャンネルごと消滅した。削除の理由は不明で、YouTubeからの公式通知も明らかにされていないが、SNSでは「政治的な圧力ではないか」とする声も多く上がっている。
溝口氏は自身のX(旧Twitter)で「NoBorderのチャンネルがいきなりバンされて動画全消し。笑える」と投稿。「こういった理不尽があったほうがやる気になる」「徹底的に抗いたいし、全部ひっくり返せる力がほしい」と心境を吐露し、「YouTubeの窓口や偉い人にも抗議しまくる」と怒りをにじませた。
SNSでは、「兵庫の闇、7/18の前編が核心に近かったかも。優勝パレード&警備会社、AIガクトが興味深い事を言ってました」「安倍首相暗殺説は攻め過ぎていたからな」といった意見が広がっている。
たしかに番組が用意した登壇者は皆個性的であり、それに輪をかけるかのようにAIガクトが横からぶっ飛んだ理論をぶっこんでくるという布陣は面白く、エンタメとしてなんか見たくなってしまうが、眉唾物な意見も多く、見る人が見れば「陰謀論の流布」と断定されてしまうような危うさをもっていることは確かである。
一方、一部のYouTuberたちは「NoBorder」運営側が自作自演で投稿を削除したのではないかとの理論を展開している人もいる。
はたして真相は如何に?
削除の背景にある「ガイドライン」運用の曖昧さ
YouTubeでは通常、チャンネル削除(いわゆる“バン”)は、コミュニティガイドライン違反が複数回累積された場合や、重大なポリシー違反が一度にあった場合に行われるとされている。具体的には、誤情報、ヘイトスピーチ、暴力的表現、スパム行為などがその対象となる。
しかし、NoBorderチャンネルが削除されたという告知がなく、動画一本一本が段階的に削除された形跡も見られない点は不可解だ。過去にも、社会的・政治的な内容を扱うチャンネルが「誤検知」でBANされた事例は少なくない。
特に政治的センシティブなテーマや、既存権力への批判が含まれる動画は、自動検出システムによって不当に削除されるリスクが指摘されてきた。
今回の削除に対してYouTube側が今後どのような説明を行うのかは不透明だが、プラットフォーム運営の“透明性”という点で、溝口氏の抗議は一石を投じるものとなりそうだ。
依存構造としてのプラットフォーム・リスク
今回の事態はまた、YouTubeという巨大プラットフォームに依存した情報発信の構造的な脆弱性を露呈したとも言える。チャンネル削除によって、過去の動画アーカイブが一夜にして消失するというリスクは、ジャーナリズムや表現活動にとって致命的な打撃となる。
とりわけNoBorderは、「時の権力にタブー視されてきたテーマに切り込む」ことを掲げた新プロジェクトであり、単なるエンタメではなく社会的意義を帯びた発信が主眼とされていた。動画削除によりその議論の痕跡がすべて消えてしまったことは、言論の健全性に対する懸念を呼ぶ。
一部では、代替プラットフォームとして「Rumble」や「Substack」などの非GAFA系発信インフラへの移行を提案する声も出ている。今後、溝口氏が新たな発信拠点をどこに選ぶかも注目される。
SNS時代における「BAN文化」と反動
今回の件を、拡大する「BAN文化」の一端と見ることもできる。YouTubeやXを含むSNSプラットフォームでは、近年「誤情報」「ヘイト対策」「安全性維持」といった名目のもと、運営側の裁量でアカウントやコンテンツを削除する例が増えている。
その背景にはAIによる自動検出システムの強化や、政治・社会的圧力の影響もあるとされるが、その境界線は極めて曖昧である。特に今回のように、削除理由が不明確なまま言論が封じられるケースは、「表現の自由」と「検閲」の線引きを社会全体に問い直す契機となる。
SNS上ではすでに、「政界批判をしたからではないか」「見えない圧力がかかったのでは」との憶測が飛び交っており、逆に“BANされたから注目が集まる”という皮肉な構造も生まれている。