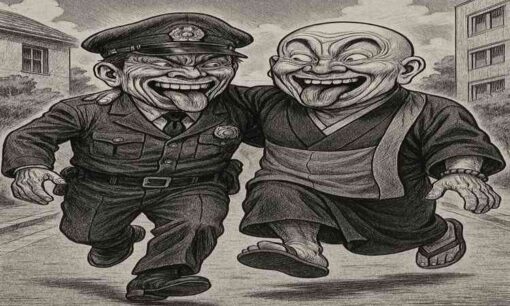76年前に策定されたまま、ほとんど見直されていない日本の保育士配置基準。その影響は現場に深刻な形で表れつつある。保育士の過重労働、子どもへの重大事故の増加、そして保育の質の低下――いずれも、慢性的な人員不足が根底にあるとの指摘が相次ぐなか、2025年6月、学識者らが「世界水準の配置基準」を目指す団体を発足させた。制度の立て直しは、子どもの命と育ちを守る社会の責任が問われるテーマとなっている。
「76年据え置き」の配置基準がもたらしたもの
日本の保育現場が抱える問題は、単なる人手不足にとどまらない。保育士の過重労働、子どもへの事故の増加、保育の質の低下――こうした問題の背景にあるのが、1948年からほぼ変わらぬままとされる「保育士配置基準」である。2025年6月26日、「子どもたちにもう1人保育士を!」を掲げる学識者らによる新たな団体が発足し、現行制度の見直しを訴えた。
この会の立ち上げには、東京大学名誉教授の汐見稔幸氏や、教育社会学者の本田由紀氏、日本総合研究所の池本美香氏らが名を連ね、多角的な視点から保育制度の改善を提案している。会の代表らは、「子どもの権利条約」の理念すら保育政策に反映されていない現状を憂い、国際水準との乖離を強く問題視した。
国際水準に遠く及ばぬ日本の配置基準
現在、日本の保育士配置基準は1歳児で「保育士1人あたり子ども6人」が原則である。2025年4月からは「5人に1人」とする加算措置が導入されたが、適用条件が厳しく、実際に加算を受けられる施設は限られている。
一方、ヨーロッパ諸国では、3歳以上の子どもに対し「保育士1人あたり子ども10人」という水準が目安とされ、保育の質と安全確保の両立を目指している。また、フランスでは保育施設に年4週間の休園期間を設け、保育者も十分に休息を取れる環境が整備されている。これにより、保育者が子どもと向き合う時間に余裕を持つことができる仕組みが築かれている。
子どもへの事故、配置基準との因果関係
全国で相次ぐ保育施設での重大事故は、こうした配置基準の不備が遠因とされている。たとえば、2023年には保育施設での死亡事故が複数報告されており、保育者の目が行き届かないことが原因とみられるケースも少なくない。
池本美香氏は、保育士の負担が限界に達しているとしたうえで、「子どもの最善の利益や発達の権利が、現状では担保されていない」と警鐘を鳴らす。子どもたちが安心して育つためには、安全面の充実が不可欠であり、その前提には「十分な保育士数の確保」があると強調した。
配置基準見直しは保育の質向上にも不可欠
教育社会学者の本田由紀氏は、保育の量と質の充実が「少子化対策」「ジェンダーギャップ是正」にも直結すると指摘した。保育が質的に保障されれば、保護者が安心して子どもを預けられるようになり、とりわけ女性の就労継続に寄与する。これは、日本社会全体の活力にもつながる。
また、保育者の待遇改善も急務である。現在の人員配置では、保育士が昼休みをまともに取れず、常に気を張り詰めた状態で勤務しているケースが多い。離職率の高さが保育士不足をさらに悪化させており、この悪循環を断ち切るには、国の制度的支援が不可欠だ。
現場からの声と政治への訴え
実行委員会のメンバーであり、東京都内の保育園園長である大西洋子氏は、「保育士たちはもっと丁寧に子どもに関わりたいと願っている。にもかかわらず、現行の制度ではその願いすら叶わない」と現場の切実な声を代弁した。
さらに、2025年7月に予定される参院選を前に、各政党に対し「保育士配置基準の改善」を公約に掲げるよう求めていく方針を示した。「保育に光を当てることは、子ども、家庭、保育士、そして社会全体に光を当てることになる」と訴えた。
配置基準見直しは喫緊の課題
保育士の配置基準は、単なる数値の話ではなく、子どもたちの命と発達を守る根幹である。配置基準を国際水準に引き上げることは、保育者の働きやすさを向上させ、子どもの事故を防ぎ、保育の質を根本から高めることにつながる。少子化の時代においても、子どもたちに寄り添う保育の姿勢こそが、日本社会の未来を支える礎となる。