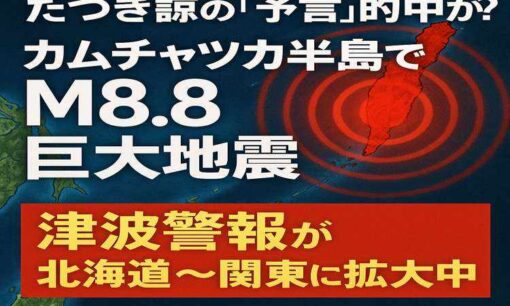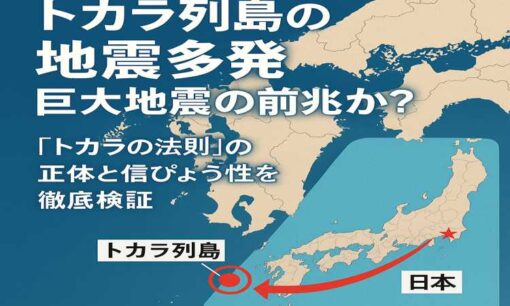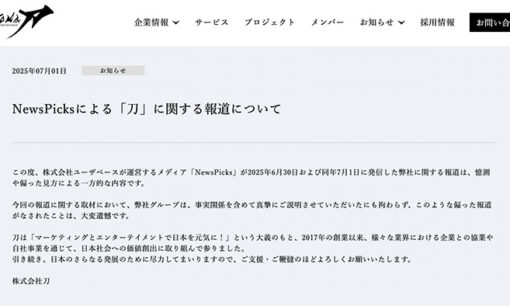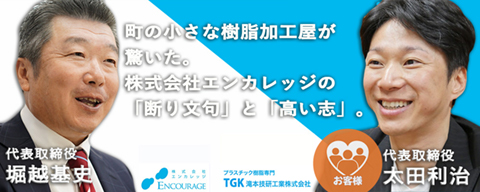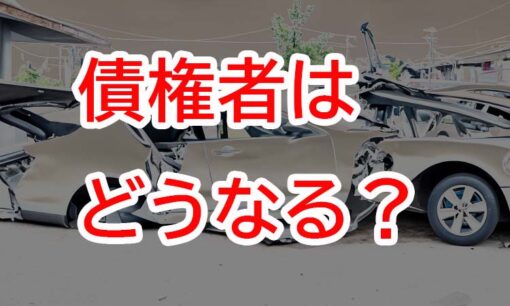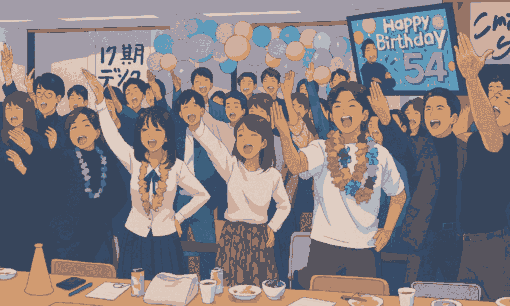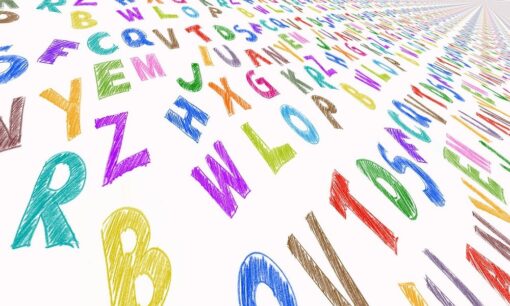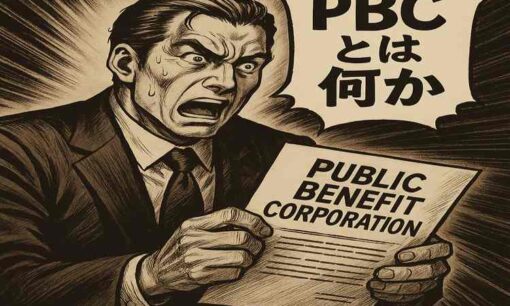「夢」が社会を揺らす日 たつき諒の予言が引き起こした“現実”
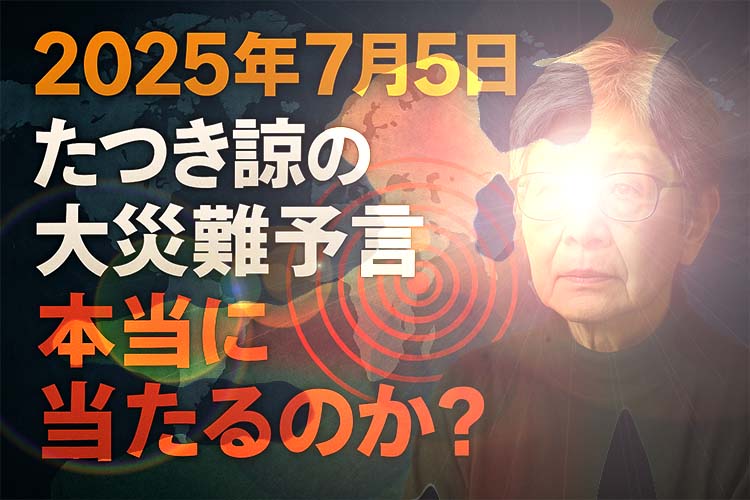
2025年7月、日本に大災難が訪れる。そんな一文が、日本社会をここまで混乱させる日が来るとは、誰が予想できただろうか。
騒動の震源地は、漫画家・たつき諒(本名非公開)氏が1999年に出版し、2021年に『完全版』として復刊された『私が見た未来』。同書に描かれた「本当の大災難は2025年7月にやってくる」という帯のキャッチコピーが、SNSを通じて炎のように広がった。
YouTubeやTikTokでは予言解説動画が数百万再生され、「2025年7月5日午前4時18分」に何かが起きるという“確定的情報”が一人歩きを始めた。
やがて事態は加速し、香港では日本行き航空券のキャンセルが続出。気象庁の野村竜一長官までもが「そのような予知は科学的根拠がない」と明言する異例の対応に追い込まれた。
だが、この予言騒動が単なる都市伝説にとどまらない背景には、現代日本社会の複雑な病理と情報経済が深く絡んでいる。
予言が金になる時代 “スピリチュアル資本主義”の真実
『私が見た未来 完全版』は2021年の発売直後から10万部を超えるベストセラーとなり、ネット古書市場では定価の30倍以上の価格がついた。さらに、たつき諒氏の予言を“解説”するYouTubeチャンネルが次々と開設され、一部インフルエンサーは月50万円以上の広告収益を得ているとされる。
電子書籍『note』『Kindle Unlimited』では、関連本が「スピリチュアル」「災害対策」部門で上位を独占。中には『2025年7月に備える防災グッズ25選』といったタイトルの“便乗商材”がSNSで拡散され、アフィリエイト収入を得る動きも確認されている。
このように、たつき諒の予言は「恐怖をコンテンツ化」し、クリック数を稼ぎ、金に換える“情報ビジネス”の燃料となってしまった。誰が信じているかは重要ではない。重要なのは、「どれだけ拡散されるか」なのだ。
「予言は社会の合わせ鏡」 マスメディアが“沈黙”する理由
また、今回の予言騒動で特筆すべきは“マスメディアの沈黙”である。YouTubeやTikTok、Xでは連日この話題で持ち切りにもかかわらず、全国紙や大手テレビ局は一貫して慎重な報道姿勢を取り続けている。気象庁長官が記者会見で「科学的根拠のないデマ」と明言したにもかかわらず、それを大きく扱った報道はほとんど見当たらない。
背景には、いくつかの“触れづらい要因”がある。
ひとつは、過去の「ノストラダムスの大予言」や「マヤ暦の人類滅亡説」などで、テレビや雑誌が扇動的に騒ぎすぎた反省がある。1999年当時には、ゴールデン帯で終末論を特集した番組が高視聴率を叩き出し、その後に「煽った責任」が問われた。ゆえに現在のメディアは、“予言”というワードに対して過剰に警戒している。
もうひとつは、“信じる人がいる”という現実だ。かつてなら一笑に付せた都市伝説も、今ではSNSを通じて“信仰圏”を形成してしまう。ひとたび「信者をバカにした」と炎上すれば、メディア不信や広告離れに直結しかねない。だからこそ、報道は「スルーすることで火を消す」という消極的スタンスを取る。
だが、それが逆に「隠されている」「裏に何かある」という陰謀論を助長しているのもまた事実である。
予言は未来を語っているようで、実は「いまこの社会の不安そのもの」を映し出す合わせ鏡なのだ。
「たつき諒って誰?」Z世代の予言依存と震災トラウマの接続点
今回の予言騒動にはもう一つ、注目すべき奇妙な構図がある。それは、「20代以下の若年層」による異常なまでの反応だ。TikTokでは「#たつき諒」「#2025年7月5日」のタグが数千万回再生を超え、Instagramのストーリーズでは“夢に備えて備蓄しよう”というハッシュタグ運動まで出現した。「気象庁が否定したから逆に怪しい」と語る大学生や、「信じてるって言うとバカにされるけど、備えておくのが一番安全」と語る高校生も。
背景には、彼らが東日本大震災(2011年)を「幼児期に経験したトラウマ世代」であることがある。揺れる教室、防災訓練、保護者の顔、そしてテレビに映った津波の映像。明確な言葉で記憶されていなくとも、身体に“地震の不安”が刻み込まれている世代なのだ。さらに、新型コロナや戦争報道などを通じて「明日がどうなるかわからない感覚」が“日常”になっている。
心理学の研究によれば、不安の高まりは「意味のある物語」への依存を強化するという。つまり、「地震が起こるかもしれない」という漠然とした不安は、「7月5日に起こる」と“確定情報”に変換された瞬間、人間にとって処理しやすい情報になる。
不確実性が支配する時代に、たつき諒の夢は、Z世代にとって“ひとつの納得できる説明”として機能してしまったのだ。
一方、香港や台湾では、たつき諒の予言がYouTuber「老高與小茉」の紹介をきっかけに広まり、SNS上で警戒の声が急増。実際に航空会社が日本便を減便するなど、旅行キャンセルが相次いでいる。中国語圏の一部では「風水的に危険」との見解も流布され、予言が現実の行動に影響を及ぼす社会現象となっている。
Xで繰り広げられる「信者 vs 懐疑派」の予言内戦
「備蓄したら助かる」「予言を否定する奴が滅びる」「たつき諒なんて商売だろ」「科学を見ろ」
現在、こういった2つの声が、今、SNSで真っ向からぶつかっている。X(旧Twitter)では、信じる派と冷静派に分かれた論争が激化。お互いのポストには「通報しました」「洗脳されている」などの言葉が並ぶ。
アルゴリズムはユーザーに似た投稿を届けるため、結果的に“信者は信者と”“懐疑派は懐疑派と”結びつく。これがいわゆる「エコーチェンバー現象」だ。まさに、SNS空間内で“並行世界”が形成されているのである。
その様子は、宗教戦争さながら。「信じるか否か」ではなく、「敵か味方か」になっているのだ。
花田紀凱×飛鳥新社の仕掛けと、宗教的な憶測の構造
この予言騒動を“単なる読者の熱狂”と切り捨てるのは早計だ。なぜなら、この一連の現象には、「飛鳥新社」という出版社の戦略的企図、そして編集長・花田紀凱(はなだ・きよし)氏の存在がある。
花田氏は元『週刊文春』編集長。ホロコースト否定記事で『マルコポーロ』を廃刊に追い込まれたことでも知られ、“タブー上等”の編集方針を貫く伝説の編集者だ。現在は保守論壇誌『月刊Hanada』の編集長として、旧統一教会や幸福の科学に対する擁護的論陣を張っている。
そんな花田氏が関わる出版社から“終末予言漫画”が発売されたことに、一部ネットでは「組織的な仕掛けでは?」という憶測が飛び交った。「教団による書籍爆買い」「情報操作によるアクセス誘導」「社会不安を利用した保守層の囲い込み」――あらゆる陰謀論が並ぶが、その多くは事実無根である。
とはいえ、宗教と予言の親和性は高い。たつき諒氏自身が「私は予言者ではない」と明言しても、信者的熱狂は止まらない。むしろ、「本人が否定している」という事実が、“真理に気づかれないようにしている証拠”として、逆説的に機能するのだ。
私たちは“夢”とどう向き合うべきか
『天使の遺言』において、たつき諒氏はこう記している。「私はただ、自分が見た夢を描いただけです。恐怖を広めたいわけではありません」
しかし、その夢は今やひとり歩きし、5,600億円の経済損失、国際的な観光キャンセル、SNS上の分断、そして宗教的熱狂をもたらす事態へと発展した。ここで問われるべきは、「たつき諒が当たるか否か」ではない。
「なぜ、私たちは不安に寄り添う“物語”を求めるのか」「その物語は誰が語り、誰が儲け、誰が苦しんでいるのか」そして、「自分の行動を、他人の“夢”に預けてしまってよいのか」
予言と社会不安が結びつくこの国で、必要なのは“信じる・信じない”ではない。
“考える力”である。何も起きないことを、7月の空に祈りながら。