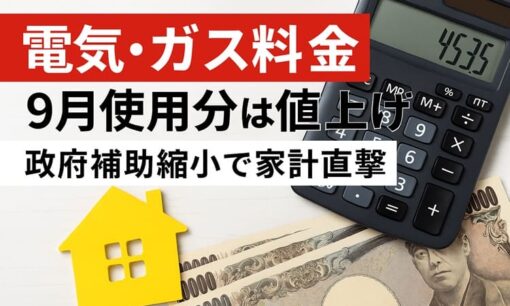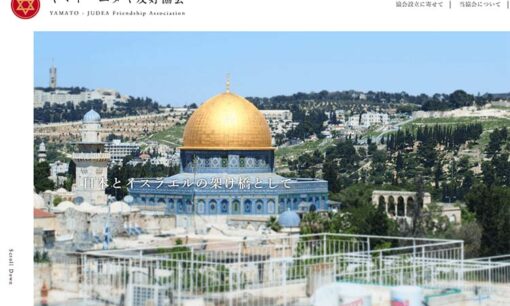出産にかかる費用の自己負担を無償化する方針について、福岡資麿厚生労働相は16日、閣議後の記者会見で「妊婦の経済的負担の軽減を図る観点から、具体的な検討を進めていく」と表明した。政府は早ければ2026年度からの制度実現を目指しており、検討の焦点のひとつには「地域ごとの出産費用の格差」がある。
正常分娩は自由診療、費用に地域差
現在、帝王切開などの医療行為を伴う出産には公的医療保険が適用されるが、正常分娩は「自由診療」と位置づけられ、保険適用外である。このため、各医療機関が自由に価格を設定でき、同じ内容の分娩でも費用は大きく異なる。
厚生労働省の「出産費用の実態調査」(2020年度)によると、正常分娩1件あたりの平均費用は全国で約50万2000円だったが、最も高い東京都では平均約62万円、最も安い鳥取県では約39万円と、最大で20万円以上の差が生じている。
| 地域 | 平均出産費用(正常分娩) |
|---|---|
| 東京都 | 約620,000円 |
| 神奈川県 | 約580,000円 |
| 大阪府 | 約550,000円 |
| 愛知県 | 約510,000円 |
| 福岡県 | 約470,000円 |
| 鳥取県 | 約390,000円 |
医療現場の反応 二極化する産婦人科医の声
正常分娩への保険適用を含む出産費用無償化については、医療現場から賛否が分かれている。
医師専用コミュニティ「MedPeer」の調査では、医師のおよそ半数が制度導入に賛成し、「妊娠・出産は医療的支援が必要な行為であり、公的保険の適用が妥当」との意見も聞かれる。特に、若年層や低所得層への負担軽減と少子化対策の一環として前向きに受け止める声が多い。
一方で、大阪府保険医協会の調査によれば、有床診療所など地域の産科医療機関の76%が「反対」と回答。理由として、「保険診療では十分な分娩収入が得られず、経営が成り立たなくなる」「サービス低下が起きる」といった懸念が挙げられた。また、正常分娩を自由診療としてきた現場にとって、報酬制度の見直しや書類負担の増加も大きな課題となっている。
「無償化で出産を軽視する懸念」は根拠薄弱か
制度導入にあたっては、「無償になることで出産が軽く捉えられ、安易に産んで捨てる人が増えるのでは」といった懸念も一部で聞かれる。しかし、児童福祉や母子保健に詳しい専門家の多くは、この見方に慎重だ。
過去の乳児院入所や乳児遺棄の事例では、
- 経済的困窮
- 望まない妊娠
- DVなどの家庭内問題
- 社会的孤立や無支援
といった複雑な背景が共通しており、「出産費用の有無」が主因ではないとの指摘がある。
また、無償化によって妊娠期からの医療機関との接点が増えることで、
- 保健師や助産師による早期支援
- 特定妊婦支援制度の活用
- 出産・子育て応援交付金による伴走型支援
などの行政支援につながる機会が増えると期待されている。
産婦人科医の宋美玄氏も、「制度によって出産が軽く見られるようになる」といった懸念に対して、「そのようなケースはごく限られ、むしろ支援との接続点を増やすことが重要」と強調している。
制度整備と周辺支援の両立が鍵に
現在、出産に際しては「出産育児一時金」として原則50万円が支給されているが、都市部ではこれを超える自己負担が常態化しており、若年層の経済的不安の一因ともなっている。
福岡厚労相は「出産費用は年々上昇しており、制度的な対応が必要」と述べており、保険適用を含む包括的な見直しに意欲を示している。
ただし、制度の実現には、
- 医療機関への適切な補填制度の構築
- 地域医療体制の維持
- 若年妊婦や孤立する妊産婦への支援強化
といった多角的な対応が不可欠となる。