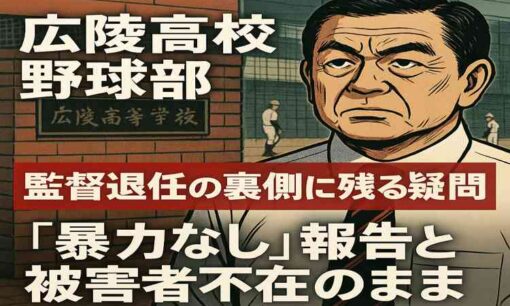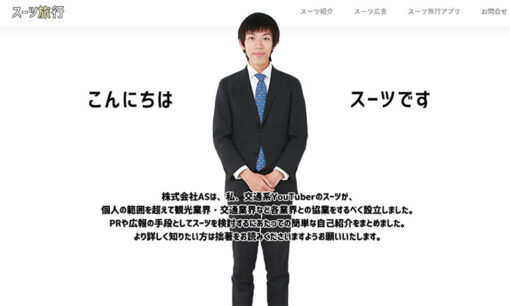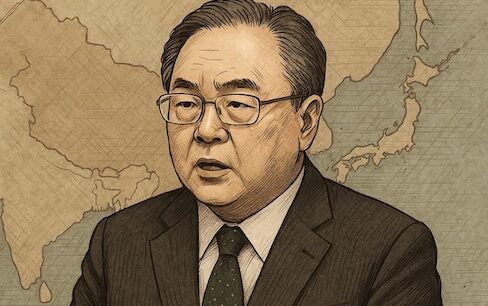物価高が続く中で、家計の支援策として注目される「子育て支援パスポート」。外食や買い物、各種サービスで割引や特典が受けられるこの制度は、子育て世帯にとって有力な助けになる一方、利用率は決して高くない。なぜ制度が浸透していないのか。その理由と今後の改善策を探る。
利用するだけで“ちょっと得” 子育て支援パスポートのメリットとは
「子育て支援パスポート」を活用すると、地域や店舗によって異なるものの、以下のようなサービスが受けられる。いずれも育児中の外出先や日常の買い物の中で「ちょっと嬉しい」「地味に助かる」と感じる内容ばかりだ。
以下の表は、全国的に知名度の高い店舗を中心とした主な特典とその効果をまとめたものである。
子育て支援パスポートの特典一覧
| ①店名 | ②特典内容 | ③特典の効果 | ④その他 |
|---|---|---|---|
| コメダ珈琲店 | ミニソフトクリーム1つプレゼント | 子どもが喜び、親も満足感が得られる | サイズは“ミニ”といいながら意外と大きめ |
| リンガーハット | 餃子3個無料 | 1品追加で満足度アップ | 食費の節約に役立つ |
| 一風堂 | 半熟塩玉子1個サービス | 子どもと分け合えて満足度向上 | トッピングの追加料金を節約 |
| いきなりステーキ | ソフトドリンク1杯無料 | 飲み物代の節約に効果的 | 特にファミリー層にはありがたい |
| マクドナルド | ハッピーセットが特別価格 | 人気メニューの割引でお得感あり | 子どもの外食意欲を高められる |
| ピザハット | 5%割引 | 宅配ピザの出費を抑えられる | 日常の食事でも利用可能 |
| ブックオフ | 5%割引 | 書籍購入時の出費を軽減 | 地味に嬉しい節約効果 |
このほか、地域によっては以下のような多様な特典も用意されている。
- スーパーでの買い物割引や、レジでのポイント付与率アップ
- 書店でのポイントアップやキャンペーン適用
- 習い事教室の入会金が半額または無料になるサービス
- 家事代行サービスの利用料割引、レンタカー利用料金の割引
また、このパスポートは登録した都道府県以外でも利用できるため、旅行や帰省時の外出先でも特典が受けられるのも魅力のひとつだ。たとえば「東京都で登録したが、帰省先の広島で子育て応援店を見つけて利用した」といった例も少なくない。
さらに、利用方法もスマートフォンアプリでの登録・提示が主流になっており、自宅で完結する。スマホに不慣れな方には、紙のパスポートを配布している自治体もあり、使い方の選択肢が広がっている点も見逃せない。
広がりを阻む5つの壁
一方、制度そのものの魅力に反して、利用が進んでいない現状がある。その背景には、いくつかの要因が重なっている。
- 制度の認知度が低い
内閣府調査では、「子育て支援パスポートを知っている」と答えた保護者は全国で4割程度にとどまり、特に若年層や転入者への周知が十分でない。 - 自治体ごとの制度名や条件の違い
全国共通で使える制度であるにもかかわらず、名称が都道府県ごとに異なり、統一感がない(例:東京都「子育て応援とうきょうパスポート」、大阪府「まいど子でもカード」など)。これにより制度の全国性が見えづらく、理解の障壁となっている。 - 特典内容に地域差が大きい
都市部では協賛店舗が多い一方で、地方では対象店舗が少なく「使える実感がわかない」という声も多い。利用価値が地域によって偏っている。 - 自己申告制への心理的ハードル
店頭で自ら「パスポートあります」と申し出る形式が多いため、気後れして利用を控える人もいる。また、制度を把握していない店舗スタッフに対応を断られることも。 - 手続きに対する抵抗感
「スマホで登録」と聞くだけで手間に感じてしまう家庭もあり、登録のハードルを下げる工夫が必要とされている。
利用促進への3つのカギ
制度の改善と浸透を図るには、以下の3点が重要となる。
- 名称とロゴの全国統一
どの自治体でも一目で制度だと分かる「共通名称・デザイン」にすることで、制度の存在感と認知度を向上させる。 - 生活動線への自然な導入
母子手帳アプリとの連携、LINE公式アカウントによる配信、学校・保育園での案内チラシなど、「自分から探さずとも目にする」導線設計が効果的である。 - 非接触・自動連携型の運用
QRコード読み取りや電子決済との連動など、提示の負担を減らす設計が望まれる。店舗側の理解促進も同時に進める必要がある。
“使える制度”を“使われる制度”に
「子育て支援パスポート」は、家庭の経済的負担を軽減し、子どもとの外出を楽しいものに変える可能性を秘めている。だが、現時点では「宝の持ち腐れ」となっている部分も否めない。
利用者の行動を変えるには、制度のわかりやすさとアクセス性が不可欠だ。そして、行政と民間事業者が連携し、「提示しやすい」「使ってうれしい」仕組みを整えることで、初めて制度は本来の力を発揮する。
制度の存在に気づいたその日が、子育て家庭の“ちょっと得”を積み重ねるスタートラインとなる。