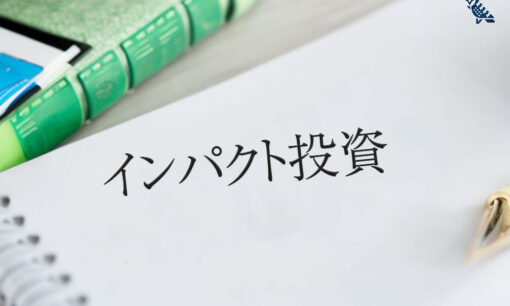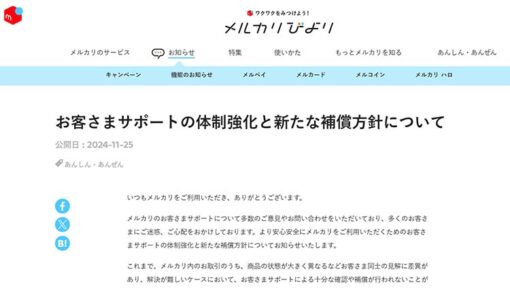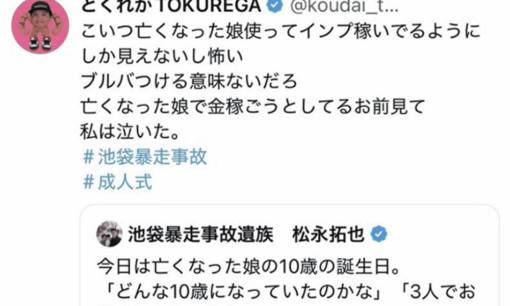精肉売場の片隅で「ご自由にお持ちください」と置かれた小さな白いキューブ。牛脂が無料で提供される光景は、日本のスーパーマーケットではおなじみだ。背景には、肉文化の変遷と化学工業の構造変化、さらに店舗サービスの歴史が絡み合う。
余り物から“サービス品”へ すき焼き文化が定着させた無料牛脂
明治期に牛鍋、昭和になるとすき焼きが家庭料理として浸透した。専門店にならい、鍋肌に脂をなじませる調理法が広がり、牛脂は「ごちそうの香り付け」に欠かせない存在となった。1970年代、総合スーパーが全国に拡大すると、店内加工で大量に生じる脂身を包装し、“タダ”で配布することで廃棄コストを抑えつつ顧客サービスを演出する仕組みが定着した。
石けん原料から余剰物へ 化学工業の転換とアジアの肉食ブーム
牛脂は19世紀から固形石けんの主要原料として重宝され、鹸化して得られるソジウムタロウエートは洗濯や洗身用の界面活性剤の主役だった。ところが石油化学の進歩で1950年代に分岐アルキルベンゼンスルホン酸塩(ABS)が登場し、洗濯機の普及とともに液体合成洗剤が市場を席巻する。
牛脂由来の石けんは泡立ちや溶解性で劣るうえコストも高く、需要は急速に縮小した。1960年代後半にはABSが河川に長く残る泡を発生させて公害問題となり、業界は1970年代により生分解性の高い直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)へ切り替えた。しかしABSもLASも石油由来で動物脂肪を必要としない点は同じで、牛脂が洗剤原料として返り咲く余地はほとんどなかった。
一方、世界的な牛肉消費の伸びが続いた結果、副産物としての牛脂は増え続けた。ろうそくや化粧品、バイオディーゼル燃料といった用途で一定量は消費されるものの、市場全体では供給過多で価格は低迷しがちだ。こうした状況では、精製済み牛脂を産業廃棄物として処理するより、店舗サービス品として配布して廃棄コストを抑える方が合理的である。
精肉売場に「ご自由にどうぞ」と牛脂が置かれる現在の慣行は、石油系洗剤の台頭による需要減と、牛肉人気が生んだ副産物過剰という二つの流れが交差して生まれた合理的な再利用策といえる。
一方、日本を含むアジア諸国で牛肉消費が拡大し、屠畜量が増えるにつれて牛脂はむしろ余剰資源となる。精製後の食用・工業用取引価格は下がり、スーパーでは「無料提供」という再利用モデルが合理的な選択肢になった。
現場の声「昔はケンネンを切っていた」
精肉担当歴20年のある店員は「かつては大型の脂身(ケンネン)を店舗で切り出していたが、人件費と衛生管理の負担から、今は精製済みの牛脂ブロック(3〜4kg/ケースで3千〜4千円)を仕入れ、サービス品として置く店が多い」と明かす。無料ゆえに大量に持ち帰る客もいるが、実のところ店舗側には“痛み”もあるという。
牛脂・ラード・鶏油――融点が語る使い分けと“胸焼け”の理由
脂は融ける温度で用途も体への感じ方も変わる。牛脂(ビーフタロー)の融点は40〜50℃と高く、室温で固まりやすい。豚脂(ラード)は34〜44℃、鶏脂(鶏油)は23〜40℃で、製品によっては26℃前後で溶けるものもある。牛脂はヒトの体温(約37℃)より高い温度で初めて完全に液化するため、胃で溶けにくく、“胸焼けしやすい”と感じる人も出る。
一方、低融点の鶏油は料理の冷めた後でも固まりにくく、ラーメンの香味油などに好まれる。
工業的視点では、牛脂は飽和脂肪酸が多く長鎖で直鎖構造が主体のため石けん・界面活性剤向けに加工しやすい。対照的に、ラードや鶏油は枝分かれした脂肪酸を多く含み、精製後もさらに分解・再合成が必要となるため工業用途では扱いにくく、食品業界での需要が中心となる。結果として市場価値が相対的に高いラードや鶏油は有料で流通し、牛脂だけが“無料の常連”として残ったわけだ。
BSEと衛生管理―「危険部位」には該当せず
2001年のBSE騒動では脂肪組織への懸念も生じたが、FDAは不溶性不純物が0.15%以下の牛脂を「禁止部位に含まれない」と位置づけており、レンダリング工程でもプリオン由来たんぱく質は分離されると説明している。国内でも個包装とロット管理が徹底され、無料提供の慣例は途絶えなかった。
道義的消費のススメ
牛脂は「捨てればコスト」の余剰物を生活者へ循環させる仕組みで成り立つ。ただし精製・包装・輸送には費用がかかる。店舗関係者は「必要分だけ持ち帰ってほしい」と口をそろえる。
タダだからこそモラルを持って受け取り、すき焼きの下ごしらえやコク出しに上手に活かす──これが“無料牛脂”と付き合う最良のマナーだろう。