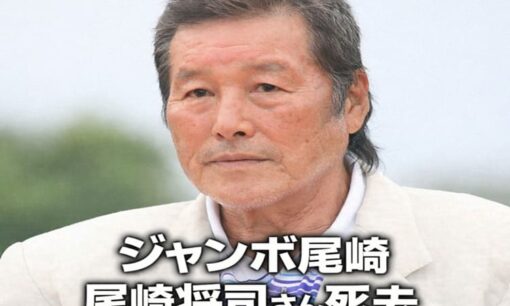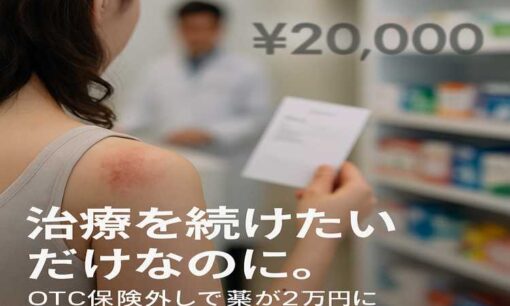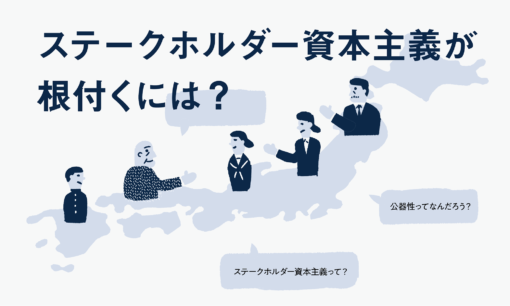社会保険料に“キャップ”はかかるのか?

第一生命経済研究所の主任エコノミスト・谷口智明氏が4月16日に発表したビジネス環境レポート「社会保険料の伸びはどこまで許容されるのか」が注目を集めている。2026年度から導入予定の「子ども・子育て支援金制度」が社会保険料にどのような影響を与えるかに着目し、政府の掲げる「社会保障負担率を上昇させない」との方針の実効性を検証している。
本稿ではその要点を紹介しつつ、負担増の先にある「社会的リターン」の可視化についても独自の視点から掘り下げてみたい。
「支援金は導入するが、負担率は上げない」の矛盾
政府は、少子化対策の新たな財源として、2026年度から医療保険料に上乗せするかたちで「子ども・子育て支援金」の徴収を始める。制度が完全施行される2028年度には1兆円規模に達する見通しだが、政府は同時に「社会保障負担率を上昇させない」と明言している。
谷口氏はこの点について、「国民所得の伸び率が社会保険料の伸び率を上回ること」が達成の条件だとし、これを“メルクマール(指標)”として提示した。つまり、賃上げなどを通じて可処分所得が拡大すれば、制度による新たな負担を吸収できるという理屈だ。
しかし、社会保険料は制度維持のため年1〜2兆円規模で自動的に増加しており、過去の実績でも国民所得の伸びを上回る年が続いている。この構図は、実質的に賃上げや経済成長に過度な期待をかけた試算だといえる。
「分母トリック」が負担の実態を覆い隠す
レポートでは、社会保障負担率の計算式の問題点も指摘されている。国民所得の中には、事業主が負担する社会保険料が含まれており、保険料が増えれば分母が増える構造となっている。これにより、実際の負担感とは裏腹に、表面的な負担率が下がる“錯覚”が生じる可能性がある。
谷口氏は、「賃上げによる雇用者報酬の増加と、制度的な保険料増加は性質が異なる」とし、後者を賃上げと同列に扱うべきではないと警鐘を鳴らす。とくに、企業が賃上げを進めようとする際には、保険料負担も自動的に増えるため、賃上げ余地が圧迫される可能性もある。
負担増の先に見える社会的リターンとは
それでもなお、国民が一定の社会保険料増加を受け入れるためには、「何のための負担なのか」という説明責任が欠かせない。子ども・子育て支援金が目指す社会的リターンは、出生率の回復、保育サービスの充実、教育環境の改善などにある。
例えば、支援金の使途として期待される施策には、①保育士の待遇改善、②0〜2歳児の保育無償化、③ひとり親世帯への支援強化などが挙げられる。いずれも社会的投資としては有意義だが、現時点では「どの施策にいくら配分されるか」が不明確なままである。支援金の原資を明示的にリターンとして可視化することが、納税者・被保険者の納得感を生む鍵となる。
「リターンの可視化」が制度の信頼を支える
現時点では、制度の透明性や成果の可視化に課題が残る。支援金を毎月支払う立場にある国民が、「何が良くなったのか」を実感できる設計でなければ、不満と不信が蓄積されていく恐れがある。
本来であれば、政府・自治体・保険者が連携し、「支援金1,000円で保育の質がどれだけ上がるのか」「児童手当がどのように変わったのか」といった“定量的な報告”を年次で公開することが求められる。公共インフラや医療制度と異なり、子育て支援はその成果が個人ごとに見えづらいため、「使途の透明性」と「成果の実感」の両立が課題だ。