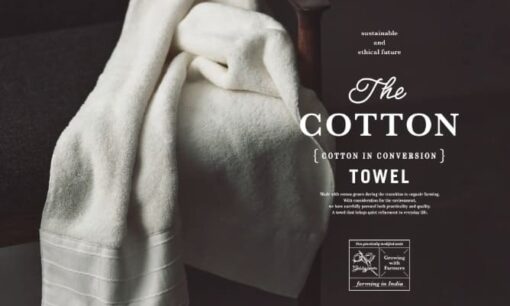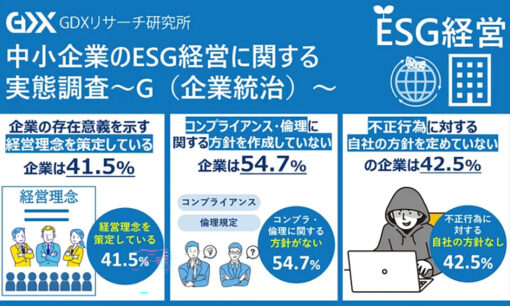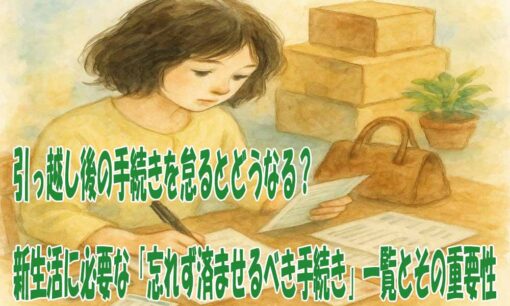海洋ごみ問題の深刻化が進むなか、静岡UPが富士市で実施した清掃イベントが、市民参加型の環境保全モデルとして注目された。158人が集い、未来に残す海のあり方を問い直す場となった。
富士市で158人が参加した海岸清掃イベントの概要
日本財団「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」によると、一般社団法人静岡UPは11月15日、富士マリンプール周辺の海岸で大規模清掃イベント「静岡お助け隊~キレイな海を守るために~ごみ拾い大作戦」を実施した。当日は事前申し込み180人のうち158人が参加し、約40kgのごみを回収した。
清掃活動は、海洋ごみに関するクイズを巡りながら進む形式を取り入れ、富士市のごみ処理状況や種類別割合など、日常では意識しづらいデータを現場で学ぶ機会となった。
回収されたのは40kg 深刻化する海洋ごみと現場で見えた実態
現場では、大型ごみは少ない一方、発泡スチロールの欠片やカップ麺容器の破片など、紫外線劣化で脆くなったプラスチックが多く確認された。細片化したごみは回収が難しく、生態系への影響も懸念される。
参加者は「破片の多さに驚いた」「製品段階での環境配慮の重要性を痛感した」と語り、問題の“見えにくさ”が意識されるきっかけになった。イベント後のアンケートでも、海洋ごみ問題への関心の高まりが多数寄せられた。
静岡UPが取り組む“自分ごと化” 日本財団プロジェクトの狙い
静岡UPは、日本財団「海と日本プロジェクト」の理念に基づき、海の現状を“自分の日常とつながる課題”として認識してもらう活動を続けている。海洋ごみの約7割が陸から流出するとされ、2050年には魚よりもプラスチックが多くなると指摘されるなか、地域固有の海と暮らしをつなぎ直す取り組みは、自治体との連携を含めて広がりをみせている。
地域から始まる海洋ごみ削減 市民参加が生む行動の連鎖
今回の清掃活動は、一度きりのボランティアにとどまらず、市民の行動変容を促す“起点”として位置づけられた。富士市や団体、自治体との連携により、身近な海を守る行動の連鎖が生まれている。
静岡UPは今後も、海と共生する文化を根付かせるための活動を継続する方針だ。海を未来へ引き継ぐための挑戦は、地域の力を結集することで一層深化していく。