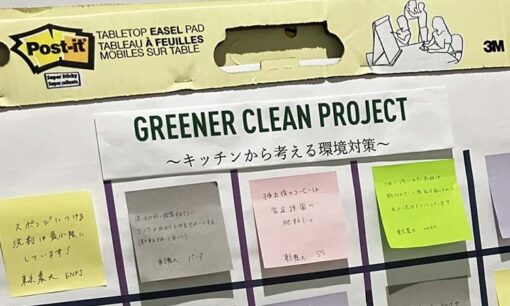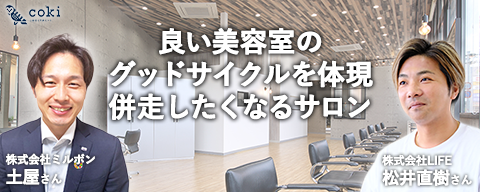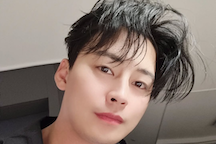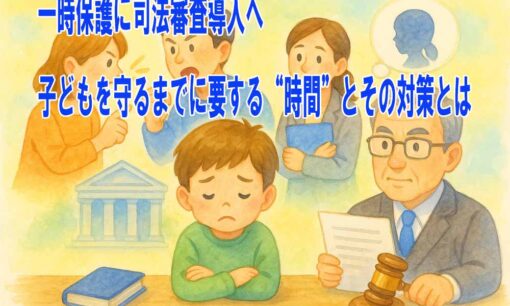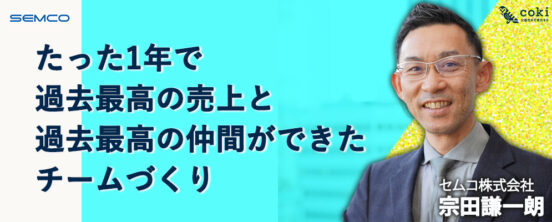時計や計算機で広く知られるカシオ計算機は、実は日本企業の中でもいち早く環境問題に取り組んできた。1993年に策定された「カシオ環境憲章」は、当時としては画期的な一歩であり、そこから30年以上にわたり環境配慮型のものづくりを続けている。
人気ブランド「G-SHOCK」をはじめ、計算機、電子辞書、電子楽器など多彩な製品群に共通するのは「長く使える信頼性」と「環境負荷低減」への強い意志だ。サステナビリティ推進室の五十嵐和典室長に、その歩みと未来の展望を聞いた。
1993年「環境憲章」が示した未来志向
カシオの環境への取り組みの原点は、1993年1月に策定された「カシオ環境憲章」にある。今でこそSDGsや脱炭素が社会の共通言語となっているが、当時はまだ概念すら一般的ではなかった。
国内では環境基本法が施行されたばかりで、企業が自主的に「環境報告書」を出すことは珍しかった。
五十嵐氏は「当時『環境センター』という部署が憲章を策定し、社外向けにも環境報告書を公表した記録が残っています。これが社内外に大きなインパクトを与えました」と振り返る。
カシオは創業以来、独創的な製品を数多く世に送り出してきた。世界初の全自動コンパクト電卓(1965年)、電子辞書の普及、電子楽器「Casiotone」など、新しい市場を開拓するたびに社会的影響力を広げてきた。その企業が早期に環境課題へ向き合ったことは、後の取り組みの基盤を築いたといえる。
「グリーンスタープログラム」が示した実践の力
2001年には「環境理念」へとアップデートし、各事業ごとの取り組み項目を明文化した。その際に導入されたのが独自基準「カシオグリーンスタープログラム」だ。
「部品点数の削減、電池使用量の抑制、分解して再利用できるかどうかの検討などを評価基準として盛り込みました」と五十嵐氏。製品づくりにおいて環境視点を欠かさず、チェックリストのように徹底してきたことが特徴だ。
たとえば計算機は、軽量で省エネ性の高いソーラーパネルを搭載することで乾電池の使用を大幅に削減。電子辞書も長寿命バッテリー化により廃棄電池の削減につながった。こうした積み重ねが、現在の「8つのマテリアリティ」へと体系化され、持続可能性を経営そのものに組み込む礎となっている。
世界ブランド「G-SHOCK」に息づく環境配慮
1983年に誕生した耐衝撃腕時計「G-SHOCK」は、いまやカシオを象徴する世界的ブランドだ。アスリートやミュージシャン、軍関係者まで幅広い層に支持され、「落としても壊れない時計」として知られる。長寿命であること自体が環境配慮につながり、「買い替えを最小限にする」という発想を自然と浸透させてきた。
さらに近年は素材面でも革新が進む。時計の量産工程でバイオプラスチックを採用し、2030年にはプラスチック部品のバイオマス比率を90%にまで引き上げる計画を掲げている。これは単なる素材転換ではなく、ユーザーに「環境を意識した選択肢」を提供する試みでもある。
「時計の量産技術のなかで、バイオプラスチックの活用には先駆的に取り組んできました。長寿命と環境配慮を両立させることで、新しい体験価値をユーザーに届けたいと考えています」と五十嵐氏は語る。
再エネ切り替えと温室効果ガス削減目標
環境課題は製品だけでなく、企業活動そのものに深く関わる。カシオは2018年を基準に、2030年までにスコープ1・2で温室効果ガスを38%削減する目標を設定した。
ここでいう「スコープ」とは、排出量を測る国際的な基準である。
- スコープ1は、工場の燃料燃焼や自社トラックの走行といった「企業が直接排出する温室効果ガス」。
- スコープ2は、他社から購入した電力や熱の使用に伴って間接的に発生する排出。工場やオフィスの電力消費が代表例だ。
- スコープ3は、それ以外の間接排出を広く含む。資材の運搬、社員の移動、製品をユーザーが使うときの電力消費や廃棄に至るまでが対象となる。
カシオはまずコントロール可能なスコープ1・2で削減を進めている。象徴的な取り組みが、国内生産拠点「山形カシオ」での再生可能エネルギーへの全面切り替えである。2024年4月に完了したこの決断は、電力使用量の大きい製造業にとって勇気ある一歩だった。
一方で、スコープ3については課題が残る。サプライチェーン全体に広がるため、取り組みは容易ではない。しかし「ここをどう減らすかが今後の挑戦であり、国際的に求められる責任でもあります」と五十嵐氏は強調する。
「体験価値」を届けるサステナビリティ
カシオが掲げるサステナビリティには二つの柱がある。ひとつは環境負荷の低減。そしてもうひとつが「製品を通じて新しい体験価値を届けること」だ。
「環境配慮型の製品を所有すること自体がユーザーの満足につながる。使う喜びを含めて価値を高めたい」と五十嵐氏は語る。時計、計算機、電子辞書、楽器といった多様な製品群に共通するのは、生活の質を向上させるという使命感だ。
製品の信頼性やデザイン性と環境配慮を両立させることが、カシオにとっての「持続可能なブランド力」につながっている。
「小さな行動」が未来を動かす
プラスチック削減は比較的わかりやすいテーマである。だからこそ全社的な浸透が早く、社員一人ひとりの行動変容へとつながっている。廃材のリサイクル、梱包材の見直し、再利用可能な部品設計など、課題は尽きない。しかし重要なのは「できることから着実に」だ。
五十嵐氏は「課題を正しく認識し、一歩ずつ進めていく。その空気を社内に広げるのも私たちサステナビリティ推進室の役割です」と語る。自然との共生という大きな目標も、日常の小さな改善から始まる。カシオの取り組みは、その原点を示し続けている。