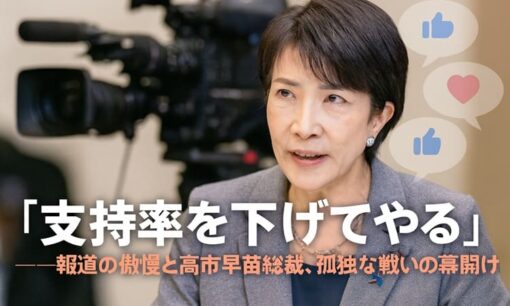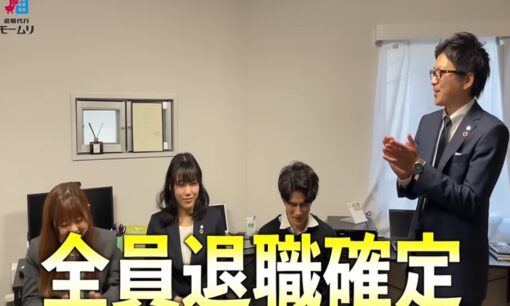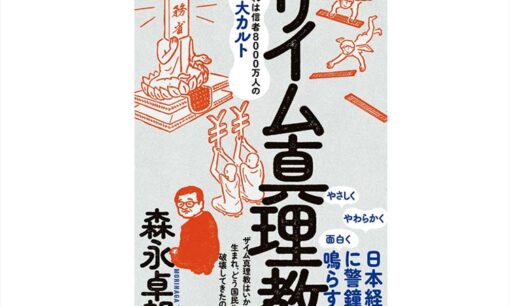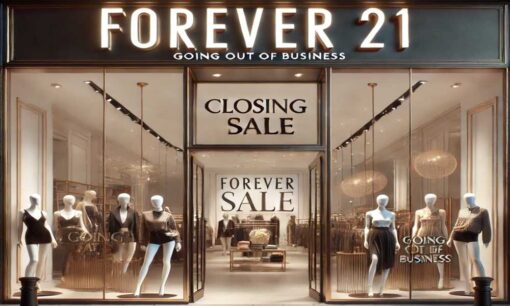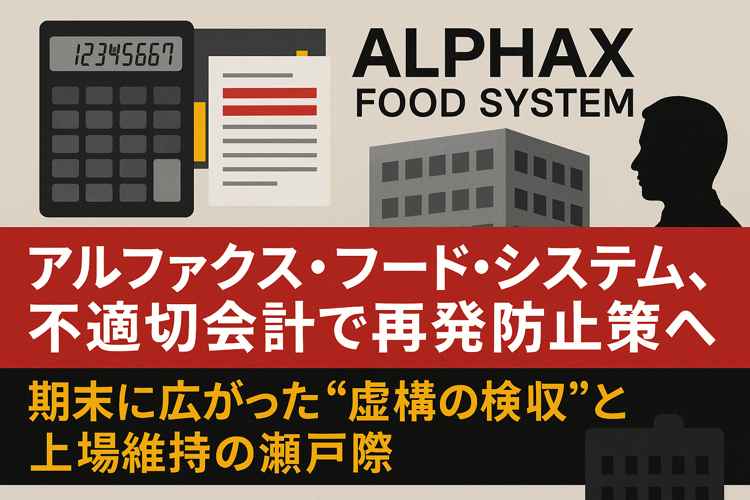
株式会社アルファクス・フード・システム(以下、AFS)は7月30日、配膳ロボットやホテル売却に関する会計処理の妥当性を検証した特別調査委員会の調査報告書(開示版)を公表した。
同報告書では、売上の早期計上や連結対象の誤認など複数の不適切な会計処理が明らかとなり、同社は9月期半期報告書の提出に向けた対応とともに再発防止策の策定を進めていると発表した。
「X社倉庫に眠るロボットたち」 虚構の検収が生まれた夜
2023年9月30日、期末を迎えたアルファクス・フード・システムの社内には、静かな緊張が漂っていた。売上確保を急ぐ幹部の指示のもと、納品も設置もされていない配膳ロボット60台分の売上計上が準備されていた。
実際、ロボットたちはX社——つまり仕入先の倉庫に積まれたままだった。にもかかわらず、Z社との契約に基づく「作業報告書」には、検収済みのサインが記されていた。
「今はまだ納品されていないが、検収サインさえ取れれば大丈夫」
そう語ったのは、社長の藤井由実子氏とされる。
Z社側の担当者も、事情を把握していた。
「そちらから頼まれてサインしました。うちではあの報告書は支払の根拠ではないので、特に気にしていませんでした」
形式上の検収が整うと、2023年9月30日付で約9,192万円の売上が帳簿に計上された。だが、ロボットたちは依然、X社倉庫で眠ったままだった。納品・設置が実際に始まるのは2カ月後、リース契約への切り替えが成立した11月末以降のことである。
しかも、藤井社長は10月13日の取締役会でこう説明したという。
「Z社の協力を得て、夜通し設置作業を進めて検収まで済ませました」
この発言は、事実と異なる虚偽説明だったと報告書は断定している。
不適切処理は複数の取引で “検収書”が売上計上の錦の御旗に
Z社案件のほか、Y社、U社、T社、V社、S社など、外食関連企業との複数の取引で、AFSは「検収書の取得さえあれば売上計上できる」との認識のもと、履行義務が未了の状態で売上を計上していた。
Y社との取引では、売れ残り商品は全額AFSが買い取るという返品保証の覚書が交わされていたにもかかわらず、これを社内でも監査法人にも隠したまま売上計上を断行。覚書は破棄されたとされ、監査法人には「返品条件はない」との虚偽の経営者確認書まで提出されていた。
U社との契約でも、未納品のまま全額を売上計上し、検収書には「20台全て検収済」と虚偽の記載がなされた。返送されたロボット6台分についても返金は行われず、仮受金として計上すべき状態が続いていた。
ホテル売却の真相 “形式だけ”の第三者譲渡と連結回避工作
2022年11月に行われた「ナチュラルグリーンパークホテル」の売却も、実質的には同社関係者が設立・資金保証した会社であり、会計上は連結対象とすべき子会社であったことが判明した。
売却先のR社は、創業者である田村隆盛会長が1000万円を貸し付けて設立資金とし、株主間契約で経営支配を保持。債務保証契約も交わされており、完全にAFSの支配下にある会社だった。だが、AFSは監査法人に対してこの事実を一切開示せず、形式的には「第三者売却」として1095万円の固定資産売却益を計上していた。
その後も、R社(現・Qホテル)は代表者変更を繰り返し、AFS関係者が実質的な支配を継続していた。
ガバナンスの不全と形骸化した監査体制 再発防止策は機能せず
調査委員会は、2020年にも同様の売上早期計上が問題視されていたにもかかわらず、再発防止策が全く機能していなかった点を厳しく批判した。今回の報告書では「コンプライアンス意識の欠如」「夫婦による支配構造」「常勤監査役の不在」など、構造的な問題が列挙されている。
内部監査部門はわずか1名体制。監査法人も短期間で5度交代しており、深度ある監査が困難であった実態も明かされた。
上場維持なるか 提出期限は8月5日、監査法人未定のまま
同社は現在、9月期半期報告書の提出遅延による整理銘柄指定の回避に向け、8月5日までの提出を目指している。監査法人の選定も進めているが、未だ候補先と協議中の段階にとどまる。
仮に提出が間に合わなければ、東証グロース市場からの上場廃止も現実味を帯びる。
調査委が提言する「6つの再発防止策」
報告書は、再発防止策として以下の6項目を提言した。
- 責任の明確化と徹底的な検証
- 業務執行取締役の意識改革と権限分散
- 履行義務明記と検収書ルールの厳格化
- コンプライアンス教育の徹底
- 内部監査部門の強化と監査等委員会の権限拡大
- 会計リテラシーのあるCFOの外部招聘
だが、これらの施策を実効あるものとするには、現在の経営体制そのものの見直しが避けられない可能性が高い。実質的な創業者であり筆頭株主でもある田村氏は、長年にわたって代表取締役を務めてきたが、その配偶者である藤井氏(現・代表取締役社長)とともに経営を掌握する構図が続いていた。
報告書では、「代表取締役に異を唱えることが難しい雰囲気が社内には広がっていた」と記されており、夫婦で代表を務める体制の下、相互牽制機能も事実上働いていなかったと指摘されている。加えて、「内部通報制度に基づく通報がなされることを期待することが難しい状況」とされ、現場から不正を監督機能へエスカレーションするルートも実効性を欠いていた。
こうした構造的な統治不全のもとでは、どれほどルールを整備しても機能しない。
信頼回復には、もはや部分的な改善では足りない段階にある。