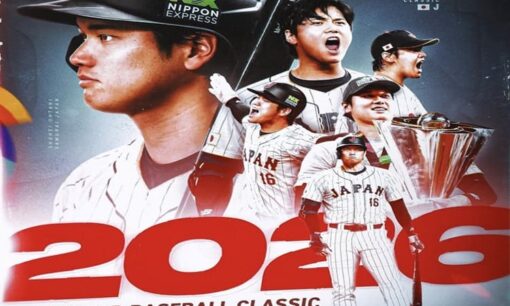製造業の世界では、工場を持たないことが合理的とされて久しい。外注し、固定費を軽くし、変動費で回す。その流れに抗うように、株式会社ウエストは2023年、福島県いわき市で再び自社工場を動かし始めた。
かつて自ら閉じた工場を、もう一度引き受ける。
それはノスタルジーでも、単なる美談でもない。経営者としての、そして一人の人間としての、泥臭い「意地」が試される決断だった。
「一度失った技術は、二度と戻らない」
ウエストは1902年創業。日本の靴下産業の黎明期から業界を支えてきた老舗だ。二代目の西村信次郎は、日本靴下協会など複数の業界団体で理事長を務め、産業基盤づくりに深く関与してきた人物である。
だが2003年、中国製品の台頭を前に、岩手の自社工場は閉鎖された。その決断の場にいたのが、現社長の西村京実だった。

「当時は、もう日本の製造業は中国に勝てない、と母は判断しました。退職金を払えるタイミングでの閉鎖は正しかったと思います。でも、閉じた後に分かったことも多かった」
閉鎖後、取引先から相次いだのは「同じ品質のものが作れなくなった」という声だった。
技術は、数字では測れない。現場を失って初めて、その重みが分かる。
その“後悔”が、20年近く西村の中に残り続けていた。
きっかけは、一本の電話だった
2022年8月。福島県いわき市にある、レナウンインクスの靴下工場が閉鎖されるというニュースが業界を駆け巡った。
「この工場がなくなったら、今依頼している自社ブランドは続かない。何より、業界にとって大きな損失になる」
西村はそう直感したという。なぜなら、その工場は単なる生産拠点ではなかった。50年以上、靴下を編み続けてきた職人が集い、技術の“最後の砦”とも言える存在だったからだ。
西村は、その工場で最も信頼していた職人に電話をかけた。
「決定なんですか?」
「決定です。引き継ぐ会社もありません」
業界で誰もが名を知るその職人は冗談まじりにこう続けた。
「地元を離れるつもりはないので、ガソリンスタンドででも働きますよ」
その瞬間、西村の中で何かが切り替わった。
「この人たちの技術が、このまま消えていいはずがない」
反対だらけの中で、決めたこと
工場の引き継ぎは、想像以上に困難だった。土地の問題、設備の問題、資金繰り、そして何より“時間がない”。
社外アドバイザーは全員反対した。
「重すぎる」「リスクが大きすぎる」「準備期間が足りない」
経営コンサルタントも首を縦に振らなかった。
それでも、西村は退かなかった。あるアドバイザーは、こう問い詰めたという。
「なぜ、そこまでしてやりたいのか。君の使命は何だ」
社員の前で、覚悟を問われ、泣くまで議論した末に出た答えはシンプルだった。
「技術を未来につないで理想の靴下をつくり続けることです」
2023年1月1日。ウエストは、いわきの工場を「いわき靴下ラボ アンド ファクトリー」として再始動させた。正社員8人からのスタートだった。だがそれは、ゴールではなく「ヒリヒリする毎日」の始まりに過ぎなかった。
工場は“生産の場”ではなく、“学びの場”に

西村が目指したのは、かつての大量生産工場ではない。「ラボ」と名付けたのは、理由がある。
「靴下を作る場所であると同時に、考える場所、育てる場所にしたかった」
工場では毎月研修が行われ、外部の知見も積極的に取り入れている。若手とベテランが同じ現場に立ち、技術だけでなく“考え方”を共有する。
「技術は、教科書では残せない。人が人に手渡すしかないんです」
これは、創業時から続くウエストの思想でもある。1960年代、岩手の工場に通信制学校を併設したのも、「働きながら学ぶ」ことを本気で考えた結果だった。
「格好つけない」からこそ見える未来
今、ウエストは正念場に立っている。2027年、そして2030年に向けた大規模な新プロジェクトのローンチが控えているからだ。
これは、ただ工場を動かすだけでは到底成し遂げられない。営業、企画、そして工場の職人たち。会社全体が一つの生き物のように一体となり、同じ熱量で向き合わなければ、霧散してしまうような挑戦だ。
「もう二度と、工場は閉鎖しない」 西村はそう心に決めている。その決意は重い。社員一人ひとりが納得し、自ら心を開いて仕事に向き合ってくれるか。その一点にかかっている。一歩間違えれば、すべてが瓦解する崖っぷちの経営だ。
「格好をつけていても、技術は守れません。泥臭く、不器用でもいい直向きに。私たちが本気で動けば、必ずできると信じています」
高級靴下は、結果であって目的ではない
近年、ウエストは高価格帯の靴下で注目を集めている。だが西村は、こう釘を刺す。
「高い靴下を作りたかったわけじゃない。ちゃんとしたものを作ったら、結果として高くなっただけです」
素材、工程、職人の時間。すべてを正直に積み上げると、価格は自然に決まる。
顧客から届く言葉が、それを裏付ける。
「足の裏で、素材の良さが分かる」
「一度履いたら、もう戻れない」
これはマーケティングコピーではない。現場で積み上げてきた時間の総和が、生んだ評価だ。
「続ける」ための経営
西村が繰り返し口にするのは、「目先の利益を追わない」という言葉だ。
「誠実にオンリーワンを作り続ければいずれ利益はついてくる」
工場を持つことは、短期的にはリスクだ。だが、技術・人・地域をまとめて引き受けることでしか、生まれない価値がある。
「大手がやらないことをやる。それが、今のウエストの役割だと思っています」
工場を閉じ、ファブレスになり、そして再び工場を持つ。その往復の中で、西村京実は「製造業の本質」に行き着いた。
それは、単にモノを作ることではない。人と技術を、どう未来に残すかという問いそのものだった。人と技術を、泥にまみれながら、どう未来に繋いでいくか。
その問いに、彼女は今、全社員と共に正面から答えようとしている。