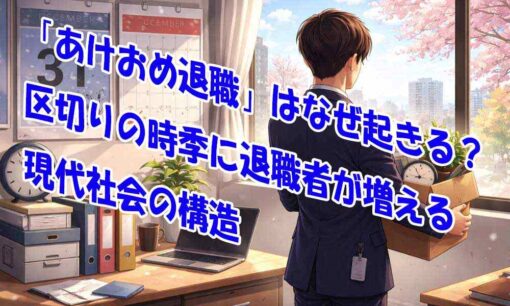「音声の真偽」に企業が答えた日

「週刊文春が報じた“パワハラ朝礼”は本当だったのか」――。
その問いに対する公式の答えが、ついに企業自身の口から明かされた。
10月30日、伊澤タオル株式会社は、適時開示で「第三者委員会による調査結果、処分および再発防止策に関するお知らせ」を公表した。文書には、代表取締役社長・伊澤正司氏による「従業員に対する言動がパワーハラスメント等に該当すると認定された」と明記されていた。
今年6月、東証スタンダード市場に上場したばかりの伊澤タオルは、Amazon限定ブランド「タオル研究所」やセブンプレミアム向けOEM「極ふわ」などで急成長を遂げていた。だが同時に、社内では“パワハラ朝礼”をめぐる疑惑が渦巻いていた。
週刊文春が報じた音声データには、社長が社員を恫喝する声が生々しく残されており、SNSでは「聞いていて胸が苦しくなる」「上場企業でこんなことがあるのか」と大きな波紋を呼んだ。
今回の第三者委員会報告書は、その音声で語られた出来事が“単なる噂”ではなく、事実として確認されたことを公式に示した。
報告書は、社長の言動が「人格を否定し、精神的苦痛を与える行為」としてパワーハラスメントに該当するとの結論を示し、企業文化・組織運営体制・ガバナンスの不備が背景にあったと指摘している。
つまり、報道が突きつけた告発は、法的に裏づけられた現実として確定したのである。
名門メーカーが直面した“信頼の崩壊”
伊澤タオルは、大阪を拠点とする老舗メーカーだ。創業以来、タオル製造の技術革新に挑み、「柔らかさの数値化」など学術機関と連携した研究で業界の常識を覆してきた。
それだけに、今回の一件は「誇りの象徴」である製品イメージを大きく傷つけることとなった。
報告書には、従業員が社長の言動を恐れていたこと、内部通報制度が十分に機能していなかったことが記されている。
社内のヒエラルキーが固定化し、誰もトップに意見できない――。
そんな「沈黙の職場」が形成されていたことが明らかになった。
第三者委員会は、こうした企業風土を「ガバナンスの欠如」と指摘。
社員が萎縮する環境が続いたことが、問題の長期化を招いたと分析した。
社長はなぜ辞任しなかったのか 取締役会の苦渋
最大の注目点は、報告書でパワハラが認定されたにもかかわらず、取締役会が社長の辞任を求めず、減給処分(50%・6カ月)にとどめたことだ。多くの上場企業であれば、代表取締役によるハラスメント行為が認定された時点で退任は避けられない。
それでも続投を決めたのはなぜか。
取締役会はその理由を、「社長がタオル製造における高度な専門性を持ち、協力工場への技術指導や主要取引先とのネットワーク構築において代替不可能な存在である」と説明している。
つまり、辞任は経営基盤を揺るがす――という判断である。
企業としては、倫理と経済の狭間で揺れた格好だ。倫理的には辞任が筋、だが経営的には社長不在が事業を危うくする。結果として、ガバナンスの独立性を保ちながらも、創業家トップを残すという“折衷案”を選択した。
しかし、この決定には社内外から「甘すぎる」との声が相次いだ。
SNSでは「これでは再発防止にならない」「上場企業の自浄能力が問われる」と批判も飛び交う。
一方で、「社長の技術と取引関係があってこその伊澤タオル」という現場の声もあり、板挟みとなった取締役会の苦渋がうかがえる。
この「続投判断」は、創業家経営が支配する中堅メーカーにおけるガバナンスの限界を象徴している。
経営刷新を求める声と、技術継承を重んじる現場――。
その狭間で揺れる企業構造は、日本の中小上場企業が共通して抱える課題でもある。
再発防止と「柔らかい組織」への転換なるか
伊澤タオルは、報告書を受けて複数の再発防止策を決定した。外部弁護士による定期監査、独立した社内相談窓口の設置、管理職研修の実施。さらに、匿名通報制度の整備や社員意識調査など、組織風土の改革を掲げた。
「タオルは人の肌に一番近いもの。だからこそ、働く人の心にも優しい会社でありたい」
社内文書に添えられたこの一文が、再出発への意思を象徴している。
第三者委員会報告書は、企業の不祥事を暴く“終わり”ではなく、“始まり”だ。
厳しい認定を経て、信頼を取り戻せるかどうか。
柔らかさを追求してきた伊澤タオルが、今度は「人の心に柔らかい組織」を築けるかが問われている。