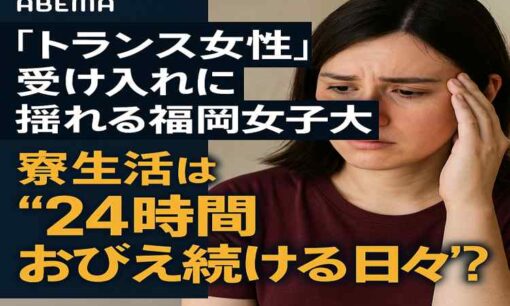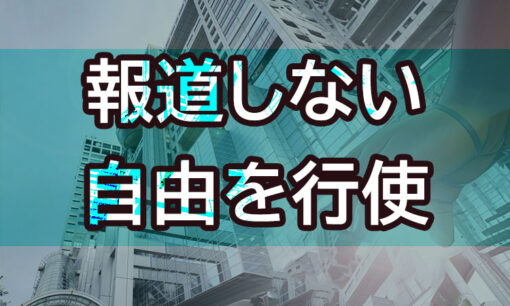下請けからの脱却——。創業1969年の株式会社システムズ(以下、システムズ)は、移り変わる時代の中で新たなビジネスモデルへ転換し、今なお新たな挑戦を次々と行っている。
同社の主力事業は「マイグレーション」。古くなったシステムを、現代に合わせて新しい環境へと移し替える仕事だ。「古いものを捨てて新しくする」でも「古き良き」でもない。古さと新しさをむすび、未来へつなぐ事業なのだ。これができるのは、長年培われてきた知識と経験があるからこそ。“古さ”を武器に変え、“古さ”を強みにしてきた会社だ。
2025年4月には北米にオフィスを開設するなど、業界の先駆けとして挑戦を続けるシステムズ。代表取締役 小河原氏に同社の歩みや展望、挑戦の背景にある思いを伺う。
「古くなったら捨てる」以外の選択肢。システムズだからできる“引っ越し”とは
インターネットやスマートフォンの普及、AIの台頭が進み、古いものは新しく、新しいものはより新しくすることが求められるようになった現代。社会の急速な変化の中で、企業の情報システム分野の進化を支える一端を担ってきたのがシステムズだ。1969年の創業から50年以上にわたりシステム開発やインフラ構築、保守運用などを行い、現在は「マイグレーション&モダナイゼーション」が主軸事業となっている。
マイグレーションとは、古くなったシステムを新しい環境へ“引っ越し”させることだ。古い言語で作られていたり、メーカーによるサポートが終了したり、最新のセキュリティ基準に対応できなくなったりしたシステムを捨てるのではなく、現代のテクノロジーに合わせて移し替える。そしてこれは「作り直し」とも違う。長年使ってきたシステムには、その会社ならではの業務や現場の工夫が強みとして蓄積されている。だからこそ、ゼロから作り直すのではなく、既にあるものを活かして移し替えることに価値があるのだ。
しかし、この“引っ越し”はどの会社でもできることではない。どんなシステムでも、10年もすれば仕様を理解している人は少なくなり、メンテナンスなどで色々な人が手を加える中で複雑になっていく。そうして古くなり、ブラックボックス化したシステムは誰も手を付けたがらず、現代の技術しか知らないエンジニアではどうしようもできなくなってしまう。そこで“引っ越し”ができるのは、古い技術と現代の技術の両方の知見と、長年の経験と実績を持つシステムズだからこそだ。
「弊社はマイグレーション事業が始まった1995年から約30年、技術や知識、実績を積んできました。古くからの技術と最新のテクノロジーの両方に精通しているからこそ、既存のシステムを活用するという提案ができるのが強みです。また、既存のシステムを活かすため、すべての業務要件をゼロから整理し直す必要がないなど、お客様の負担も投資コストも大きく減らすことができます」(小河原氏)

さらに同社では、“引っ越し”の際にシステムを変えたり、機能を改善したり、新しい技術に合わせたりする「モダナイゼーション」も手がけている。既存のシステムの良さやお客様の文化を大事にしながら現代に合わせてアップデートし、これからも安心して使い続けられるシステムにする。そんな、過去と現在、そして未来をもつなぐのがシステムズの仕事なのだ。
「単にシステムを移行するのではなく、お客様の強みや企業文化といった『らしさ』を大切にし、お客様のビジネスを『ありたい姿』までお連れするのが弊社のミッションです。我々はシステムを新しく作り直すことを否定していません。既存システムを流用するという選択肢をお客様に提供することが大切だと考えているのです」(小河原氏)
ビジネスモデルの転換から確立までの15年
システムズは、先代社長である小河原氏の父が創業した会社だ。大学生の頃から、いずれは会社を継ぎたいと考えていたという小河原氏。「自分で起業することも選択肢として考えましたが、自分の力だけでジャンプするよりも、先代が築いてきたものを土台にしてジャンプした方がもっと高く飛べるだろう、というイメージがあったんです」と語る。
小河原氏は、社長になるために先代の知り合いの経営者に定期的に話を聞いて勉強していくうち、「自分でモノを売る力を学ぶべきだ」と考えた。そして、新卒ではパソコンや周辺機器を販売する商社に入社し、営業の仕事に就いた。4年ほど働いたのち、1999年にシステムズに入社。最初は仕事を学ぶため、SEとして開発やチームリーダー、プロジェクトマネージャーなどを5年ほどかけて一通り経験した。
その後、アメリカ・シリコンバレーに留学して経験を積み、日本へ戻ってきてからは、新たに立ち上がった営業部隊の責任者を務めることに。同社はもともと大手IT企業に技術者を派遣する下請けの仕事がほとんどで、新規顧客獲得のための営業経験がほとんどなかった。しかしバブル崩壊をきっかけに、下請けを脱却しなければこの先、生き残っていけないとの課題意識からマイグレーション事業に舵を切ったところだったのだ。
中堅企業の商社で営業を経験してきた小河原氏は「中小の企業規模では、営業の人員をたくさん抱えるような投資をしての顧客獲得は難しい。営業の人員に依存せず、マーケティングやブランディングで認知度を高めることで、お客様の方から問い合わせをしてもらえる会社にしなければだめ」そう考え、古いシステムを使う企業向けのセミナーやWeb広告、自社サイトでの事例紹介などの情報発信の仕組みを立ち上げ、認知を獲得していった。
「下請けから脱却するという事業の方向性を変えてから、しっかり確立させるまでは実に15年かかりました。ただ、その中で一番大変だったのは事業を変えること以上に、社員の気持ちや考えを変えてもらうことだったんです。方向性を理解してもらえず辞めていった社員も少なからずいましたし、長い時間がかかりました」(小河原氏)

技術者派遣が中心だった頃のシステムズの社員は、派遣先の会社のプロジェクトの一員として動くため、「自分がどこの会社に所属しているのか分からない」という状態になりがちだった。そのため、元請けを目指す会社の変化に置いていかれてしまう社員がいたのだ。その中で、小河原氏は丁寧に対話や発信を続けた。全体発信をしながらも、個人と話すことを重視していたため、少人数でカジュアルに話せる場を年に40〜50回作り、会社の変化やビジョンを伝えた。その後は他の経営幹部にも社員と懇談をする場を作り、様々な視点から対話をしてもらうようにした。そうして5年ほどかけて社員の考えも変化していき、現在のシステムズが作り上げられてきたのだ。
変化のために挑戦を続けてきた小河原氏。長い時間がかかっても続けてこられた理由について、「下請けで技術力だけを提供していれば成長できる時代は必ず終わる。むしろ、このまま変わらずにいる方が大変なことになるという強迫観念のようなものがありました」と語った。
ワクワクしながら働き、長く活躍する人材が育つ会社作り
——御社が会社作りにおいて大切にしていることは何ですか?
社員一人ひとりがワクワクしながら働けることです。弊社は「『らしさ』から『ありたい』をかたちにする」をパーパスに掲げています。この考えを社員に定着させるためには、まずは社員一人ひとりの“らしさ”を伸ばし、“ありたい”を実現できる組織でなくてはなりません。
また、創業当初は高度成長期だったこともあり、1人のカリスマ経営者がそのセンスや情熱で会社を大きくしていける時代でした。その後バブルが崩壊し、低成長の社会環境になったことで、無駄をなくして利益を出すという、管理と数字によって社員を動かすPDCAの管理経営の時代になったんですよね。必要な変化だったと思いますが、私はそのやり方では社員の能力を十分に活かせないと思ったんです。管理されて動くのではなく、自ら考えて行動しなければと。だから、やりがいや働きがいを持って自分らしく、ワクワクしながら働く会社にしたいと考えました。
最初は「仕事でワクワクなんかできないですよ」「仕事に“やりがい”や“ワクワク”なんて必要ですか?」という社員がたくさんいました。それでも、働きがいのある楽しい会社にしたいという思いや、ワクワクして仕事をすることがなぜ必要かを伝え続けてきました。おかげで、今はほとんどの社員が「ワクワクや働きがいを求めたい」と恥ずかしがらずに口にできる雰囲気に変わってきています。
また、そうした変化に伴って社員同士の関係性も変化してきています。社員は「上司と部下」ではなく同僚のように、でもお互いにリスペクトを持って話し合っています。まさに、お互いが“らしさ”を持ってコミュニケーションを取れているのだと思います。そういう雰囲気を見て「私も一緒に働きたい」と言ってくださる学生も多く、弊社の大きな強みになっています。

——業界の課題だと感じていることと、それに対して御社が行っていることを教えてください。
やはり、IT人材不足は大きな課題です。また、人材が不足してきている一方で、人材の能力がそれほど高まっていないのも課題に感じています。これからはただ人を増やすだけでなく、質的な変化もしていかなければなりません。
そこで弊社では、4年後の60期に向けた経営計画「ビジョン60」で3つの人財像を掲げています。それが「リーダー人財」「スペシャリスト人財」「コンサルティング人財」です。
「リーダー人財」は、この先AIがさらに社会に浸透していく中でも、人の心を動かし、チームを力強くリードしていくのは人にしかできません。また、一つの分野を突き詰めていくテックリードとしてのスキルを持つ「スペシャリスト人財」も大切です。「コンサルティング人財」は、お客様の“らしさ”から“ありたい”を実現するためには、机上の計画だけを作るのではなく、お客様とともに伴走できる人財が不可欠だと考えています。
——人材育成に力を入れているのも御社の特徴だと思いますが、中でも特色のある制度はありますか?
28歳、32歳、40歳、50歳で行うキャリアデザイン研修です。世代によって課題や問題が異なる中で、自分の将来について考える機会となっています。入社5年目くらいの28歳は、様々な仕事ができるようになってきた中で、不平不満や課題意識、不安が出やすい時期です。その中でストレスをためてしまったり、この会社は違うと安易に判断して辞めたりする人が出てきます。それに対して、自分の課題として捉え、これからどう行動・改善するか考える研修となっています。
32歳は入社して10年目くらいで結婚したり子供が生まれたりする人が多い世代です。この時期だからこそ抱える悩みを話したり経験談を共有したりして、気づきを得てもらう研修を行っています。40歳、50歳での研修については、定年が近づいてくると「もう定年を迎えるまで今の作業を続けるだけ」と仕事に本腰が入らなくなってしまう人も出てきます。でも、今は65歳まで働けますし、あと数年もすれば70歳まで働く時代にもなるでしょう。さらに、労働人口が減っていく日本においては何歳でも健康で活躍してもらいたい。であれば、10年、20年先を見据えて今何をするかを考える機会を作ることが大切だと思ったんです。また、社員皆で生産性を上げないと給与水準も上げられません。そこで、先を見据えながら年齢に関わらず活躍してもらえるよう、40歳と50歳で自分のキャリアと向き合うための研修の機会を作っています。
日本を拠点にアメリカ市場へ。掛け算で広がるシステムズ
——2025年4月には北米にオフィスを出されていますが、なぜアメリカを選んだのですか?
2050年には日本の人口は8,000万人を下回り、経済も縮小していくと予想されています。一方で、アメリカは2050年においても人口も経済もまだ成長し続けていると言われているんです。それなら、アメリカの市場に今から手を打ち、時間をかけながらビジネスを展開していけば、5年あればアメリカでもしっかり地に足のついた会社にできると考えたからです。
——アメリカではどんなことをする予定なのでしょうか?
これまでにアメリカに進出した日本のIT企業は何社もありましたが、多くが撤退しています。というのも、アメリカにオフィスを出して、さらに現地で人を1人、2人雇うだけで年間3,000〜5,000万かかると言われており、3年間で1〜1.5億円の投資コストになります。それだけの投資を継続的に支払えるビジネスにまで確立するのが難しいため、撤退を余儀なくされるのです。だから、我々はいかにコストをかけずにアメリカの市場にアクセスするかを重視しています。
我々はかつて顧客基盤がない中で、日本でビジネスを拡大させたのは、マーケティングやブランディングによる顧客獲得でした。それと同じことをアメリカでもする予定です。マーケティングのフェーズもアメリカには社員を置かず、日本からのオペレーションでWebやSNSなどを通じてアメリカ現地のCEOやCIOに発信して認知度を高めていき、興味がある人に連絡してもらえるようにしたいと考えています。
アメリカにおけるSEの給与水準は1,500〜2,000万円。つまり、日本人の単価を倍にしてもアメリカでSEを雇うより競争力があるんです。アメリカという市場で日本人の価値のあるサービス・クオリティを安価に提供することで社会に貢献できれば、システムズの存在感を高めることができ、ひいては社員の給与水準も上げていけると考えています。

——今後の展望を教えてください。
これまで15年近くかけて改善を重ね、年率10〜15%の成長ができる会社になりました。改善を積み上げてきた“足し算”の時代です。しかしこれからは“掛け算”によって大きくなっていく時代だと考えています。例えば、会社を買収してより短期間で事業を大きくしたり、地方の会社を買収して地場のSIerと一緒に事業を広げたり、アメリカ進出もその一つです。そういう“掛け算”をして成長することで、いままでよりももっとワクワクできる会社にしていきたいと思っています。
また、2026年から始まる「ビジョン60」では、4年後には収益を50億円まで高め、大手企業を超える給与水準にする。そして10年後には100億円を目線として、上場企業を超える給与水準にするという目標を立てています。このビジョンは、これまでの“足し算”の継続と、先ほどあげたような “掛け算”を組み合わせることによって実現可能だと考えています。
さらに今、生成AIを活用してシステムの仕様を抽出し、要件定義、機能設計、詳細設計などを作れる仕組みを準備しています。この仕組みができれば、古くなったシステムから仕様書を生成し、そこから新たなシステムを作り直すことが出来るようになります。しかしこれはどこの企業でも提供できるサービスではないと考えています。生成AIを使うには、レガシーシステムを熟知した人財による問い合わせのためのキーワードや背景情報を知っていなければなりません。だからこそ、生成AIの時代でも、長年培ってきた弊社の知見や、育ててきた社員の力が活きていくと考えています。
新しいフェーズを迎えるシステムズのこれからが楽しみで、私自身、本当にワクワクしています。
◎企業情報
会社名:株式会社システムズ
本社所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-5 ONEST西五反田スクエア(旧 西五反田102ビル) 8階
設立:1969年(昭和44年)12月24日
資本金:1億円
代表取締役社長:小河原 隆史
社員数:250名(2024年7月1日現在)
URL:https://www.systems-inc.co.jp/
◎インタビュイー
小河原 隆史
1973年生まれ、東京都出身。大学で宇宙工学を専攻後、商社で営業職を経験し、1999年に株式会社システムズに入社。エンジニアや営業を経て、2007年にマーケティング事業本部長、2009年に副社長、2011年に社長に就任し、現在に至る。経営の舵を取り、SES中心だった事業を受託開発やマイグレーション分野へと拡大。システムのモダナイゼーションを推進し、老朽化した基幹システムの最新化を強みとする企業へと成長させた。「現場×IT」を掲げ、顧客に寄り添うIT支援を重視。レガシー技術と最新技術の橋渡しを行い、持続的な成長を目指す。改善と挑戦を追求する経営理念のもと、事業拡大と人材育成に尽力している。