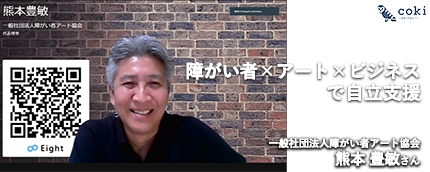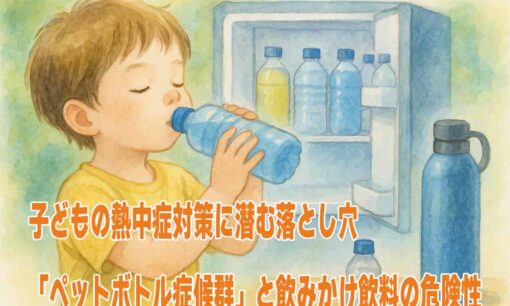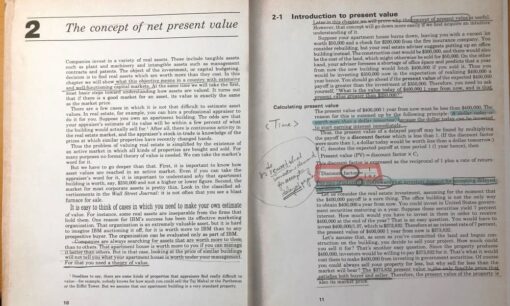老朽化と向き合う50年企業の挑戦

地下に眠るインフラの老朽化が全国で顕在化する中、埼玉県八潮市での道路陥没事故を契機に、再整備の必要性が改めて注目されている。その最前線に立つのが、1975年創業のトンネル工事専門会社・ヤスダエンジニアリング株式会社(大阪府大阪市)だ。
上下水道やガス、電気、通信といった生活基盤を支える地下インフラの工事において、同社は「推進工法」と呼ばれる独自技術を武器に、全国でトップレベルのシェアを維持してきた。
「ロケット鉛筆」式で掘り進む推進工法
推進工法とは、掘進機をジャッキで地中に押し込み、その後ろからコンクリート製の管を継ぎ足しながら、トンネルを形成する方式だ。まるでロケット鉛筆のように後方から力を加えて進めるこの手法は、日本の地下インフラの根幹を担ってきた。特にヤスダエンジニアリングは、小口径から大口径までをカバーできる自社機材を保有し、機器保有台数では全国1位を誇るという。
地下障害物との闘い 「削る」という逆転の発想
しかし、再整備の現場には厄介な敵が潜む。過去の工事で放置された鋼矢板やコンクリート杭などの「地下障害物」だ。これらにより推進工事が頓挫するケースも多く、事前に察知できてもルートの大幅な迂回が必要となり、費用や工期を押し上げる要因となっていた。
この課題に対し、同社が開発したのが「ミリングモール工法」だ。従来のように力で障害物を砕くのではなく、硬い素材を「優しく削る」ことで切削・貫通する新技術である。例えるならば、硬いコーヒー豆を丁寧に挽く“コーヒーミル”のようなアプローチだ。実際、この工法によってH形鋼などの難敵を乗り越え、都市部での再整備の道が拓かれている。
ピーク後の転機、不動産事業から本業回帰へ
同社の歴史をたどれば、波乱の連続だった。創業者の安田京一氏は、家族8人の生活を支えるため、若くして建設業に身を投じた。推進工法との出会いを機に独立、下水道整備が進む1970年代から90年代にかけて、事業は右肩上がりに成長した。
だが、1998年をピークに下水道工事の需要は減少。2003年には売上が半減し、倒産寸前に追い込まれる。そこで救いの手となったのが不動産事業だった。V字回復を果たしたのち、2007年のリーマンショックを経て本業へ回帰。「ミリングモール工法」などの技術開発によって再び軌道に乗った。
海外へも広がる日本の技術 ベトナムODA事業で表彰も
縮小する国内市場をにらみ、ヤスダエンジニアリングは韓国・台湾・インドネシア・ベトナムへと海外展開を進めた。特にベトナムでは日本のODA(政府開発援助)プロジェクトとしてホーチミンとハノイの下水道整備に参画。大手ゼネコンすら懐疑的だった案件を、中小企業としてやり切り、国交省から表彰も受けた。現地で育成したベトナム人スタッフは今、日本の現場でも活躍している。
「世界の地下インフラに貢献する」100年企業を目指して
2025年には老朽化していた旧工場を刷新し、新工場を建設。現在は、ミリングモールとシールド工法を組み合わせた「ミリング推進シールド」の開発に挑む。長距離・急曲線施工への対応を見据えたこの技術が成功すれば、日本全国、そして世界の地下インフラ整備に新たな道を開く可能性がある。
「最後まで諦めずにやり切る」――その精神を掲げ、ヤスダエンジニアリングは次の50年、そして100年企業を見据え、歩みを止めることはない。