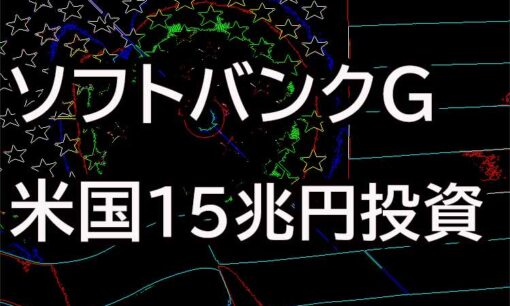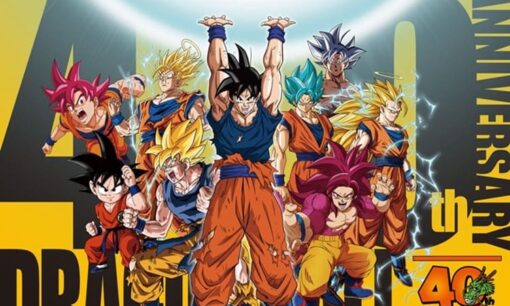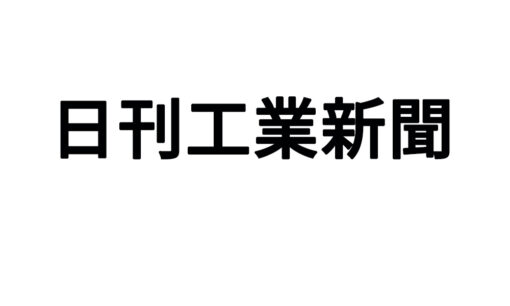共同通信の報道によると、厚生労働省は出産にかかる費用の無償化に向け、公的医療保険の新たな枠組みを創設する方向で調整を進めている。今回の方針は、2025年11月20日の社会保障審議会部会で議論され、2026年度以降の導入を視野に入れた法改正案が次期通常国会に提出される見込みだ。ただ、その背景には、2023年の合計特殊出生率が1.20となり、2024年は1.15にまで下がったとの報道があるなど、日本の出生数が歴史的な低水準に達している現状がある。出生数は2024年に約68万6千人となり、過去最低を更新した。こうした状況を踏まえると、出産費用の無償化がどこまで出生率の改善につながるのか、冷静な検討が求められている。
出産費用はいくらかかるのか
日本では正常分娩が公的医療保険の対象外となっており、医療機関が自由に価格を決められる仕組みが続いている。そのため、地域差や施設差が大きく、費用の予測が難しい面もある。厚労省資料などに基づく分析では、2022年度の正常分娩費用の全国平均は約48万2,000円となっている。これは公立・私立・助産所などを含めた平均値で、祝い膳や個室料などの追加サービスは含まれない。
一方で、都市部の民間病院では出産・入院・新生児管理料を合わせて80万~100万円程度となる例も見られる。加えて、妊婦健診の自己負担や出産準備品の購入なども必要となるため、出産前後の支出は必然的に大きくなりがちだ。
現在の主な支援制度
出産育児一時金(50万円)
現在、もっとも中心的な支援が出産育児一時金である。政府は出産費用の上昇に対応するため、2023年4月に支給額を42万円から50万円へ引き上げた。さらに、医療機関への直接支払制度により、利用者は差額のみを支払う方式が広がっている。ただ、都市部では総費用が50万円を超えるケースが珍しくなく、結果として10万~20万円程度の自己負担が残る例も多い。
出産手当金(働く人向け)
また、会社員や公務員として働く人には出産手当金が支給され、産前42日・産後56日の休業期間について標準報酬日額の3分の2相当が補填される。ただし、フリーランスや自営業者は対象外となるため、雇用形態による格差が指摘されている。
妊婦健診費用の公費負担
妊婦健診は保険適用外だが、多くの自治体が受診票(クーポン)を交付し、14回前後の健診を補助している。ただし、自治体によって補助額が異なるため、検査内容によっては追加負担が生じることもある。
自治体独自の支援
さらに、自治体ごとに独自の支援も行われている。出産祝い金、産後ケアの補助、家事・育児支援サービスの割引、タクシーチケットの配布など地域ごとの取り組みがみられ、居住地によって恩恵が異なる点が特徴的だ。
出産費用無償化に向けた新たな保険枠組み
共同通信の報道では、厚労省が正常分娩を特別な保険枠に組み込み、全国一律の価格水準を設定する方向で制度を検討しているとされる。この方式は、通常の医療と同じ1~3割負担ではなく、特別な仕組みにより自己負担を極力抑える設計を目指すものである。ただし、祝い膳や記念撮影といった付帯サービスは保険の対象外となる方向で議論されている。
また、自己負担を実質的にゼロへ近づけるため、保険給付に加えて現金給付を併用する案も検討中だ。もっとも、制度設計には時間を要するとみられ、そのため当初予定していた2026年度の開始は遅れる可能性が高い。
現在の支援と新制度案の比較
| 項目 | 現在(2025年時点) | 検討中の新制度(案) |
|---|---|---|
| 出産費用の扱い | 正常分娩は保険適用外 | 新たな保険枠で標準的な費用を保険適用 |
| 公的支援の中心 | 出産育児一時金50万円 | 保険給付と現金給付を組み合わせる方向 |
| 価格水準 | 地域差・施設差が大きい | 全国一律の点数化により平準化 |
| 利用者負担 | 10~数十万円程度が生じる場合も | 標準的な分娩費用は原則ゼロへ |
| 付帯サービス | 基本的に自己負担 | 同様に保険対象外 |
| 開始時期 | 現行制度が実施中 | 2026年度以降の開始を検討 |
日本の出生率はどこまで低下しているのか
日本の出生率は長期的な低下が続いており、2023年の出生数は758,631人で、同年の合計特殊出生率は1.20だった。さらに、2024年は出生数が約68万6千人、出生率が1.15となったとの報道があり、人口維持に必要とされる2.1を大幅に下回っている。こうした水準は、社会の持続性に関する警鐘として受け止められている。
出産費用無償化で出生率は上がるのか
出産費用の軽減が出生を後押しする可能性はある。経済的な負担が減ることで、第1子や第2子を考える際の心理的な障壁が下がり、特に若年層の出産意欲を支える効果が期待されるためだ。加えて、費用面での安心感は、妊娠・出産に対する前向きな気持ちをつくりやすい。
しかしながら、専門家の間では「無償化だけでは出生率の大幅な改善は難しい」との見方が根強い。出生率の低下には、雇用の不安定さ、住宅費の高さ、教育費負担、働き方の問題、ジェンダー格差など複合的な要因が関係しているためである。そのため、出産費用の軽減は一定の後押しにはなるものの、出生数全体の反転には限界があるという判断が多い。
また、国際比較研究では、出生率の改善には、保育サービスの拡充や働き方改革、男性の育休取得促進など、子育て期間を通じた支援体制の強化が不可欠だとされている。こうした取り組みが併せて進められることで、初めて出生率の改善につながるとの指摘が相次いでいる。
おわりに
出産費用の無償化は、家計負担を減らし、出産をためらう人々にとって重要な支援となる。全国一律の価格水準が実現すれば、地域間の不公平もある程度解消されるだろう。しかし、出生率の低下は広範な社会課題の反映でもあるため、一つの政策で流れを変えることは難しい。むしろ、出産費用の無償化を手がかりに、妊娠・出産から子育てまでを総合的に支える仕組みを築けるかどうかが問われている。