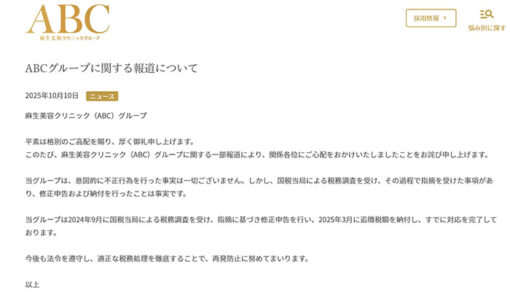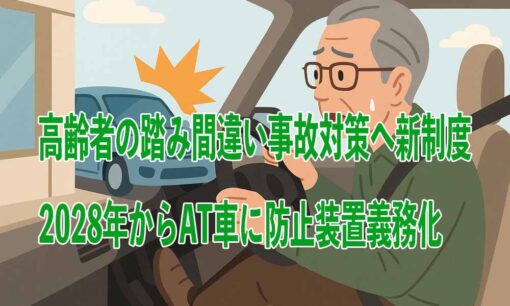大分市佐賀関で発生した大規模火災は、約170棟を焼損し、多くの住民が避難生活を続けている。行政は義援金の受け付けや相談窓口の設置を進め、住宅確保や生活再建への支援を本格化させている。一方で、鎮圧状態となった今も原因調査と復旧作業は続き、地域全体での支え合いが欠かせない。避難所の現状と支援制度、復興への課題を整理する。
大分・佐賀関の大規模火災 住まいを失った人びとをどう支えるか
――長期化する避難生活と復旧への課題
大分市佐賀関地区で11月18日に発生した大規模火災は、住宅密集地と周辺の山林を焼き尽くし、住民の暮らしを一変させた。読売新聞によると、住宅地と一部山林を合わせた焼損面積は約4万8900平方メートルに達し、建物被害は約170棟。総務省消防庁のまとめでは、2016年の新潟県糸魚川市の大規模火災(147棟焼損)を上回り、地震や林野火災を除く市街地火災としては「平成以降で最悪規模」とされる。
大分市消防局は20日午前、住宅地と佐賀関半島側の山林について「延焼の恐れがほぼなくなった」として「鎮圧状態」に入ったと発表した。一方で、被災地から南東方向に約1.4キロ離れた無人島・蔦島では、なお白煙が上がり、鎮火には至っていない。
出火から3日目を迎えても、被災者は自宅に戻る見通しが立たないまま、不安な避難生活を続けている。
生活の拠点を突然失った人びと
大分市の資料によると、今回の火災では最大で121世帯・180人が、佐賀関市民センター内の佐賀関公民館に避難した。その後も避難生活は続き、20日正午時点でも70世帯・108人がセンターでの避難生活を送っている。
避難所では、市の備蓄物資に加え、日本赤十字社が毛布やタオルケット、緊急セットなどを配布。20日朝には「吉野鶏めし」のおにぎりが提供され、昼食と夕食にはおでんやパンが振る舞われたと報じられている。
服や日用品を持ち出す余裕もないまま避難した人が多く、「着の身着のまま逃げてきた」「洋服もタオルもなく、体を洗うこともできない」といった声が伝えられている。
自宅を失った高齢者や持病のある人にとって、慣れない集団生活は心身への負担が大きい。夜間の冷え込み、プライバシーの確保、服薬管理や食事内容の調整など、きめ細かい生活支援が欠かせない。
「鎮圧」後も続くリスク 延焼・被害拡大の要因をどう見るか
今回の火災では、なぜ被害がここまで拡大したのか。日テレNEWSなどの検証報道によれば、次のような要因が指摘されている。
- 木造住宅が密集する古い街並み
狭い路地に木造家屋が立ち並ぶ「裸木造」の地区が多く、防火区画が十分でなかった。これは糸魚川市の大規模火災と構造的に似た特徴だとされる。 - 強風と空気の乾燥
火災発生当時、豊後水道には強風注意報が出ており、海からの西寄りの風が火の粉を運び、飛び火が起きやすい条件だったと専門家は分析している。 - 道路事情と消火活動の難しさ
路地が複雑で幅も狭く、消防車両の進入が難しい場所が多かった。加えて、海に面した地形のため、ホースの延長や水利の確保など、消火活動に時間がかかったとされる。
半島側の火は鎮圧状態となったものの、山林の根や土中にくすぶった火種が再燃する可能性は残る。蔦島では今も消火活動が続いており、ヘリコプターによる上空からの散水が欠かせない状況だ。
今後の注意点としては、次の点が挙げられる。
- 再燃・二次災害への警戒
焼け跡のがれき撤去や家屋解体の際に、残った火種により再び出火するリスクがある。現場には立ち入り規制が続いており、専門家や消防による安全確認を経たうえでの作業が求められる。 - 老朽家屋・空き家対策の検証
空き家が多い地区で被害が拡大したことから、木造密集地域の空き家管理や耐火改修、防火帯の整備など、中長期的な「まちづくり」と一体となった防災対策が課題となる。 - 高齢化地域での避難体制
住民の高齢化が進む港町で、どう命を守るか。今回、近隣住民が声を掛け合い、高齢者を支えながら避難したことが多くの命を救ったとされる一方で、平時からの個別避難計画や支援体制の整備が問われている。
住まいと暮らしを再建するための公的支援
火災によって住居を失った人びとには、今後、一定の公的支援が適用される見込みだ。現時点で公表されている主な枠組みは次の通りである(詳細は今後の自治体の正式決定を待つ必要がある)。
罹災証明書と生活再建支援
- 罹災証明書の発行
住宅の被害程度に応じて、市が「全焼」「半焼」「一部損壊」などを判定し、罹災証明書を発行する。これが、各種支援金や減免措置を受ける前提になる。 - 被災者生活再建支援金などの対象
地震や風水害と比べると、火災のみの災害で生活再建支援金がどのように適用されるかはケースによって異なる。今回の火災では災害救助法が適用されており、今後、住宅再建に関する具体的な支援メニューが整理されていく見通しだ。 - 公営住宅・社宅の提供
地元企業であるJX金属製錬佐賀関製錬所は、社員寮の空き部屋31室を被災者の受け入れに提供する意向を示している。今後は市営住宅や県営住宅の活用なども含め、長期的な住まい確保の方策が焦点となる。
生活相談窓口の設置
大分市社会福祉協議会は20日、被災者の「困りごと」を聞き取るための「大分市地域ささえあいセンター」を、佐賀関市民センター2階視聴覚室に開設した。ここでは、生活や介護、福祉サービスの利用、仕事の不安など、幅広い相談を受け付けている。
避難生活が長引くほど、心身の疲労や家計への不安は募る。単に「物資を配る」支援から、「生活再建の見通しを一緒に考える」支援へと, 支え方を変えていくことが求められる。
事業者への支援と雇用の確保
今回の火災では、住宅だけでなく、店舗や事業所も多数被災したとみられる。地域の雇用や経済を守るうえで、事業者への支援も重要だ。
経済産業省と九州経済産業局は20日、火災で被災した中小企業・小規模事業者を対象に、特別相談窓口の設置や災害復旧貸付、セーフティネット保証4号の適用などの支援措置を発表した。日本政策金融公庫や商工中金、商工会議所などでも相談を受け付けている。
被災店舗の再建には時間と資金が必要である。迅速な資金繰り支援とともに、仮店舗や共同出店の場をどう確保するかも課題となるだろう。
現地支援窓口と義援金の情報
支援したい人にとって、公的・公認の窓口を通じて支援することが、トラブルを避けるうえでも重要だ。現時点で公開されている主な窓口は以下の通りである。
1.大分市の義援金受付
- 窓口
大分市は20日、被災者支援のための義援金の受け付けを開始した。募金箱は- 市役所本庁舎1階案内所
- 佐賀関支所を除く市内7支所(鶴崎、大南、稙田、大在、坂ノ市、野津原、明野)
に設置されている。
- 受付期間
2025年11月20日〜12月19日 - 振込による義援金
振込による受付の準備も進められており、詳細は今後市の公式サイト等で案内される予定だ。
2.日本赤十字社による支援
日本赤十字社大分県支部は、大分県の要請を受けて、避難所に毛布や緊急セットなどの物資を配布している。今後、日赤本社や県支部が義援金口座を開設する可能性もあり、最新情報は日本赤十字社の公式サイトで確認する必要がある。
3.NPO等による緊急支援
民間の災害支援団体「空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”」は、現地でのニーズ調査や物資支援のため、緊急支援チームの派遣を決定し、オンラインで寄付を受け付けている。
また、大分県は、災害ボランティアの受け入れについて、県の中間支援組織「おおいた災害支援つなぐネットワーク(O-Link)」を通じて調整する方針を示している。個人で現地に入るのではなく、公式なルートを通じた参加が求められている。
地域のつながりが支援の鍵に
災害からの回復には、行政だけでなく、自治会やボランティア、企業、そして全国から届く支援が、互いに連携して動くことが欠かせない。ふるさと納税を活用した寄付窓口の設置や、物資提供を調整する仕組みづくりなど、地域ぐるみの支え合いが今後いっそう重要になるだろう。
避難所で暮らす住民の一人は「落ち着ける場所さえあれば前を向ける」と話す。被災者一人ひとりの事情に寄り添い、誰一人取り残さない復興計画をどう描くかが問われている。
今後の見通しと課題
大分市と大分県は、災害救助法の適用を受けつつ、自衛隊や消防、警察と連携して消火・捜索活動と被災者支援を続けている。住宅地の鎮圧が確認されたことで、今後は次のステージに移る。
- 焼け跡の安全確認とがれき撤去
- 被災家屋の被害認定と罹災証明書の交付
- 避難所から仮住まいへの移行支援
- 子どもや高齢者への心理的ケア
- 生活と仕事の両面での再建支援
糸魚川大火の例では、都市計画や防火対策の見直しが全国の木造密集地域にとっての「教訓」となった。今回の佐賀関の火災もまた、港町や漁村など、全国各地に残る古い街並みが抱えるリスクを浮き彫りにしている。
被災した人びとが、もう一度この町で暮らしていきたいと思えるような復興を実現できるかどうか。その成否は、行政の支援策はもちろん、地域のつながりと、全国から寄せられる支援の力にかかっている。