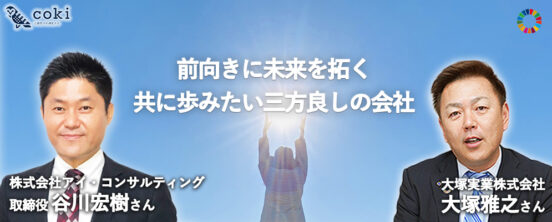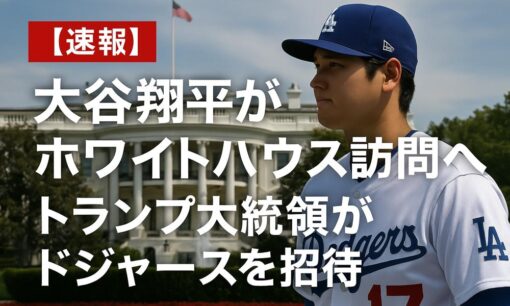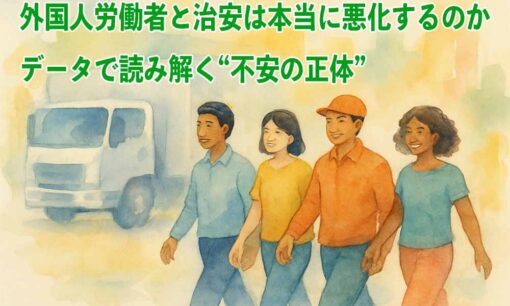肩こりが慢性化する背景には、首の深層にある「頸長筋(けいちょうきん)」の機能低下が関わっているとの指摘が広がっている。スマートフォンの長時間使用やデスクワークで姿勢が乱れ、首のインナーマッスルがうまく働かなくなると、頸椎の動きが硬くなり、肩や背中に負担が集中しやすくなるためだ。本記事では、専門家が解説する頸長筋のメカニズムと改善エクササイズに加え、アスリートが日常的に実践する身体メンテナンスの要点を整理した。生活習慣のなかで取り入れやすい予防と対策を示し、肩こりに悩む人の体づくりを多面的に支える内容となっている。
首の深部で何が起きているのか
寒さが増す季節、肩こりに悩む声が例年より早く聞かれる。近年、その原因として注目されているのが、首のインナーマッスルである「頸長筋」だ。シドニー、アテネ、北京の各五輪で水泳チームドクターを務め、体幹深部筋研究の第一人者として知られる金岡恒治・早稲田大学教授は、この小さな筋肉が首と肩の機能を大きく左右すると指摘する。
頸長筋は首の前側、骨の近くに位置する比較的薄い深層筋で、頸椎(首の骨)を安定させ、滑らかに動かす働きを担う。スマートフォンの長時間使用やデスクワークによる姿勢の乱れにより、この筋肉が十分に働かず“サボりやすい状態”になるとされる。
MRIの比較映像では、頸長筋が働いている場合は顎を軽く引き、頭部を丸めながら起き上がる動きになるが、機能していない場合は顎から持ち上がるような不自然な動作となり、頸椎下部に負担が集中しやすい。これは一つの傾向であり個人差はあるものの、深層筋が働かない場合に負荷が偏る可能性は医学的にも指摘されている。
“亀首”が頸長筋を弱らせる
頸長筋が本来の役割を果たしにくくなる背景には、頭部が体の前に突き出した「亀首」と呼ばれる姿勢がある。猫背に首の前傾が加わった状態で、成人の頭の重さ(約5kg程度)が首の上に真っすぐ乗らず、支える筋肉に負担がかかりやすくなる。
一般に、頭を前に30度ほど倒すと首への負荷は約15kg、60度では約25kgに増えるとされるが、これはあくまで目安であり個人差を含む概算値だ。ただ、この姿勢が首や肩に大きな負担を与えること自体は専門家の間で広く共有されている。
負担が偏った状態を放置すれば、肩甲骨周辺の筋肉が補おうとして過剰に働き、肩こりを悪化させる悪循環に入る可能性がある。
自分でできる“頸長筋チェック”
頸長筋が適切に働いているかは、以下の動作で確認できる。
- 上を向いた状態で頭を左右に振る
- 痛みがある
- 動かす際に引っかかりを感じる
- シャリシャリと擦れる音がする
これらは頸椎の可動域や周囲組織の状態を示す一つの指標であり、必ずしも疾患を断定するものではないが、深層筋が十分に働いていない可能性を示唆する。
肩こり改善に取り入れたいエクササイズ
金岡教授が示すエクササイズは短時間で行え、姿勢をリセットする“習慣づけ”に適している。ただし、頸椎疾患を抱える人や痛みが強い人は無理に行わず、必要に応じて医療機関へ相談することが望ましい。
肩こり改善エクササイズ早見表
| 名称 | やり方 | 効果の見込み | 所要時間 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 肩甲骨クローズ | ①腕を上げる ②手のひらを外側へ ③ひじを後方へ引き下げる ④肩甲骨を寄せる | 頭部の位置が整いやすく、姿勢のリセットに貢献 | 数十秒・2〜3回 | 痛みが出ない範囲で実施 |
| にわとりエクササイズ | ①首は固定し顔だけ前へ ②元の位置へ戻す | 頸長筋を刺激し、前傾姿勢の改善に役立つ可能性 | 朝に2〜3回 | 肩を動かさない |
| あご引きおじぎ | ①背筋を伸ばす ②首→背中→腰の順に丸める ③逆順に起き上がる | 頸椎の動きを滑らかにし、負担軽減の一助となる | 約1分・2〜3回 | ゆっくり動かし深層を意識 |
アスリートは体をどう守っているのか
トップアスリートは、深層筋の働きが競技力の基盤であることを経験的に理解している。頸長筋のような小さな筋肉の機能が、フォームの安定や怪我の予防に影響する可能性があるため、日常から丁寧なメンテナンスを行う。
深層筋の“質の高い働き”が競技力を支える
表層筋の筋力だけでなく、深層筋が適切に働くことで、動作が滑らかになり、身体のブレが減る。水泳・体操・陸上選手などは、ウォームアップの段階から頸椎や背骨のしなやかな連動性を重視する。
“痛みを作らない姿勢”を日常で徹底する
アスリートが重んじるのは、練習中よりも日常の姿勢管理だ。
- スマートフォンを胸の高さより下で見ない
- 長時間座り続けず、20〜30分ごとに肩甲骨を動かす
- 疲れ姿勢に気づけばすぐリセット
- 荷物の偏りを避ける
小さな習慣の積み重ねが体のゆがみを防ぎ、怪我の予防にもつながる。
継続の秘訣は“儀式化”と“微細な変化への気づき”
アスリートはメンテナンスを毎日の“儀式”として組み込む。朝の動きのチェック、練習後の肩甲骨リセットなど、流れを固定することで習慣化が進む。
さらに、
- 首の可動域の微妙な差
- 昨日との動きの違い
- 肩の高さのわずかなズレ
こうした微差に気づく力が、ケア内容を適切に調整する基盤となる。
競技ごとの重点ポイント
- 水泳:頸椎の回旋が大きいため、深層筋の安定性が重要
- ランニング:頭の位置のズレが全身のフォームに影響
- 球技:接触が多く、頸椎の安定・保護が不可欠
深層筋の機能不全がパフォーマンスに影響する可能性は、どの競技にも共通している。
一般の肩こり対策にも活かせるアスリートの視点
アスリートの身体管理は、一般の生活にも応用できる。短時間のリセット動作を習慣化し、疲れ姿勢をそのままにしない考え方は、肩こりや首の負担軽減に役立つと期待される。