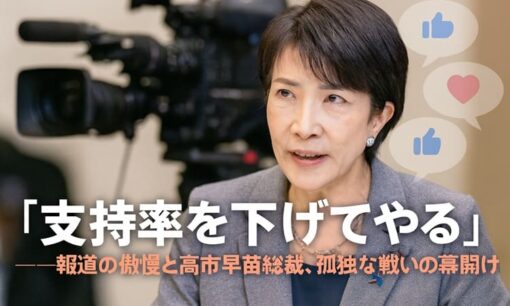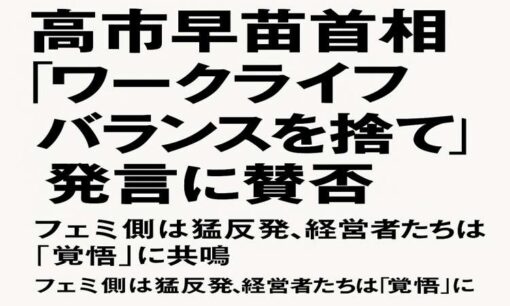時事通信社は9日、同社所属の男性カメラマンが自民党本部での取材待機中に「支持率下げてやる」などと発言した問題で、本人を厳重注意したと発表した。インターネットの生中継で音声が拡散し、報道の公正性と中立性に対する深刻な疑念が投げかけられている。
発生した「不適切発言」の全容:マイクが拾った「本音」の衝撃
大手通信社である時事通信社は2025年10月9日、同社に所属する男性カメラマンに対し、厳重注意処分を下したことを発表した。この処分は、カメラマンが自民党本部での取材待機中に、極めて不適切かつ報道の公平性を損なう発言をしたことが原因である。
問題の発言が確認されたのは、自民党の高市早苗総裁が、新執行部の発足に伴い党本部で取材に応じる予定となっていた10月7日午後のことだ。時事通信社の男性カメラマンは、高市総裁の「ぶら下がり取材」対応を待つため、他社のカメラマンらと党本部内の待機場所に集まっていた。
この待機中、報道陣の一部による雑談の内容が、一部メディアが生中継していたインターネット配信のマイクによって偶然拾われてしまった。そして、この雑談の中に、時事通信社のカメラマンによる、極めて問題のある発言が含まれていたことが後に判明する。
同社が確認したカメラマンの発言は、主に以下の二点である。
- 「支持率下げてやる」
- 「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」
これらの発言は、政治権力に対して意図的に不利益な報道を行う、あるいは報道姿勢に個人的な政治的意図を反映させることを示唆するものであり、「公正な報道」を生命線とする報道機関の人間として、断じて許容されないものであった。
発言が収録された動画は、その後すぐにX(旧ツイッター)などのSNSを通じて爆発的に拡散された。朝日新聞の報道によると、ライブ配信の切り抜き動画を含む投稿は、8日夜の時点で約3700万回以上表示されるなど、社会的に大きな波紋を呼んだ。動画を見た一般の視聴者からは、「冗談であったとしても許されない」「メディアの偏向報道の証拠だ」といった、報道機関全体に対する強い批判が相次いだ。
報道機関としての中立性を問う厳重注意:時事通信の公式対応
この事態を受け、時事通信社は速やかに事実確認を行い、当該発言が自社の映像センター写真部所属の男性カメラマンによるものであると特定した。そして9日、同社は公式にこの事実を認め、本人に厳重注意を行ったことを発表した。
今回の発言は、あくまで「他社のカメラマンらとの雑談中」に行われたものであった。しかし、時事通信社は、雑談という場での発言であったとしても、その内容が「報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」として、この事案を重く見て厳重注意処分に踏み切った。この判断は、報道のプロフェッショナルとして、公的な場以外での言動にも高い倫理観が求められるという認識を示すものだと言えるだろう。
時事通信社は、ニュースサイトへの記事掲載や公式X(旧ツイッター)での公表を通じて、社会と関係者への謝罪を表明している。
同社の斎藤大社長室長は、今回の問題について以下のようなコメントを発表した。
- 「自民党をはじめ、関係者の方に不快感を抱かせ、ご迷惑をおかけしたことをおわびします」
- 「報道機関としての中立性、公正性が疑われることのないよう社員の指導を徹底します」
また、藤野清光取締役編集局長も、報道の公正性・中立性に疑念を抱かせた点を指摘し、厳重注意を行ったとしている。
その他の疑惑発言と時事通信の見解
SNS上では、この「支持率下げてやる」という発言以外にも、「イヤホン付けて麻生さん(麻生太郎副総裁)から指示聞いたりして」や「靖国(神社参拝)は譲れません」などといった、高市総裁を揶揄するような内容の音声も拡散されていた。
これらの他の発言についても、時事通信社は社内調査を実施した。その結果、これらは厳重注意処分を受けた同社カメラマンの発言ではないことを確認したとしている。この点については、発言者特定をめぐる混乱が広がる中で、同社カメラマンの発言とそれ以外の発言を明確に切り分けた形だ。
政治側と専門家が示す危機意識:メディアへの信頼回復は急務
今回の「支持率下げてやる」発言は、政治の世界においてもすぐに波紋を広げた。発言があった7日に新執行部が発足し、就任したばかりの自民党の鈴木貴子広報本部長は8日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、この問題について言及した。
鈴木本部長は、拡散された音声について「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であること、を鑑みると非常に残念な発言です」と強い遺憾の意を表明した。
このコメントは、政権与党が、メディアの「不偏不党の原則」を厳しく注視していることを示している。また、鈴木本部長は「発言された者/社を特定することもありませんが、今回の事案でその発言をされた方はもとより、周りで聞いていた方、笑っていた方もきっと何か思うところがあるのでは、と思います」と、その場にいた報道関係者全員の倫理観に訴えかける表現を用いている。これは、メディア側の自己規律に対する期待と同時に、世論の厳しい目が向けられている状況を代弁したものだと言えるだろう。
「常に監視されている時代」の報道倫理
今回の事案が特に深刻なのは、単なる「失言」で終わらず、現代のメディア環境における構造的な問題を浮き彫りにした点にある。
かつての取材現場では、カメラが回っていない、マイクが拾っていない場所での報道陣の会話は、現場限りのものとして扱われることが多かった。しかし、現代は状況が一変している。「壁に耳あり障子に目あり」という古い言葉があるが、今や現場は、マイクやカメラが常時作動するデジタル時代の新たな『監視下』にある。スマートフォンやインターネットの生中継技術が普及したことにより、取材対象者が現れるまでの「待ち時間」も含め、すべての瞬間が公開されるリスクを孕んでいる。
このため、記者やカメラマンといった報道の担い手は、「いつでも、どこからでも見られている」という強い感覚を持ち、改めて意識改革を行うことが強く求められている。たとえ私的な雑談の場であっても、その発言が「報道の公正性、中立性」を損なうものと受け取られる可能性があることを、徹底的に認識しなければならない。
この「全方位監視時代」においては、報道のプロフェッショナルには、公私の区別なく高い倫理観と自律性が求められるのである。
読者が求める「信頼回復」への道筋
今回の時事通信社カメラマンによる不適切発言と、それに伴う厳重注意処分は、報道機関が社会から負託されている中立性の重みを再認識させる事案となった。
報道機関は、特定の政治的主張や支持政党を持たず、事実を客観的に、そして公平に伝えることが、民主主義社会における責務である。この原則が崩れれば、国民は「どの情報が信頼できるのか」という根幹的な判断に迷うこととなり、社会の健全な議論の基盤が揺らいでしまう。
時事通信社が、今回の件について迅速に事実を認め、本人を処分し、公に謝罪した対応は、一定のけじめをつけたものとして評価できる。しかし、SNSで一度拡散された「不信感」は、容易に払拭されるものではない。
今後、時事通信社をはじめとするすべての報道機関に求められるのは、謝罪コメントにある「社員の指導の徹底」を、単なる訓示で終わらせない実効性のある改革として実行することだ。具体的には、全社員を対象とした報道倫理研修の強化や、デジタル時代における取材現場での行動規範の見直し、そして何よりも、日々の報道姿勢そのものを通じて、「我々は公正である」ということを社会に示し続ける必要がある。
政治家や権力者に対する批判的な視点を持つことは、報道のチェック機能として重要である。しかし、それが個人的な感情や意図的な操作にすり替わることは、報道の自殺行為に等しい。読者や視聴者は、感情的な「支持率操作」ではなく、厳密な事実に基づいた公平な情報提供を求めている。
今回の騒動は、報道に携わるすべての人々にとって、「報道とは何か」、そして「プロフェッショナルとしての倫理とは何か」を改めて問い直す、大きな契機となるだろう。報道機関が信頼を回復し、公正な情報社会の実現に貢献できるかどうか、その真価が問われていると言える。
参照:本社カメラマンを厳重注意 =「支持率下げてやる」発言=(時事通信社)
【関連記事】