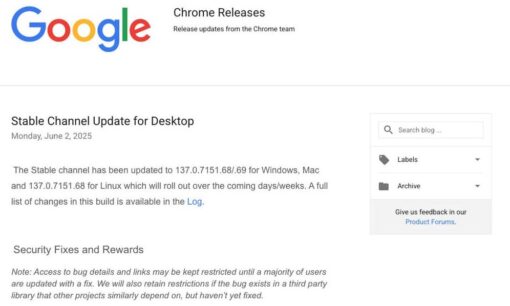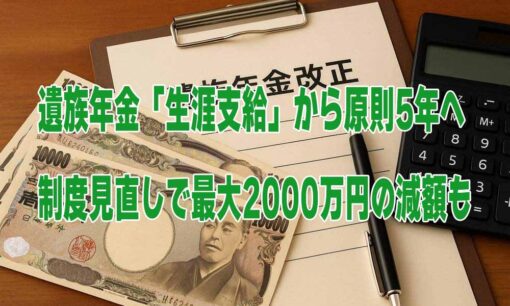全国の自治体病院の経営悪化が深刻さを増している。全国自治体病院協議会の調査では、2024年度決算で86%が経常赤字、95%が医業赤字に陥った。特に大都市近郊では小児科や産婦人科医の不足が際立ち、千葉や埼玉では全国で最少水準となっている。慢性的な人材難と財政難が重なるなか、住民からは「このままでは病院がなくなるのでは」と不安の声が上がる。地域医療を守る最後の砦として、自治体病院の持続可能性をどう確保するかが問われている。
自治体病院の経営の現状
全国自治体病院協議会(全自病)が公表した2024年度決算調査によると、回答のあった自治体病院657施設のうち、86%(562病院)が経常赤字、95%が医業赤字を計上した。これは朝日新聞や医療専門メディア「gemmed」など複数の報道でも確認されており、過去10年で最悪の赤字率とされる。
背景には新型コロナ禍での補助金終了がある。コロナ期には病床確保費などで補助金が手厚く支給され、黒字転換していた病院も多かったが、補助金がなくなり再び赤字に転落した。
さらに、2024年の人事院勧告で国家公務員給与が平均4.4%引き上げられ、自治体病院職員もそれに準じた賃上げが必要となった。一方、同年の診療報酬改定による増収は2.5%程度にとどまり、収入の伸びは支出に追いつかない。加えて電気代や医療資材の高騰が重なり、構造的な赤字体質がより鮮明になっている。
赤字幅は地方に限らず大都市部にも及んでいる。東京都の都立病院では2024年の医業赤字が680億円に上った。慢性的な赤字が全国規模で常態化していることが浮き彫りになった。
利用患者の現状
最も影響が大きいのは、小児科や産婦人科といった採算性の低い診療科である。厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況(2022年)」によれば、
- **小児科専門医(15歳未満人口10万人当たり)**は鳥取県148.5人が最多、千葉県66.1人が最少。
- **産婦人科専門医(15〜49歳女性10万人当たり)**は徳島県66.7人が最多、埼玉県32.4人が最少。
これは、大学医学部や医療インフラ整備が人口流入に追いつかなかった大都市近郊の典型的な課題を示している。特に千葉県や埼玉県といった首都圏近郊では小児科・産婦人科医不足が顕著であり、自治体病院の縮小が進めば「医療空白」に直面する恐れがある。
住民からは「このままでは病院がなくなるのでは」との声が広がり、地域医療崩壊への懸念は現実味を帯びつつある。
働く医師や看護師の実情
小児科や産科はケア項目が多く、分娩や救急対応に長時間を要するため、労働負担が大きい。にもかかわらず収益性は低く、人材確保が難しい。
賃上げ圧力がある一方で病院財政は逼迫し、待遇改善や人員増強が進まない悪循環に陥っている。首都圏郊外のある自治体病院では、今年度も数億円規模の赤字が見込まれており、職員からは「病院がなくなるのでは」と不安の声が出ている。疲弊する現場の実態は深刻だ。
今後の見通しと改善案
自治体病院の赤字問題は単なる経営課題ではなく、国民生活に直結する問題である。感染症指定医療機関、災害拠点病院、救命救急センターといった「不採算だが不可欠」な医療を自治体病院が担っている。全自病の調査では、これら専門病院の赤字割合は9割を超えている。
改善策としては、以下が指摘されている。
- 財政支援の制度化
不採算医療を担う病院への補助金を一時的措置ではなく恒常的に確保する仕組みが必要。 - 地域間医師偏在の是正
小児科・産科医不足が顕著な千葉県・埼玉県などに重点配置するため、大学医学部や研修医制度の調整が求められる。 - 医療連携の強化
民間病院と役割分担を明確化し、自治体病院に過度な負担が集中しない体制を整える。 - デジタル・人材支援
オンライン診療やAIによる業務効率化を進め、医師の負担軽減を図る。看護師やコメディカルの待遇改善も不可欠。
大都市部では自治体病院の割合が低く(東京都では全病床の8.3%)、災害やパンデミック時に医療需要が急増すれば民間病院だけでは対応困難になる。自治体病院の持続可能性を高めるためには、医療従事者・自治体・国民が広く議論に参加し、合意形成を図ることが不可欠である。