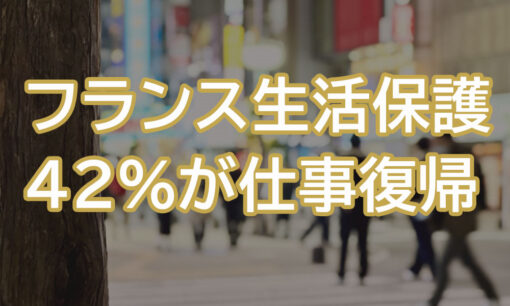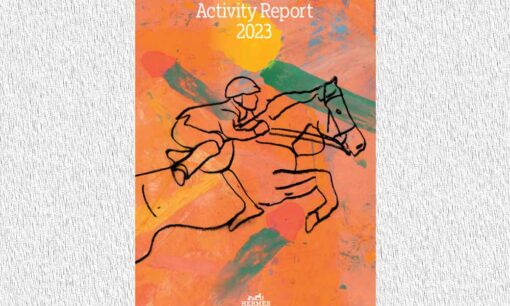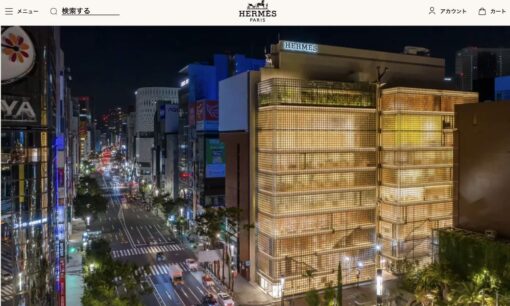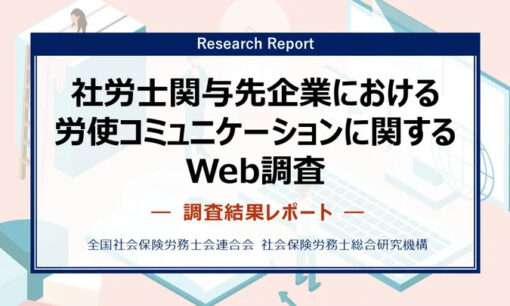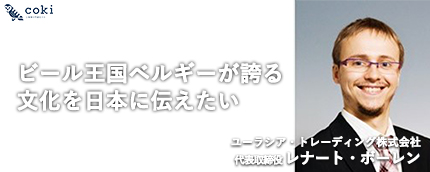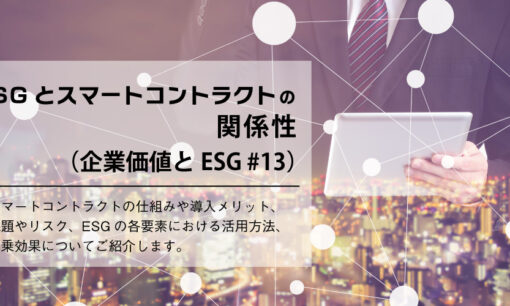汚染の川から“市民の誇り”へ、五輪が導いた100年越しの大転換

1923年に遊泳禁止となってから、ちょうど1世紀。2025年7月5日、パリ中心部を流れるセーヌ川で、ついに一般市民の水泳が解禁された。かつて「汚れた川」として忌避されてきたこの水辺は、今やパリ市民と観光客の歓声に包まれた新たなレジャースポットへと生まれ変わった。
背後にあるのは、2024年パリ五輪がもたらした14億ユーロ(約2300億円)もの浄化投資と、市・国を挙げた水質改善の総力戦だった。セーヌ川復活は、五輪のレガシーという言葉を象徴的に体現した成功例といえる。
100年間“泳げなかった川”の過去
20世紀初頭、セーヌ川は市民が水浴びを楽しむ親しみ深い存在だった。だが産業化の進展とともに川の水質は悪化し、1923年に遊泳は禁止。その後も下水や工場廃水が直接流入し続け、1990年代には「重金属汚染が世界最悪レベル」とも評された。
1990年、当時のパリ市長ジャック・シラク(後に大統領)は「3年以内に泳いでみせる」と宣言したが、それは果たされなかった。専門家も「2020年以前には泳ぐという発想そのものがなかった」と指摘する。
パリ五輪が変えた計画の現実性
転機となったのが、2024年のパリ五輪・パラリンピックだった。トライアスロンやオープンウォーター競技をセーヌ川で開催するため、パリ市とフランス政府は大規模な水質浄化に着手。プロジェクトの予算は14億ユーロに上り、20以上の政府・行政機関が関与した。
下水や雨水が川へ直接流れ込まないようにするための地下貯水トンネルの建設や、下水処理場への接続義務化など、かつて不可能と思われた都市型水域の再生が本格化した。特に、嵐や豪雨時に備えて設置された貯水池は、20個分のオリンピックプールの水量を一時的に貯留できる構造となっている。
パリ東部の巨大施設「セーヌ=ヴァラントン」では、排水に酸化剤を添加することで病原菌レベルを劇的に抑える技術も導入された。
一般開放までの“最後のハードル”
セーヌ川の水質は日々の天候や船舶の動きによって大きく変動する。そのため、遊泳場の安全管理は極めて厳格に設計されている。市当局は欧州の水質基準に基づいた検査を毎日実施し、水質が悪い日や流れが速い日は「赤旗」を掲げて入水を禁止。
現在、遊泳が許可されているのはエッフェル塔周辺やノートルダム付近など3カ所のみで、それ以外の場所では引き続き遊泳禁止が続く。
市民の声と新たな課題
解禁初日、サンルイ島付近には数百人の行列ができたようだ。開始3時間前から並んだ24歳の男性は「歴史的な日。水温もちょうどよく、パリの誇りだ」と語った。
一方で、「まだ水が濁っていて不安」「観光船が多く怖い」といった懸念も根強い。実際、昨年の五輪競技後には一部選手の体調不良が報告されたが、川との因果関係は不明のままだ。
水質測定技術においても「現在の評価法ではリスクを過小評価している」と警鐘を鳴らす研究者もいる。技術面・科学面での持続的な改善が、今後の本格普及には不可欠だ。
なぜ泳げるようになったのか セーヌ川復活の本質
「泳げる川にする」ことは、単なる衛生環境の向上だけでなく、都市の公共空間の再設計である。パリ市長アンヌ・イダルゴ氏が掲げた「市民が川に触れ合える都市構想」の具体化でもあり、五輪はその手段であり、加速装置だった。
このプロジェクトは、水質浄化だけでなく都市インフラ全体をアップデートする試みだった。老朽化した下水道網の更新、住宅の排水システム接続、ハウスボートの処理義務化など、暮らしの“裏側”に大きな変革が加えられた。
そしてその成果が、2025年夏、セーヌ川を泳ぐ市民たちの姿として結実したのだ。