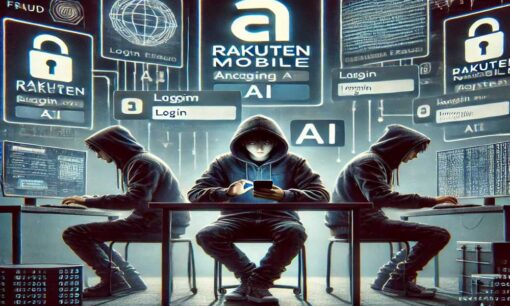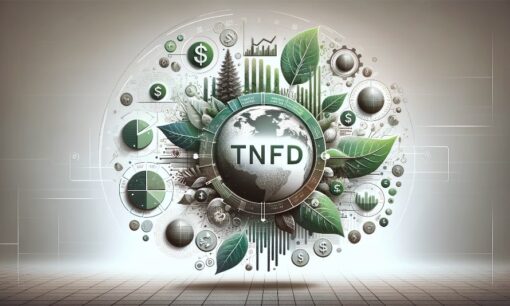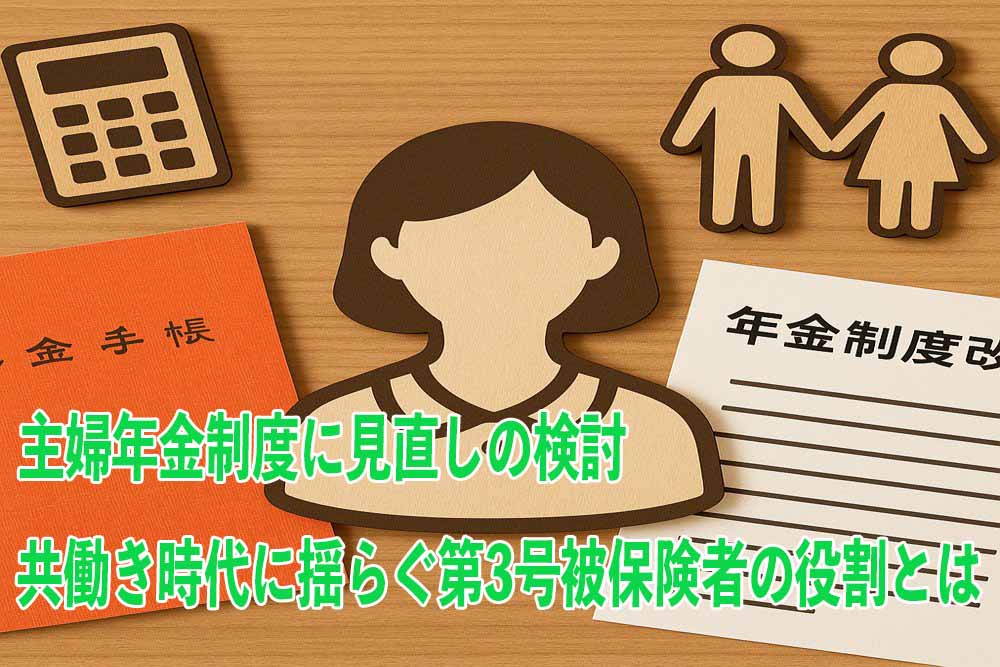
共働き世帯が主流となる中、専業主婦などが保険料を納めずに年金を受け取れる「第3号被保険者制度」が見直しの対象となりつつある。政府が5月に示した年金制度改革法案では、制度の将来的な在り方を検討する文言が初めて付則に盛り込まれた。国民年金の納付期間延長も併せて議論されており、今後の制度設計が注目される。
■専業主婦でも保険料なしで年金受給 支え続けてきた制度に初の見直し明記
政府が進める年金制度改革の中で、いわゆる「主婦年金制度」の見直しが初めて付則に明記された。対象となるのは、会社員や公務員の配偶者である専業主婦らを対象にした「第3号被保険者」制度。1986年の制度導入以来、年金保険料の負担なく将来の年金受給が認められてきたが、共働きが多数派となった現代にそぐわないとの指摘が強まり、改革の機運が高まりつつある。
■【図解】第1号~第3号被保険者の違い
| 区分 | 対象者 | 加入制度 | 保険料の負担 | 年金受給の仕組み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 自営業者・学生・無職など | 国民年金 | 自分で全額納付 | 基礎年金のみ | 所得が少ないと免除制度あり |
| 第2号 | 会社員・公務員 | 厚生年金+国民年金 | 会社と折半で天引き | 基礎年金+報酬比例年金 | 被扶養配偶者に第3号資格あり |
| 第3号 | 第2号被保険者に扶養される配偶者(年収130万円未満) | 国民年金(みなし加入) | 保険料負担なし | 基礎年金のみ | 制度上は「無拠出で年金受給」 |
■共働き世帯が多数派に 「不公平」との声も
共働き世帯の増加に伴い、3号制度をめぐっては「保険料を納めていないのに年金を受け取れるのは不公平」「労働時間をセーブして扶養の範囲にとどまろうとする要因になっている」といった批判が根強く存在する。
実際に、専業主婦の世帯数は1986年の約900万世帯から2022年には430万世帯に減少。逆に、共働き世帯は2022年に1191万世帯と、大きく上回る状況となっている。
こうした社会構造の変化を背景に、経済同友会や連合などの経済・労働団体からは制度の将来的な廃止や見直しを求める声が上がっている。
■【年表】主婦年金制度(第3号被保険者制度)の導入と変遷
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1986年 | 第3号被保険者制度が創設。厚生年金加入者に扶養される配偶者が対象に。 |
| 1990年代 | 共働き世帯が専業主婦世帯を上回る。 |
| 2000年代以降 | 年金財政の厳しさや不公平感から制度見直しの声が高まる。 |
| 2010年 | 一部で「130万円の壁」が社会問題化。制度が就労抑制の要因との指摘。 |
| 2025年 | 年金制度改革法案の付則に、制度見直しの検討が初めて明記される。 |
■所得保障としての役割 「一律廃止には慎重に」との指摘も
一方で、社会保障審議会の年金部会では、病気や介護などの事情で働くことが難しい人たちにとって、3号制度が重要な所得保障の役割を果たしているとの意見も根強い。とくに、子育てや配偶者の介護を担う非労働層に対する支援策としての意味合いも指摘されている。
今回の年金改革法案では、3号制度の即時改正や廃止には踏み込まず、将来的な検討課題として付則に盛り込むにとどまった。
■【表】第3号被保険者制度に対する主な賛否の意見
| 立場 | 意見の要旨 | 背景・論拠 |
|---|---|---|
| 賛成(維持すべき) | 働けない事情のある人への所得保障として重要。 家族内での無償労働を支える仕組み。 | 育児・介護・持病などで働けないケースがある。 |
| 反対(廃止・見直しを) | 保険料を払わず年金を得られるのは不公平。 「130万円の壁」が就労意欲を削ぐ。 | 共働きが多数派になった現代との乖離。負担の不均衡。 |
| 中立(改革は段階的に) | 制度の持続性を考えると見直しは不可避。ただし、移行措置や代替制度が不可欠。 | 突然の廃止は混乱を招くため、段階的対応が必要。 |
■国民年金の納付期間延長も課題に
同じく付則では、国民年金の保険料納付期間(現行40年間)について、延長を検討することも明記された。少子高齢化が進む中で、年金財政の持続性を確保するための措置として、保険料を支払う期間の延伸を求める議論が強まりつつある。
仮に納付期間の延長と第3号制度の廃止が並行して進めば、年金制度全体の「自助」へのシフトが加速することになる。ただし、低所得者や非労働者への新たな支援措置を伴わない改革には、生活保障の観点からの反発も予想される。
■制度の行方は今後の議論に
今回の法改正では、制度変更の具体的な日程や内容には言及されていない。今後は、厚生労働省の社会保障審議会や国会での議論を経て、制度設計が詰められていく見通しである。
かつて「夫が外で働き、妻が家庭を守る」ことが標準とされた時代に整備された仕組みが、現代の多様なライフスタイルに対応しうるのか。年金制度の根幹に関わる見直しは、社会全体での理解と合意形成が欠かせない。