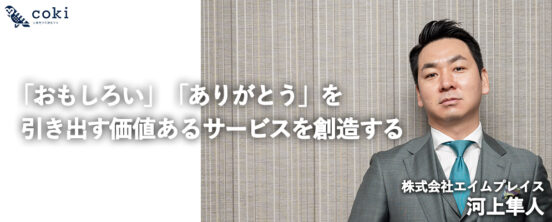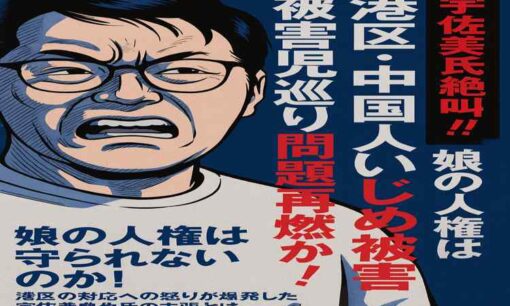北海道で「リンゴ病(伝染性紅斑)」の感染が拡大している。道内では2015年以来10年ぶりに警報レベルを超える保健所が相次ぎ、特に子どもと妊婦への影響が懸念されている。新型コロナの影響で過去数年間流行が抑えられていた反動として、免疫を持たない世代を中心に感染が急増しており、専門家は「感染症への備えが弱まっている」と警鐘を鳴らす。妊婦が感染した場合は胎児に重篤な影響が及ぶ可能性もあり、予防の徹底が急務となっている。
■リンゴ病(伝染性紅斑)の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 伝染性紅斑(Parvovirus B19による感染症) |
| 通称 | リンゴ病(頬が赤く染まる症状から名付けられた) |
| 原因ウイルス | ヒトパルボウイルスB19 |
| 感染経路 | 飛沫感染(咳・くしゃみなど)、接触感染 |
| 潜伏期間 | 約10~20日 |
| 主な症状 | ・頬が赤くなる発疹(典型例) ・微熱、咳、倦怠感 ・関節痛(特に大人) |
| 重症化リスク | 妊婦(胎児への影響)、免疫不全者、溶血性疾患を持つ人 |
| 感染可能な時期 | 発疹が出る「前」がもっとも感染性が高い |
| 治療方法 | 特効薬はなし。対症療法(解熱剤、安静など)。通常は自然回復 |
| 予防方法 | ・手洗い、うがい、マスクの着用 ・体調不良時の外出自粛 |
| 注意点 | 妊娠20週未満の妊婦は胎児水腫・胎内死亡のリスクがあるため特に注意が必要 |
◆コロナ禍を経て、感染症への備えが緩んだ?
北海道内で「リンゴ病」と呼ばれる感染症・伝染性紅斑が再び拡大し、保健所単位での警報基準を4週連続で超過している。道内で警報レベルが確認されたのは2015年以来、実に10年ぶりである。札幌市を含む8つの保健所管内で、定点医療機関あたりの患者数が基準値を大きく上回り、特に小樽では12.5という高い報告数が出ている。
「ここ数年で最も流行している印象だ」と語るのは、札幌市の小児科医・多米淳院長。新型コロナウイルスが猛威を振るった時期には、手洗い・マスク・ソーシャルディスタンスの徹底により、多くのウイルス性感染症の拡大が抑制されていた。その影響で、子どもたちは本来、幼少期に感染して免疫を獲得するはずだった病気に曝露される機会が減っていたという。
加えて、社会全体の感染予防意識の緩みが現在の拡大に拍車をかけていると見られる。「マスクや手指消毒といった基本的な予防行動の継続率が低下していることが、今回の再燃の要因と考えられる」(同院長)との指摘もある。
◆「大人のリンゴ病」見過ごされる重症化リスク
リンゴ病は10〜20日の潜伏期間を経て、微熱・倦怠感・咳といった風邪に似た症状を伴い、頬が赤く染まる発疹が特徴とされる。ただし、これらの症状が出るのは一部であり、大人では発疹が出ない、あるいは関節痛のみが目立つケースも多く、診断が遅れる傾向にある。
特に妊婦が感染した場合は、その影響の深刻さが問題視されている。日本産婦人科感染症学会の山田秀人理事は「妊娠中に感染すると胎児貧血や胎児水腫が引き起こされ、妊娠20週以前の感染では約11%が胎内死亡に至る」と述べ、注意喚起を行っている。
また、幼少期に感染せず大人になってから初感染した場合、強い関節痛や発熱が長引くなど、日常生活に支障をきたすこともある。女性では特に、手首や指の関節に慢性的な痛みが残るケースもあり、症状がリウマチと類似するため医療機関でも誤診されるリスクがある。
◆予防の鍵は「基本の徹底」
リンゴ病に特効薬は存在しない。発症した場合は対症療法が中心で、発疹が出る時期にはすでに他者への感染力は弱まっているとされる。ただし、感染初期の段階では飛沫を通じて他者にうつす恐れが高く、家庭内や保育施設、学校での二次感染が広がりやすい。
有効な対策は、結局のところ「手洗い」「うがい」「マスク着用」といった基本的な感染症対策の徹底に尽きる。感染ピークは7月上旬と予想されており、今後もしばらく注意が必要だ。
とりわけ妊婦や持病のある人、高齢者が身近にいる家庭では、無症状や軽症であっても感染拡大の起点となる可能性がある。症状の有無にかかわらず体調不良時の外出自粛や、密な場所を避けるなどの配慮も求められている。