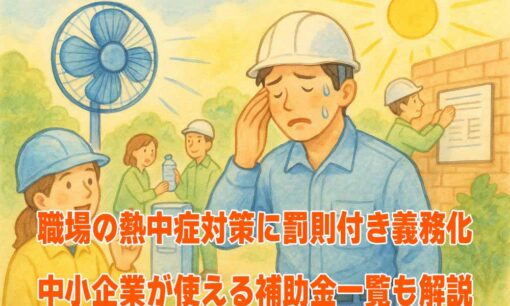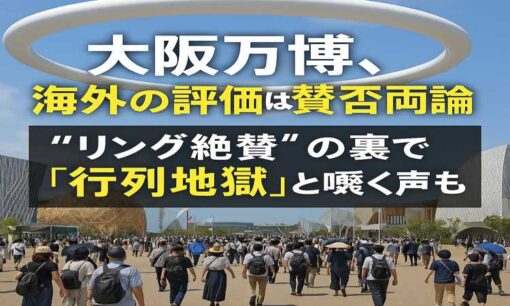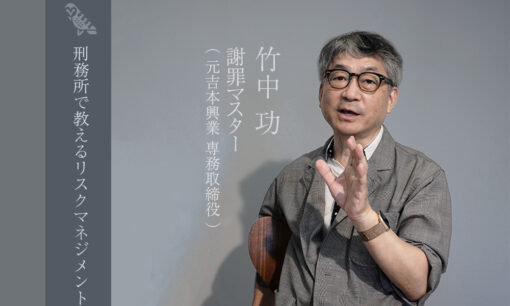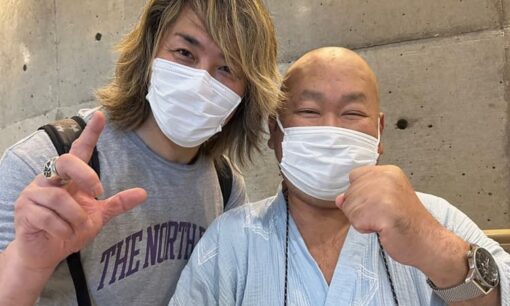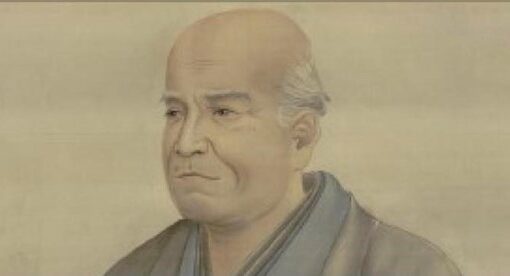夏を前に、水分補給の重要性が高まっている。とくに2~5歳の子どもを持つ家庭では、熱中症対策として「とにかく水分を」と気をつける一方で、思わぬ健康被害を引き起こすリスクも潜んでいる。注目されるのが「ペットボトル症候群」だ。
スポーツドリンクは万能ではない
小児科医の伊藤明子氏(赤坂ファミリークリニック院長)によると、「ペットボトル症候群」とは清涼飲料水ケトーシスとも呼ばれ、糖分を多量に含む飲料を日常的に摂取することで血糖値が異常に上昇し、糖尿病のような状態に陥る症状を指す。吐き気、倦怠感、頻尿、意識障害などを引き起こし、最悪の場合は命に関わる。
とくに体重の軽い幼児は、大人より少ない量でも症状を発症しやすい。スポーツドリンク500mlにはおよそ30~40g(大さじ3~4杯)の糖が含まれており、日常的に飲み続ければリスクは増す。運動中に必要なミネラル補給という本来の目的を逸脱し、習慣化すれば有害となりかねない。
水分補給は「水」か「麦茶」で十分
伊藤氏は、日常生活での水分補給は基本的に水や麦茶で十分であり、特別な事情がない限り、糖分の高い清涼飲料水を与える必要はないと指摘する。どうしても味付き飲料を与えたい場合には、経口補水液を水で薄めるなどの工夫が必要だ。
また、飲料選びの際にはラベルの原材料表示に注意を払うべきだという。「果糖ぶどう糖液糖」などの表示がある場合、それは異性果糖を意味し、摂取しすぎると脂肪肝や肥満を招く恐れがある。実際、日本の子どもの約5%が脂肪肝であるという報告もある。
ペットボトル飲料の衛生面にも要注意
もう一つ、見落とされがちなのが、ペットボトル飲料の「衛生リスク」だ。ペットボトルの飲みかけを室内や車内に放置すると、口から入った細菌が容器内で繁殖する可能性がある。特に暑い季節には、数時間で細菌が増殖し、食中毒の原因となることも。
口をつけて直接飲むスタイルでは、唾液に含まれる細菌が飲料内に入りやすい。未開封の状態でも、開栓後の保存状況が悪ければ危険性は高まる。とくに子どもは体内の抵抗力が未発達なため、少量の細菌でも体調を崩す恐れがある。
食中毒予防のポイント
厚生労働省や自治体が推奨する食中毒予防の三原則「つけない、ふやさない、やっつける」は、ペットボトル飲料の扱いにも応用できる。
- 飲みかけを長時間放置しない(ふやさない)
- 直接口をつけず、コップに注いで飲む(つけない)
- 暑い場所に放置せず、冷蔵保存し24時間以内に飲み切る(やっつける)
また、持ち歩きには水筒の活用も有効だ。中身を清潔に保ちやすく、衛生管理がしやすい。
家庭でできる水分補給習慣の見直しを
子どもの水分補給については、利便性や習慣だけで判断せず、糖分や衛生面のリスクにも注意を払いたい。甘い飲料を「見ない・買わない・持ち込まない」を徹底し、代わりに水や麦茶、健康的な補食を与えるなど、家庭での取り組みが問われている。
日々の選択が、子どもの未来の健康に大きく関わる。暑さが本格化する前に、いま一度、家庭の水分補給のあり方を見直すべきときだ。