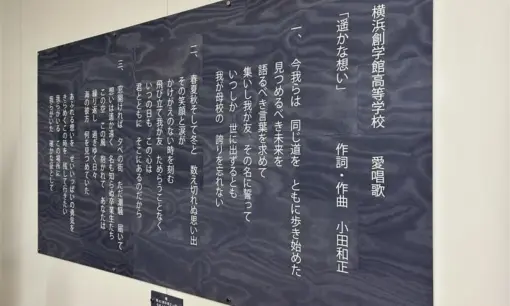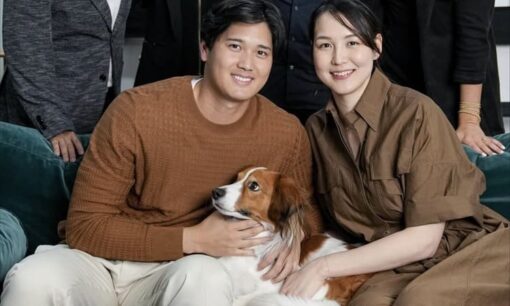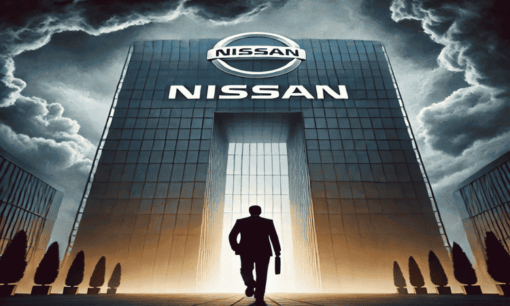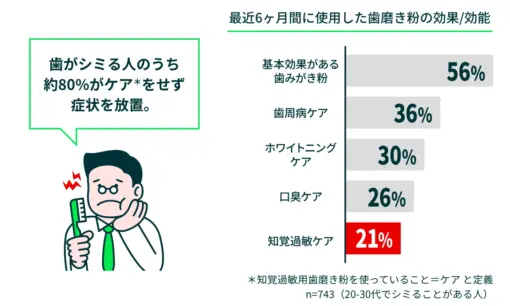給食費は10年据え置きのまま、米や牛乳の価格は右肩上がり――。広島市の公立小学校では、物価高騰の影響が学校給食にじわじわと及んでいる。副食に割ける予算は圧迫され、子どもたちの楽しみだった献立にも影が差しつつある。制度上の制約から給食費の引き上げは容易ではなく、その負担は現場にのしかかる。限られた予算の中で、工夫と情熱によって一食一食を支える現場の姿から、今の学校給食が抱える課題と意義が浮かび上がる。
米価・牛乳高騰が副食予算を圧迫 広島市の現場に広がる「献立の苦悩」
全国で相次ぐ食料品の値上げが、学校給食の現場にも深刻な影響を及ぼしている。広島市西区の市立高須小学校では、物価高により主食や牛乳の価格が高騰し、副食にかけられる予算が削られるという構造的なひずみが生じている。給食費は過去10年間据え置かれており、現場では栄養教諭や調理スタッフの工夫によって質の維持が図られているが、その努力には限界がある。
高須小学校では、校内の給食室で約500食を調理する「自校調理方式」が採用されている。食中毒や二次汚染を防ぐため、衛生管理は徹底されており、調理室への立ち入りは検便済みの職員に限られている。栄養教諭の下沖真千子氏は「ご飯もすごく高いので、おかずにかけられるコストにしわ寄せがいく」と話す。
広島市では、給食の献立に対し、「栄養バランス」「食育教材」「安全安心」という三つの基本方針が定められている。だしは昆布や鰹節から丁寧に取り、行事食や郷土食材も積極的に取り入れられているが、近年の物価上昇はこの運用を直撃している。
副食費の補助はわずか1円増 拡充が追いつかない制度の限界
広島市内の公立小学校では、保護者が支払う給食費は1食あたり250円に設定されている。この金額は過去10年間変更されておらず、近年の物価高騰に対して行政が拠出する補助金で何とか補っている状況だ。
市は国の交付金を活用し、1食あたりの補助額を前年より15円増の49円に引き上げたが、そのうち14円は主食や牛乳の値上げ分に充てられており、副食の増額分はわずか1円にとどまっている。栄養教諭らは「季節の果物やデザートを入れたいが、予算上難しい」とこぼす。
献立作成会議では、「少しでも子どもたちの楽しみになるようなメニューを維持したい」といった声が上がる一方で、出汁の抽出時間を延ばす、野菜の使用量を最小限に調整するなど、わずかな調整でやりくりする工夫が続いている。
給食費はなぜ上げられないのか 制度と現場のはざまで
給食費が10年間にわたって据え置かれてきた背景には、保護者への配慮と制度上の制約がある。
まず、学校給食費は「教育費」ではなく、児童が食事をするための実費としての位置づけがなされている。文部科学省は、学校給食を「教育の一環」としつつも、食材費は保護者負担が原則と明示しており、各自治体が定める条例や要綱に基づいて徴収されている。
給食費の増額には、保護者への説明や同意、徴収体制の再構築といった調整が必要になる。物価上昇が進む一方で、保護者の生活も逼迫していることから、増額への反発を避けたいという思惑もある。全国的には給食費無償化に舵を切る自治体もある中で、広島市が独自に値上げを決断することは政治的・制度的に困難とされている。
その結果、行政は補助金の拡充で対応しようとするが、その規模には限界があり、実質的な負担の多くは給食現場に転嫁される構図が続いている。
「楽しみ」を削らないための現場の創意工夫
高須小学校では、価格の安い鶏ムネ肉を煮込み料理に活用しつつ、唐揚げのように子どもに人気の高いメニューではあえて鶏モモ肉を用いるなど、味と食感を大切にした使い分けがなされている。昆布や鰹節の量を減らして煮出し時間を延ばすなど、コストと品質を両立させるための細やかな工夫が随所に見られる。
5月の「こどもの日」に合わせた献立では、「大きく育ってほしい」という願いを込めてタケノコの炊き込みご飯が提供された。こうした行事食には食文化の継承や四季を感じる教育的意義も込められており、物価高の中でも食育の軸がぶれることはない。
子どもたちの声が伝える給食の価値
給食の時間、教室には笑顔と歓声が広がる。「全部おいしかった」「地域の野菜を食べられてすごくうれしい」――子どもたちは、調理の苦労や献立に込められた思いを素直に受け止めている。実際、残菜はほとんどなく、調理の工夫が味と満足度に結びついていることがうかがえる。
戸田美鈴校長は、「給食室は、楽しく美味しく食べられるように工夫しているので、こどもたちもその気持ちを汲んで、しっかり食べてもらいたい」と語る。下沖栄養教諭も「安い材料を使うということばかりではなく、調理で工夫できるところを見つけながら、安全でおいしい給食を作っていきたい」と語る。
学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提供するだけでなく、郷土の食材や年中行事を通じて食の知識や文化を伝える、かけがえのない教育の場でもある。物価高騰の波がこの貴重な教育機会を脅かさないように、制度と現場の両面から持続可能な在り方がいま問われている。