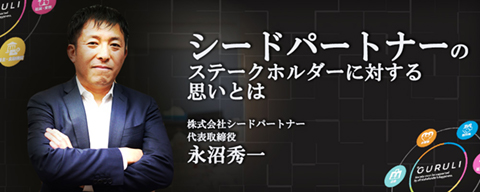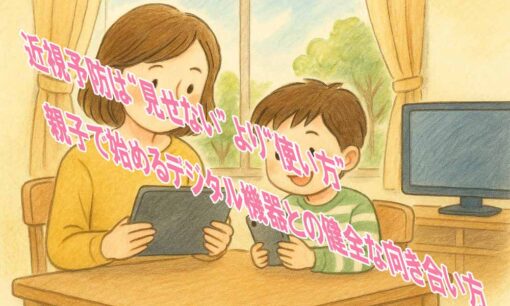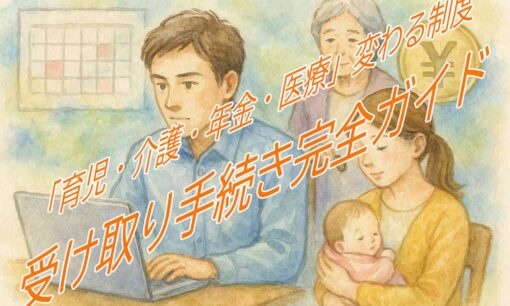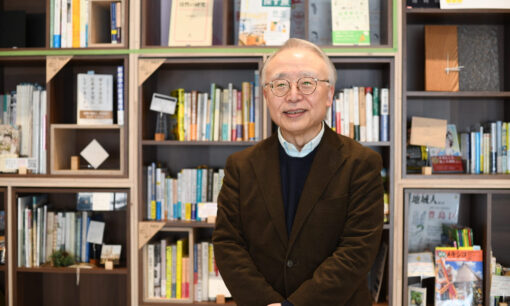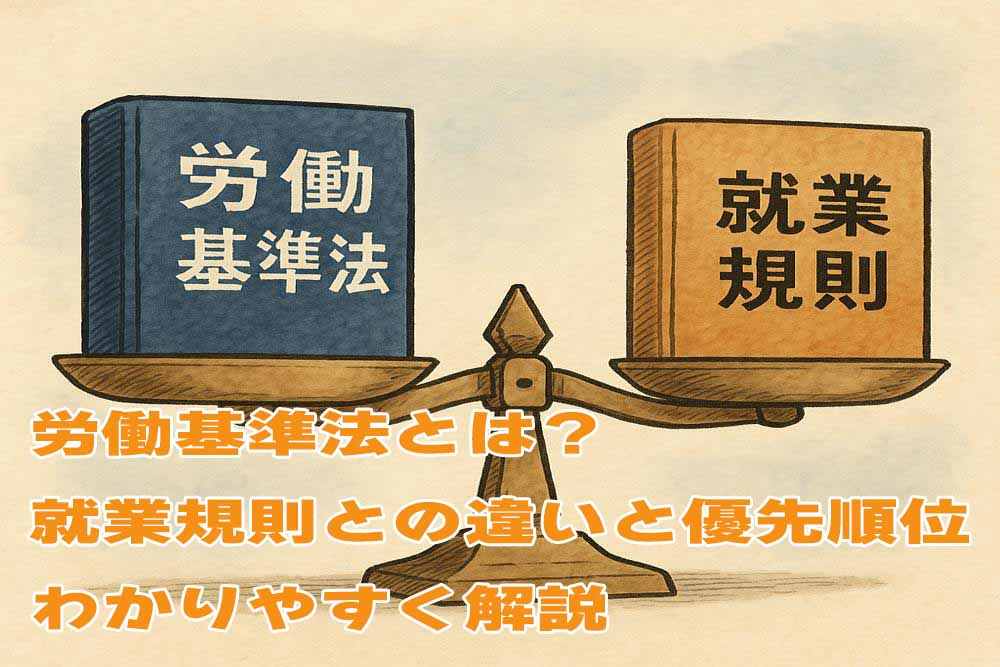
労働トラブルが起こる背景には、「何が正しいのか」を知らないまま働いている現実がある。労働基準法は、すべての労働者の権利を守る“最低限のルール”であり、企業の就業規則もその枠内で運用されなければならない。
この記事では、「労働基準法とは何か?」という初歩的な疑問に答えるとともに、就業規則との違い、守らなかった場合のリスク、そして労使間の信頼構築に向けた理解の在り方を分かりやすく整理する。
労働基準法とは?――働くすべての人を守る“最低ライン”の法律
労働基準法(昭和22年法律第49号)は、労働者が人間らしく働ける環境を保障するために制定された法律である。内容は労働時間、休憩、休日、有給休暇、賃金、解雇など、労働条件の基本を定めている。
この法律の特徴は、「最低基準」であることにある。つまり、企業がどれほど自由に就業規則を定めたとしても、労働基準法の水準を下回る内容は一切認められない。たとえ労使の間で合意があっても、その合意が法律に反していれば無効とされる。
就業規則とは?――会社ごとのルールだが、法の枠内で
就業規則とは、企業が労働者に向けて定める社内のルールであり、労働条件や服務規律、懲戒などが記されている。常時10人以上の労働者が働く事業場では作成と届け出が義務付けられており、全従業員に周知する必要がある。
就業規則で定められる内容は企業ごとに異なるが、その中身はすべて労働基準法の定める最低基準を満たしていなければならない。この順序関係は次のように整理されている。
■ 労働ルールの優先順位(高い順):
- 法令(労働基準法など)
- 労働協約(労働組合と企業との合意)
- 就業規則(企業が定めるルール)
- 労働契約(個々の雇用契約)
具体例で知る優先関係――退職や有給休暇、休憩時間の扱い
たとえば、就業規則に「退職は1か月前に申し出ること」と書かれていても、民法では「2週間前の通知で退職が成立する」と規定されている。この場合は民法の方が優先され、企業側はこれを拒否できない。
また、労働基準法で定める有給休暇は「入社6か月後に10日」。これに対し、就業規則で「8日」としていた場合、その定めは無効とされる。一方で「15日」とすることは、基準を上回っているため認められる。
労働時間・休憩時間は就業規則の「絶対記載事項」
就業規則には、労働時間や休憩時間を必ず明記する義務がある。これは「絶対的記載事項」と呼ばれ、明記されていなければ就業規則としての効力を持たない。
たとえば次のような規定が必要とされる。
- 「1日の所定労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間以内とする」
- 「休憩時間は正午から午後1時までの1時間とする」
- 「始業:午前9時 終業:午後6時」
また、労働基準法では6時間超の勤務で45分、8時間超では1時間の休憩を義務付けている。休憩は労働時間の「途中」に与える必要があり、業務の開始前や終了後にまとめて取らせることは法違反にあたる。
「労働者」と「使用者」 法的な立場の違いとは?
■ 労働者=守られる立場
労働者とは、企業に雇用され、指揮命令を受けて働き、賃金を得るすべての人を指す。正社員、パート、アルバイトなど名称にかかわらず、実態により法律で保護される。
■ 使用者=ルールを守らせる立場
使用者とは、企業経営者や労務管理者など、労働条件の決定・指示を行う者を指す。使用者には、就業規則の作成、労働条件の明示、労働時間の管理など、多くの義務が課されている。
使用者がこれらの義務を怠った場合、労働基準監督署の是正勧告や、刑事罰、民事訴訟による責任追及に発展することもある。
違反した場合はどうなる? 労働者と企業それぞれのリスク
■ 労働者側の違反:懲戒処分の可能性
労働者が就業規則を破った場合、たとえば遅刻や無断欠勤、服装規定違反などがあれば、懲戒処分の対象となる可能性がある。ただし、処分は就業規則に明確に記されている必要があり、過度な処分や事前の周知がない場合は無効とされるおそれがある。
■ 企業側の違反:是正勧告や法的責任も
企業が労働基準法や就業規則を守っていない場合、労働者は労働基準監督署に申告することができる。監督署は調査を行い、違反が認められれば是正勧告を出す。
是正勧告に法的強制力はないが、悪質な場合には刑事処分や損害賠償請求の対象になることもある。企業にとっても、法令違反は大きなリスクである。
「知らなかった」では済まされない労働ルールの基本
労働基準法は、働く人すべてにとっての“憲法”ともいえる存在である。この法律は、「誰かが守ってくれる」のではなく、自ら知り、自らを守るための知識として身につけておくべきものである。
企業はルールを守る義務があり、労働者もまた、自身の権利と義務を理解し、必要なときに正しく主張する力が求められる。
「働きやすさ」は制度と意識の両方から生まれる。
就業規則と労働基準法の正しい理解が、職場における信頼の土台となる。