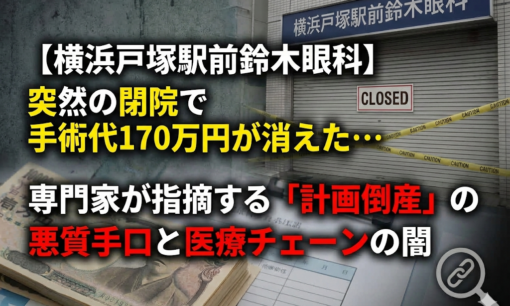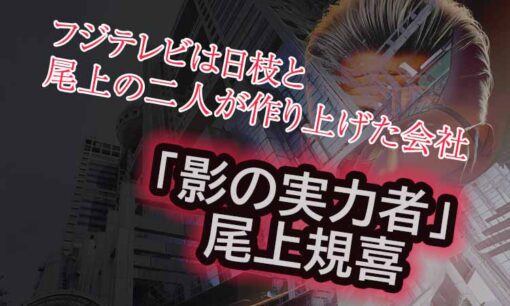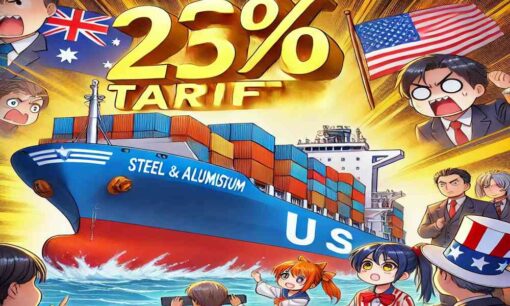2月23日放送のテレビ朝日系情報番組『グッド!モーニング』で取り上げられた電気代高騰の問題が、SNS上で大きな話題となっている。番組の報道を受けて、家庭や産業における深刻な影響が改めて浮き彫りとなり、多くの視聴者がその実態に衝撃を受けた。
光熱費10万円超えの衝撃
夜の帳が下りたリビング。照明は暗く落とされ、家族の顔はぼんやりとした影の中に浮かぶ。埼玉県八潮市の6人家族は、かすかな明かりの中でひっそりと過ごしていた。ふと届いた電力会社からの請求書。封を開けた瞬間、家主の手は震えた。そこに記されていたのは12万7248円という数字――まるで家賃の請求書でも届いたかのような衝撃。
「これは詐欺かと思いましたよ。まさか、ここまで上がるなんて」
昨年の同じ月には8万2875円。それでも決して安くはない。しかし、わずか一年で1.5倍の負担に膨れ上がった。寒波が列島を襲うこの時期、暖房を止めるわけにはいかない。それでも次回の請求額が15万円に達するのではと、不安は募るばかりだ。
電気代12万円超――寒さの中で節電を強いられる生活
この家庭はオール電化の家に暮らしている。家族全員が協力して節電に励むものの、その対策も限界に近い。「昼間は子どもがいないので、電気は最小限に抑えています」。暗い部屋の中で過ごす日々は、まるで生活の質そのものが削られているかのようだ。
その悲鳴は、北の大地・北海道でも聞こえてくる。後志地方に住む3人家族の家主も、請求書に記された12万3158円という数字に思わずため息を漏らした。
「まさか、ここまでとは思わなかった。うっかりしていたわけじゃない、しまった、という感覚です」
昨年は9万6175円だった請求額が、一気に2万6000円以上も跳ね上がった。節電のためにコンセントを抜くといった小さな努力では、到底追いつかない現実がそこにある。家主は「このままならオール電化をやめ、暖房設備そのものを変えるしかない」と語る。生活の根幹を見直さざるを得ない状況に追い込まれている。
生産現場を襲う危機――養豚業者が語る深刻な現実
さらに、電気代高騰の影響は家庭にとどまらない。ある養豚場では、先月届いた請求書に450万円という驚愕の金額が記されていた。そのうち約100万円は豚を生かすためのヒーター代。しかし、残りの大部分は糞の発酵や浄化槽の運用にかかる電気代だ。
「20年前に義務化された設備とはいえ、これほどのコスト上昇は想定外です。うちは相場で取引しているため、コストがそのまま手取りに反映されるわけではありません。このままだと、生産者は次々と行き詰まるでしょう」
生産者は、国産豚肉の自給率が約4割である現状を懸念している。コスト増が続けば、国産食料の供給にも深刻な影響が及ぶことは避けられない。
政府補助縮小で負担増――識者が警鐘を鳴らす
現在、政府は1キロワットアワーあたり2.5円の補助金を支給しているが、3月からは1.3円に縮小される見込みだ。これにより、来月以降の電気代がさらに上昇することが懸念されている。
RAUL株式会社代表取締役の江田健二氏は、「契約容量の見直しや、老朽化した設備の更新、太陽光発電などの導入を検討すべき」と指摘。一方、FP(ファイナンシャルプランナー)である不破雷蔵氏は、電気料金の単価だけでなく消費電力量にも注目すべきだと語る。
「冷暖房機器の設置状況や気候によって消費電力は大きく変動します。埼玉県の電気料金単価の上昇幅を考慮すると、去年に比べて約**6.5%から17.8%**の増加が見込まれます。利用状況を再確認することが大切です」
SNSでも怒りと疑問の声――「企業と政府の透明性が問われている」
SNS上では、国民の怒りと疑問の声が噴出している。ある投稿では、ウクライナ情勢による値上げ申請に対し、電力会社が過去最高益を計上したことに触れ、「政府と企業の利益構造に不透明感がある」と批判する意見が多く見られた。
また、「オール電化の節電対策が進んでいない」「再生可能エネルギー税の廃止を求める」といった現実的な対策を求める声も上がっている。さらに、電力会社を公共インフラと見なすか、民間企業の経済活動として扱うのか、政府の明確な方針を求める声も根強い。
一方、テレビ番組で紹介された家庭の電気代についてはさすがに使い方の方がおかしいだろうという冷静なつっこみも多い。
高騰する電気代――解決策は見えず、家計と産業を直撃する深刻な現実
電気代の高騰は、家庭や生産現場に大きな打撃を与えている。政府補助の縮小が目前に迫る中、節電対策だけでは解決できない課題が浮き彫りとなった。今後、政府と企業がどのように対応していくのか――国民の不安は、まだ消える気配がない。