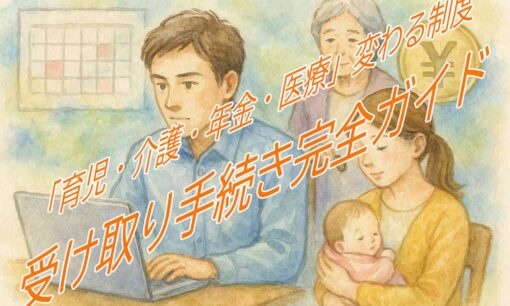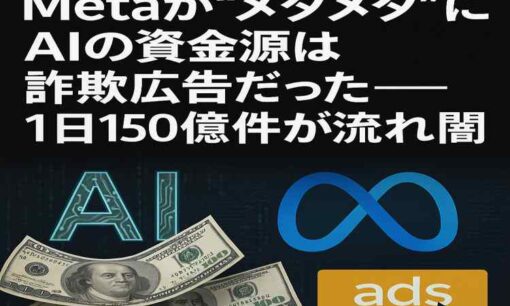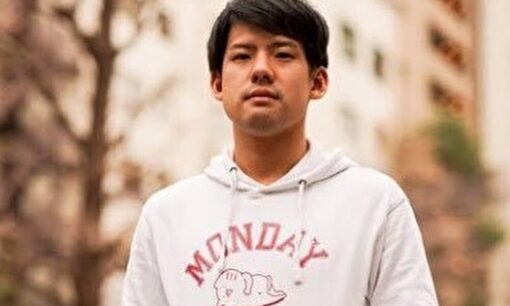花粉症の本格シーズン到来
3月上旬にピーク2月25日(火)以降、スギ花粉の飛散が関東や西日本で急増し、3月上旬にはピークを迎える見込みだ。日本気象協会によると、東京都心では来週後半に「多い」、静岡では「非常に多い」レベルの飛散が予想されている。
例年にない飛散の動き、影響を受ける地域は?
今シーズン、東京都内では1月8日にスギ花粉の飛散が確認され、1985年の調査開始以来、最も早い記録となった。しかし、その後2月中旬まで強い寒波が続き、飛散量は低いままだった。結果として、飛散開始から「やや多い」ランクに達するまでに40日間を要し、2001年以来最も遅いペースとなっている。
影響を受ける地域は関東地方全域、東海地方、西日本を中心に広がっている。特に関東地方が主な影響を受ける理由として、スギの植林が多く行われたことに加え、都市部の大気汚染の影響が考えられる。自動車の排気ガスやPM2.5が花粉と結びつきやすく、アレルギー症状を悪化させる要因となっている。また、関東は風が強く、山間部から都市部へ花粉が運ばれやすいことも一因である。特に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などの都市部では飛散量が急増する見込みであり、静岡県では「非常に多い」レベルの飛散が予想されている。関西では大阪府や京都府、兵庫県でも影響が顕著になるとみられる。
3連休明けの25日以降、寒波が撤退し、一気に気温が上昇することで、スギ花粉の飛散が本格化する見込みだ。東京都心では最高気温が17℃程度まで上がる日もあり、気温の上昇とともに花粉の飛散量も急増すると予測されている。
花粉症患者数の増加傾向
花粉症患者数は年々増加傾向にある。日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会の調査によると、1998年の時点で花粉症全体の有病率は19.6%、スギ花粉症は16.2%だった。しかし2008年には花粉症全体で29.8%、スギ花粉症で26.5%、さらに2019年には花粉症全体で42.5%、スギ花粉症で38.8%に達し、約10年ごとに10ポイント程度増加している。
東京都の調査では、1983年から1987年の時点でスギ花粉症の推定有病率は約8.9%だったが、2016年には約49.1%に上昇している。特に都市部ではスギやヒノキの植林による花粉の増加や、大気汚染などの環境要因が影響していると考えられる。
花粉症患者数増加の背景
花粉症患者の増加には複数の要因が関係している。戦後の植林政策によりスギやヒノキの人工林が増えたことが、花粉量の増加につながっている。特に、戦後に植えられたスギが成熟し、大量の花粉を放出するようになったことが影響している。また、大気汚染も要因の一つとされており、自動車の排気ガスやPM2.5などが花粉と結合することで、アレルギー症状を引き起こしやすくしている。
都市部では生活環境の変化も関係している。住宅の高気密化やエアコンの普及により、外部の花粉が室内に入り込みやすくなり、長時間にわたり花粉にさらされることで症状が悪化しやすくなっている。さらに、食生活の変化やストレスなどもアレルギー体質の人を増やしている要因として指摘されている。
花粉シーズンの到来で求められる対策
気温の上昇は春の訪れを感じさせるが、花粉症の方にとっては症状の悪化が懸念される。特に、飛散量が「多い」日が続くと、外出時のくしゃみや鼻水、目のかゆみなどに悩まされる人が増えるだろう。
花粉症対策としては、マスクや眼鏡を着用し、室内の換気を控えめにすることが推奨される。洗濯物を部屋干しにすることも効果的だ。また、空気清浄機を活用し、室内の空気を清潔に保つことも有効とされる。症状がひどい場合は、医療機関で相談し、適切な薬を処方してもらうことが望ましい。
今後の見通しと注意点
3月上旬には、東京や名古屋、大阪など広い範囲でスギ花粉のピークを迎えると予想されている。ピーク期間は10日間から1か月程度続く見込みだ。
花粉症の症状が重い人は、早めに病院で診察を受け、適切な治療を始めることが重要だ。また、日々の天気予報を確認し、飛散量が多い日は外出を控えるなどの工夫も求められる。
まとめ
3連休明けからスギ花粉の飛散が急増し、関東や西日本で3月上旬にピークを迎える。寒波の影響で今シーズンの飛散は例年とは異なる動きを見せているが、今後は本格的な花粉シーズンに突入する。花粉症の患者数は長期的に増加傾向にあり、その背景には戦後の植林政策や大気汚染、生活環境の変化がある。症状の悪化を防ぐためにも、早めの対策が不可欠だ。