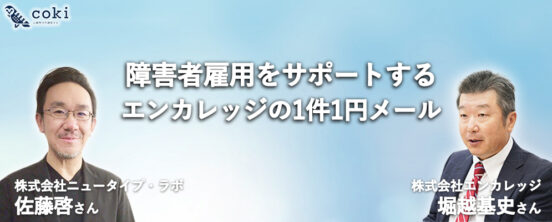師走の郵便局に、かつてのような慌ただしさはない。2025年12月15日、2026年用年賀はがきの受付が始まったが、カウンター前に列を作る人の姿はまばらだった。紙の年賀状が当たり前だった時代は、静かに終わりを迎えつつある。
帝国データバンクが実施した「年賀状じまい」に関する企業アンケート(2025年12月)によると、すでに年賀状をやめた企業は58.1%に達し、初めて半数を超えた。企業の年末年始の挨拶文化が、明確な転換点を迎えている。
「もう出していない」企業が過半数に 1年で8.7ポイント増
調査では、「すでに年賀状じまいをした」と回答した企業が58.1%だった。内訳を見ると、「2023年1月分以前にやめた」が22.0%、「2024年1月分から」が15.4%、「2025年1月分から」が10.4%と、段階的に増えてきた様子が浮かぶ。
さらに、「2026年(来年)1月分からやめる」企業も10.3%あり、年賀状じまいを実施・予定している企業は実質7割近い計算になる。前年調査では49.4%だったため、わずか1年で8.7ポイント上昇した。
背景には、郵便料金の値上げに伴う年賀はがきの価格上昇(85円)に加え、印刷・宛名管理・手書きコメントといった年末業務の負担感がある。帝国データバンクは「費用削減だけでなく、事務作業の効率化やペーパーレス志向も後押ししている」と分析している。
2026年に年賀状を送る企業は29.1% 「送る側」が少数派に
一方で、「年賀状じまいはしない」と回答した企業は29.0%だった。「一度やめたが、2026年1月分から再開する」企業は0.1%にとどまり、2026年に年賀状を送る企業は29.1%と3割を下回った。
それでも、年賀状を続ける企業には明確な理由がある。慣習としての意味合いに加え、「年に一度の接点として、関係の浅い取引先に忘れられないため」「年賀状をやめる企業が増えたからこそ、逆に目立つ」といった声が聞かれた。年賀状を単なる儀礼ではなく、営業ツールの一つとして再定義する動きも見られる。
紙からデジタル、そして“別の贈り物”へ
年賀状をやめた企業の中には、単に挨拶を省略したわけではない例もある。カレンダーやクリスマスカードの送付に切り替えたり、メールやSNS、デジタル年賀状で新年の挨拶を済ませたりするケースもあった。
「取引先から年賀状じまいの連絡が来た」「業界全体が縮小している」といった“空気”も、企業の判断を後押ししている。形骸化した慣習を見直し、別の形で関係性を保とうとする姿勢がうかがえる。
個人にも広がる「年賀状じまい」 文化は消えるのか
この流れは企業に限らない。毎日新聞は、年賀状じまいについて専門家の見解を紹介し、「年賀状は送りたい人が送るものに変わっている」と指摘する。義務感やプレッシャーから解放される一方で、「大切な人にだけ送る」という原点回帰の兆しもあるという。
デイリー新潮では、「年賀状じまいをわざわざ宣言する必要はあるのか」との問題提起もなされ、手間やストレスに見合わない文化として距離を置く層の存在が浮き彫りになった。
年賀状は“終わる”のか、“変わる”のか
帝国データバンクの調査結果は、年賀状が急速に減っている現実を示している。ただ、その一方で、完全に消えるのではなく、「送る人を選ぶ文化」へと姿を変えつつあるようにも見える。
コストと効率を重視する企業が年賀状じまいを進める一方で、あえて紙を選び、年に一度の挨拶に価値を見いだす企業も残る。年賀状は今、「やめるか続けるか」ではなく、「どう使うか」を問われている。