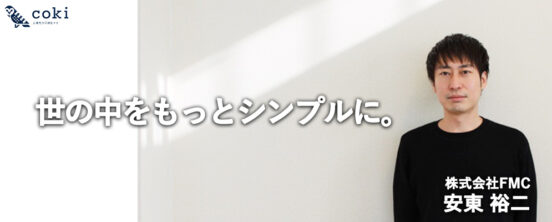日本でクマによる人的被害が急増する一方、同じ緊張感は国境を越えて広がりつつある。米国や中国は渡航者に注意喚起を行い、欧州では駆除ルールが大きく転換されている。
都市近郊での目撃が相次ぐ日本、農村部で襲撃が増える欧州、そして野生動物の生活圏と人間社会が交錯する世界の現場では、静かだが確実な変化が進んでいる。
米国・中国が相次いで注意喚起 日本で高まる緊張感
日本を訪れる外国人への警戒が強まっている。米国は在日大使館を通じて、北海道や東北地方でクマの出没や襲撃が増加しているとして、日本に滞在する自国民に注意を促した。札幌市内の公園ではクマが目撃され、園内の一部が閉鎖される事態となり、観光客の往来が多いエリアでも警戒が続く。
中国も独自に注意情報を発信し、訪日旅行者に対し、野生動物の出没情報を事前に確認し、単独行動を避けるよう求めている。都市部に近い地域でもイノシシやクマの目撃が増えている点を挙げ、クマよけスプレーの携帯を推奨するなど、明確な対策を促す姿勢が目立つ。
夕暮れの遊歩道では、観光客が地図アプリを見つめる背後で、木の影が揺れたという報告もある。過去には考えられなかった場所で、人とクマの動線が重なり始めている。
ロシア・トルコでも深刻化 生活圏に踏み込むクマたち
世界の各地でも同様の緊張が高まっている。ロシア極東の町では、駐車場を歩く男性が背後から接近したクマに襲われ、辛うじて車内に逃げ込む映像が撮影された。そのクマは直前に高齢女性を襲っており、後に駆除された。
トルコでは、農家が育てるレタス畑が一晩で食い荒らされ、破壊されたビニールハウスの残骸が散乱する光景が相次ぐ。車が損傷するケースも増え、監視カメラには夜闇を悠然と歩く大型個体の姿が残されている。
背景には、森林伐採や都市化で縮小する生息地があり、人の生活圏とクマの行動範囲が重なる機会が増えている。野生動物が本来の餌場を失い、人里へと降りざるを得なくなる構図は国や地域を問わず共通している。
欧州で揺れる「保護と安全」 射殺容認の方向へ
欧州でも深刻な転換点が訪れている。クマによる人的被害が増加したルーマニアでは、従来の「追い払い」や「麻酔による捕獲」を優先する仕組みを見直し、人間に危害を与える恐れがある場合には即時に射殺できる体制へと移行した。過去20年で多数の死傷者が出たことが背景にある。
同じく東欧の国では、国境付近でのクマの駆除が増えており、隣国からは「保護区域の個体まで脅かしている」との懸念が示されている。クマは国境を理解しないため、保護政策が国をまたいで干渉し合う難しさが表面化している。
欧州山岳地帯では、登山道に糞が残され、住宅地近くで親子連れのクマが目撃される例もある。「いま攻め込んでいるのはどちらなのか」と感じさせるほど、双方の生活圏は複雑に入り組んでいる。
日本の“高密度地帯”という構造的問題 専門家の見立て
日本のクマ問題には、世界でも特異な側面がある。生息密度が高く、山林と市街地の距離が非常に短いことだ。専門家は、日本は偶発的な遭遇が起きやすい地形と生活習慣を抱えていると指摘する。早朝にゴミを出す文化や、住宅街すぐ近くまで迫る森林など、人間の行動と野生動物の行動時間帯が重なりやすい。
薄暗い住宅街の路地で破れたゴミ袋が放置され、残飯の匂いが広がれば、そこはクマにとって格好の餌場になる。たまたま居合わせた住民が攻撃される構図は、決して特別なシナリオではなくなりつつある。
専門家は、誘因となる物を徹底的に管理しない限り、住宅地への接近は続くと分析する。都市近郊での遭遇リスクが増す理由は、自然側ではなく人間側の生活ルールにも深く根付いている。
“国境を越える課題”としてのクマ対策 世界が向かう方向性
世界の状況を俯瞰すると、多くの国が「保護と安全」の両立を模索しながら、それぞれ異なる道を歩み始めている。欧州では駆除枠の拡大や即時射殺が議論の中心にあり、北米やアジアでは観光客への周知や生活圏の整理が進む。一方、日本が直面しているのは、市街地との近さに起因する根本的な構造であり、単純な駆除や保護の議論だけでは解決が難しい。
クマが本来の生息地を離れざるを得なくなる背景には、人間側の環境変化がある。世界各国が示す対策の共通点は、自然環境・生活環境・情報管理を一体で扱う姿勢だ。国際的に拡大するクマ被害は、もはや「一国だけの問題」ではない。
山から都市へ、そして国境を越えて。クマの動きは、今、人間社会の警戒網を試している。