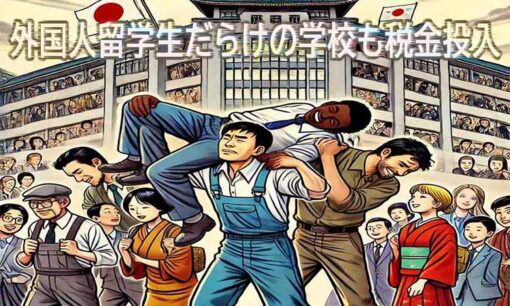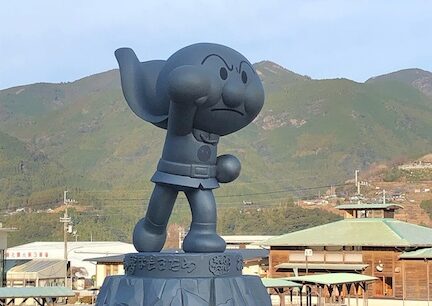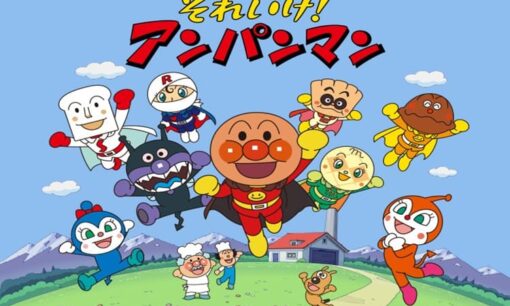TBSが放つ日曜劇場『VIVANT』続編で、ついに「生成AI映像」が地上波ドラマ本編に導入される。
発表の場はGoogle Cloud主催のAI Agent Summit ’25 Fall。主演・堺雅人をはじめ豪華キャストが再集結する一方で、AIがどのように“リアルな映像世界”を支えるのか、業界の注目が集まっている。
ドラマ制作の常識を変える挑戦の舞台裏を追う。
TBSが挑む“地上波初”の試み
10月30日に、都内で開催されたGoogle Cloud主催のイベント「AI Agent Summit ’25 Fall」。
壇上に立ったのは、TBS『VIVANT』のプロデューサー・飯田和孝氏と、マーケティング&データ戦略局の宮崎慶太氏だった。
二人が語ったのは、「Veo 3」によるAI生成映像を地上波本編に採用するという、テレビ業界でも前例のない挑戦だった。
TBSが発足させた社内AI活用プロジェクトの一環として進められるこの試みは、単なる実験ではない。
制作チームのリソースを最大限に生かし、作業をAIが担い、人が創造に専念するという新たな制作体制の実現を目指している。
これまで撮ることが前提だったドラマ制作が、ついに創ることへと進化しようとしているのだ。
リアルを超えるリアリティをどう描くか
前作『VIVANT』は、モンゴルの大地を舞台にした圧倒的なロケ映像が視聴者を驚かせた。
風を切るラクダの足音、砂塵を舞い上げるトラックの爆音、俳優の汗にまで映り込む本物の光。
そのリアルこそが作品の象徴だった。
続編では、そこに生成AI映像が加わる。
Veo 3は、文章から動画を自動生成するGoogleのメディアAIで、光の角度やカメラワーク、人物の表情に至るまで再現できる。
これにより、過酷な環境でのロケや危険なスタント、広大な群衆シーンの再現が格段に効率化される。
ただし、視聴者の多くが気にするのは、「どこからがAIなのか?」。
CGのように明確な区切りがないぶん、リアルとフェイクの境界が曖昧になる。
この境界の消失こそ、AI映像時代の新たなテーマと言える。
制作現場をどう変えるのか
TBSがVeo 3を採用する目的は、単に映像を美しくするためではない。
膨大なルーティンワークをAIが担うことで、脚本・演出・演技といった創造の核心に時間を割けるようにすることだ。
AIが背景や群衆、空撮などを生成し、クリエイターは物語に集中する。
この変化は、俳優業やスタッフ構成にも波及する可能性がある。
特に、脇役やエキストラの出番が減少することで、俳優育成の現場そのものが再構築されるかもしれない。
一方で、AIによる生成映像の素材権利や著作権といった新たな課題も浮上する。
映像制作が人間とAIの協働に移行する中で、倫理や契約のあり方も見直されていくだろう。
「AI×人間」の共創が生むドラマの未来
コメント欄では、期待と不安が入り混じっている。
「どこがAIで作られているのか見破りたい」「リアルなVIVANTの世界観が壊れないか心配」。
その一方で、「制作費を抑えつつ新しい映像が見られるのは面白い」「俳優とAIの共演が楽しみ」という前向きな声も多い。『VIVANT』は前作でも、海外ロケ・文化描写・政治的リアリズムなど、地上波の限界を超えたスケールを実現した。
続編では、AIが描くリアリティという新たな実験場となる。
この挑戦が成功すれば、日本のドラマ制作の構造そのものを塗り替えることになるだろう。