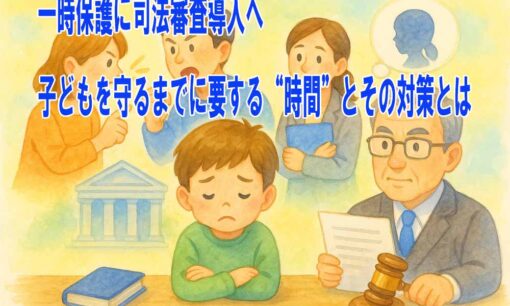世界文化遺産・富士山。その荘厳な姿の陰で、異臭を放つ現実が広がっている。森の中や道路脇に投げ捨てられた「尿入りペットボトル」──通称“しょんボトル”。清掃活動の現場にはモラルの問題を超えた、社会構造のひずみが横たわっていた。富士山の美を汚すものは、一部の心ない人間ではなく、私たちが生きる便利社会そのものなのかもしれない。
清掃現場に広がる異様な光景
10月上旬、環境NPO「富士山クラブ」が主催する清掃活動に約60人が参加した。富士河口湖町の富士山世界遺産センターを出発し、国道139号線沿いを歩きながらごみを拾う。最初は軽い気持ちで参加した人々も、すぐに表情を失った。
草むらの中には、コーヒー飲料やスポーツドリンクのラベルが貼られたペットボトルが多数転がっていた。中には紅茶色の液体がぎっしり詰まっている。スタッフが静かに告げた。
「これが、尿入りのボトルです」
開けた瞬間、強烈なアンモニア臭が鼻を突き、胃がひっくり返るような不快感に襲われた。ペットボトルの中で尿が発酵し、ガスがたまることもあるという。自然の中に、人工的で不衛生な「異物」が静かに積み重なっている。
“人目のない道”が捨て場に
発見が相次ぐのは、富士吉田IC付近や青木ヶ原樹海、朝霧高原など、人通りの少ない区間だ。富士山クラブの荒井みずき氏は「ドライバーが人目を避けて捨てている」と話す。
清掃活動の1時間で回収されたごみは約60キロ。そのうち約30本が尿入りペットボトルだった。富士山麓全体に換算すれば、その数はおそらく数千本に及ぶ。誰かが、見えない場所で、静かに自然を汚している。
「観光地の外れだから、見られないと思っているのでしょう。でも、私たちは拾っています。その現実を知ってほしい」
荒井氏の声は、怒りよりも哀しみに近かった。
コロナ禍で急増 “加害者”の実像
2020年、観光客が消えた富士山で、尿入りボトルは逆に増えた。外国人観光客のモラルではなく、問題は国内にあった。物流を担うトラックドライバーだ。
コロナ禍で道の駅やコンビニのトイレが閉鎖され、休憩施設がほとんど使えなくなった。数百キロを移動する運転手たちは、行き場を失った。ボトルに排尿し、人目のない林道や側道に捨てる──。その行為は違法だが、同時に「選択肢のない行為」でもあった。
「コロナのころは、見つけたペットボトルの7割が尿入りでした。外国人も観光客もいないのに、です」と荒井氏。
富士山の清浄な森が、社会インフラの欠陥を映す鏡となった。
自治体の処理対応に温度差
尿入りペットボトルをどう処理するか。これが清掃活動を悩ませる最大の課題だ。山梨県側の自治体では、尿入りでも可燃ごみとして処理できる。しかし静岡県側では「液体が入ったものは危険物扱い」として受け入れを拒否する自治体がある。
結果として、清掃活動では“その場で尿を捨ててからボトルだけ持ち帰る”しかないことも多い。だが、森の中に尿を撒けば土壌や水質汚染の懸念が残る。つまり、どの選択も「環境にやさしくない」のだ。
さらに、ボランティアが他人の尿を処理する行為そのものが精神的な負担を伴う。
「家に持ち帰ってトイレに流してから捨ててくださいなんて言えません。誰も来なくなります」
荒井氏は苦笑しながらも、制度の矛盾に声を震わせた。
県境をまたぐごみの扱いが統一されていない日本の現実が、世界遺産の保全を阻んでいる。
富士山の威容に忍び寄る“文化の汚染”
富士山クラブが1998年に活動を始めた当初、撤去対象はタイヤや家電などの産業廃棄物だった。だが世界遺産登録(2013年)を境に、一般ごみのポイ捨てが主流となった。
観光客の増加と比例するように、道路沿いには空き缶、レジ袋、そして尿入りペットボトル。富士山の裾野は、いつしか「便利社会の残骸」を映す風景になっていた。
自然と調和するはずの山が、欲望と効率の象徴であるプラスチックに覆われている。
「文化遺産」は、その文化の成熟度も問われる。今の富士山は、人間の未熟さを映す鏡でしかない。
荒井氏は言う。
「私たちが守りたいのは、景観だけではなく“心の清浄さ”です」
対策は「モラル啓発」だけでは足りない
「ポイ捨てをやめましょう」と訴えるだけでは何も変わらない。必要なのは“構造的対策”だ。
トラックドライバーが安心して利用できるトイレ・ごみ処理施設を、幹線道路沿いに増設すること。駐車しやすいスペースを整備し、捨てる理由をなくすことが第一歩となる。
次に、投棄行為への罰則強化だ。監視カメラやドライブレコーダー映像を活用した摘発も現実的な手段である。
さらに、処理ガイドラインを全国で統一し、液体入り容器の専用処理施設の整備を検討すべきだ。
「富士山を汚した人を責めるより、汚さずに済む社会を作らなければいけない」
荒井氏の言葉は、単なる道徳論ではない。社会の設計そのものを見直すべきだという訴えだ。
終わりに:富士山が沈黙のまま泣いている
荘厳な姿で私たちを見下ろす富士山。その静けさの奥で、自然が泣いている。人間の都合と怠惰が生んだ“しょんボトル”は、やがて風化してマイクロプラスチックとなり、再び私たちの生活に戻ってくる。
世界遺産とは、過去を誇るための称号ではない。未来に何を残せるかを問う鏡だ。
その足元で、腐臭を放つペットボトルが転がっている――。
この現実を前に、私たちはどんな顔で富士山を見上げることができるだろうか。