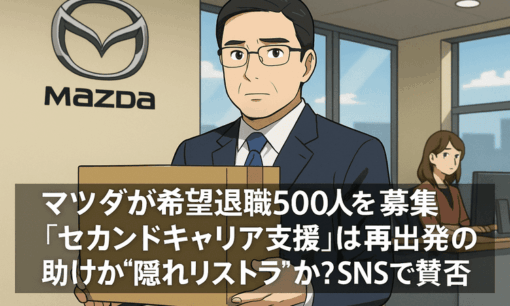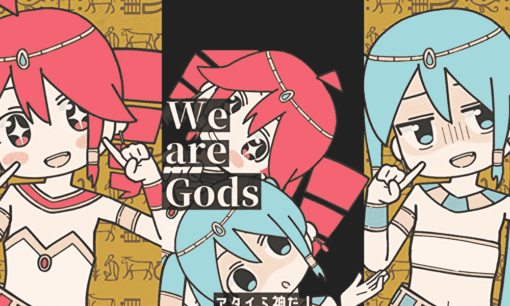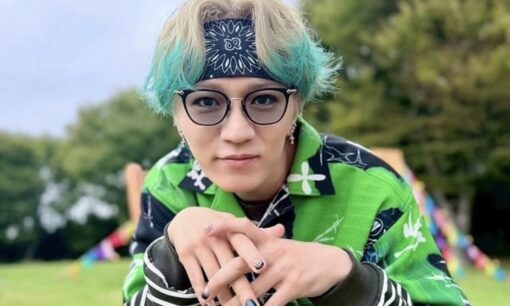京都市の人気ラーメンチェーン「天下一品」で、看板商品にゴキブリの死骸が混入していた事案を受け、運営会社「天一食品商事」は新京極三条店と、同じオーナーが経営していた河原町三条店の2店舗を閉店すると9月30日に発表した。いずれも看板が撤去され、公式サイトから姿を消している。
本件は、単なる衛生事故以上に、フランチャイズ運営体制や危機対応の不備を露呈した出来事である。なお、新京極三条店は2015年6月29日に開店しており、閉店時点でおよそ10年3か月での閉店となった。河原町三条店は移転オープンを2021年4月27日とする情報があり、もしそれを起点とするならば閉店まで約4年半に満たない運営期間ということになる。
ゴキブリ混入発覚と店舗閉鎖
事件が起きたのは8月24日。新京極三条店で20代女性が注文した「こってりラーメン」のスープに、ゴキブリの死骸が混入していた。女性はすぐに異物に気づき従業員に申し出たが、健康被害は確認されなかった。店側は返金を提示したが、女性はこれを辞退したとされる。問題が発覚した以上、直ちに営業を停止し保健所へ報告すべき状況だったが、店舗は9月2日まで通常営業を続けていた。報告が行われたのは9月3日、発覚から10日も経過していた。
対応の遅れは消費者に「隠蔽ではないか」との疑念を生じさせ、ブランドの信頼を著しく損ねる結果となった。さらに、同じオーナーが経営する河原町三条店も営業を停止。結局、両店舗はそろって閉店となり、京都市の繁華街から天下一品の看板が消えることとなった。発祥の地での撤退は象徴的であり、企業にとって大きな痛手である。
保健所の調査で判明した衛生管理の甘さ
9月4日、京都市保健所が新京極三条店に立ち入り調査を行った。厨房の衛生状態そのものに重大な欠陥は見られなかったとされるが、害虫駆除に関する記録が一切確認できなかったことが大きな問題となった。食品衛生法では、害虫防除や清掃の実施記録を1年間保存することが義務付けられている。スプレーの散布や粘着シートの設置といった日常的な作業の記録がなければ、再発防止策を立てる根拠すらなく、管理体制が形骸化していたことを意味する。
さらに問題だったのは、混入したゴキブリの死骸そのものがすでに処分されていたことだ。異物の形状や状態は侵入経路や原因を特定する上で重要な証拠となる。それを残さなかったことで、原因究明が困難となり、消費者からは「調査の意思があるのか」と厳しい目が向けられた。
この調査をきっかけに、京都市内の他店舗にも調査が拡大された。その結果、七つの店舗でも同様の記録不備が見つかり、文書での指導が行われた。今回の混入は一店舗の偶発的な事故ではなく、チェーン全体に蔓延する衛生管理の甘さを示す事例として浮かび上がった。
信頼を失った対応の遅れと不透明さ
今回の問題がここまで拡大した背景には、天一食品商事の初動対応の遅れと不透明な情報公開がある。8月24日の発覚から保健所への報告までに10日間を要したことは、危機管理の観点からすれば致命的だ。さらに、異物のサンプルを破棄してしまったことも、調査の真摯さに疑念を抱かせた。
また、発覚後も数日間営業を続けたことで、消費者の間には「利益を優先したのではないか」という疑念が広がった。SNS上では「天下一品にはもう行けない」といった書き込みが相次ぎ、ブランドイメージの低下は瞬く間に拡散した。京都市内という観光客も多い地域でのトラブルは、国内外の来訪者にも波及し、 reputational damage は計り知れない。
同じオーナーが経営していた二つの店舗が同時に閉店に追い込まれたことは、個別の不祥事ではなく、運営体制そのものに問題があったことを裏付けている。保健所の調査によって他店舗でも記録不備が見つかった事実は、フランチャイズチェーンとしての管理監督が十分でなかったことを示している。
過去の異物混入と業界が抱えるリスク
外食産業では異物混入が繰り返し問題化している。今年1月には牛丼チェーン「すき家」で提供されたみそ汁にネズミの死骸が混入し、全国の店舗が一斉休業に追い込まれた。その後3月にはゴキブリ片の混入も発覚し、短期間での連続トラブルは業界全体を震撼させた。天下一品の今回の件も同様に、ひとつのミスが全国ブランドを揺るがす大事件につながることを改めて示している。
特にフランチャイズ運営では、本部が定めたマニュアルが必ずしも現場で徹底されるとは限らない。人員不足やコスト削減の圧力の中で、衛生管理に割く余力が不足し、記録が後回しにされることは珍しくない。監査が不十分であれば、問題は水面下で放置され、今回のように大きな事件となって初めて表面化する。これはフランチャイズという仕組みが持つ構造的リスクであり、天下一品だけでなく外食業界全体が抱える課題でもある。
再発防止への道筋と課題
今回の閉店劇は、事故対応にとどまらず、企業がどのように信頼を回復するかを問う試金石となっている。天一食品商事が信頼を取り戻すためには、まず徹底的な調査と改善策の公開が欠かせない。第三者機関による監査を定期的に実施し、その結果を公表することで透明性を高めるべきだろう。
また、日常的な衛生管理を記録に残す体制を確立し、従業員教育を強化することが求められる。異物混入のリスクをゼロにすることは難しいが、記録を残し点検を重ねることで、リスクを限りなく低減することは可能だ。さらに、消費者に対する賠償や補償制度を整えることも、信頼回復に不可欠な要素となる。
発祥の地・京都で築いてきたブランドは、長年にわたり「こってり」という唯一無二の味で多くのファンに愛されてきた。しかし今回の不祥事は、その土台を揺るがす大きな打撃となった。天一食品商事がどのような姿勢で再発防止に取り組むか、その真価が問われている。