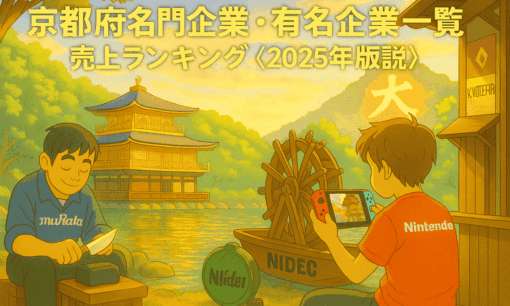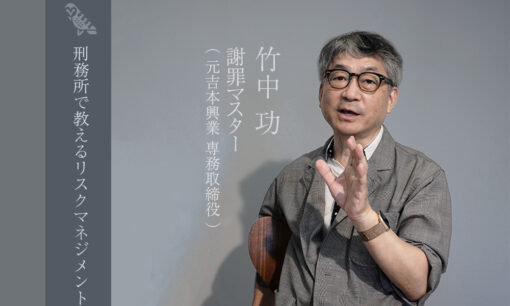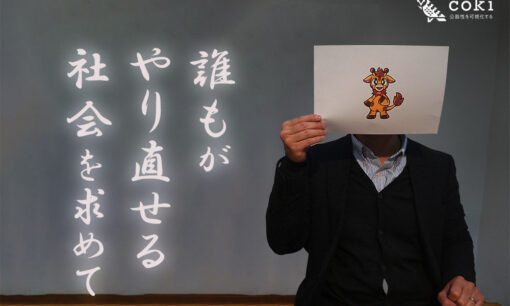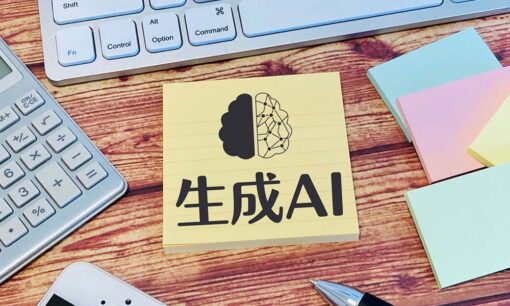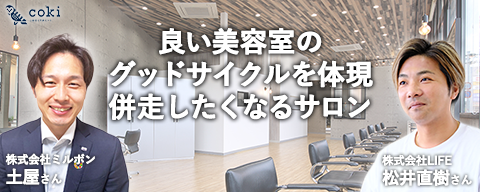「10代の犯罪を減らす」。このシンプルで力強い使命を掲げ、2023年に京都で創業した株式会社一(ICHI INC.)。代表の中馬一登氏は、少年院や刑務所と連携し、刑務作業を単なる労働ではなく「社会につながる経験」へと変える取り組みを続けてきた。そんなICHIが京都刑務所と組んで挑んだのが、法務省主催の「ミッションチャレンジ2025」だ。
9月13日、東京都港区で行われたプレゼンテーションには全国から11の刑事施設が登壇。来場者139人による投票で、京都刑務所の発表は最多得票を集め「フロア大賞」に輝いた。
刑務所の現実 「更生を信じられない」構造

京都刑務所とICHIは、発表の冒頭であえて厳しい現実を突きつけた。「職員も受刑者自身も、更生を信じられない」。職員は日々の業務に意義を見いだせず、受刑者は作業が社会復帰につながらないと感じる。出所後の就職も難しく、再び犯罪に戻ってしまう構造がある。この閉塞感こそ、改革の出発点だった。
そこで両者は、地域企業や伝統産業とつながることで「役立つ実感」を生む仕組みを考案。西陣織や黒谷和紙の担い手不足解消を受刑者が支える「伝統産業プログラム」、企業と商品開発を進める「ブランド企画」、そして起業家精神を学ぶ「起業家育成」。3つの挑戦は、職員と受刑者の意識を同時に変えていく試みだ。
これまで刑務作業で作られるものには、デパートの紙袋や箪笥、お守りなどさまざまなものがあった。なかには府中刑務所のパンなどは美味しいことでも有名であるし、資格の試験問題なども塀の中の印刷工場で刷られると聞く。それでも、こうした作業が直接的に社会復帰後の就労に結び付く事例は少ないだろう。
制度改革の流れと同相
日本では2025年6月1日から新たな「拘禁刑」が導入され、処遇の重点を懲罰から改善更生へ一段とシフトさせる運用が始まった。ながらく言われてきた懲役という言葉さえ使用されなくなったという。従来赤落ちした受刑者は、番号で管理され、担当刑務官のことは「親父さん」とか「担当」などと呼ぶのが当たり前の世界だったのが、大きく変わる端境期にあるのだろう。
法務省の公表文書でも、刑事施設の処遇改善や社会内処遇の充実を指向する流れを強調している。今回の京都刑務所×ICHIの受賞は、こうした制度転換の“現場版”として位置づけられる。
審査員の心をつかんだ言葉
審査員の東京大学教授・熊谷晋一郎氏は「冒頭の“更生を信じていない”というセリフで胸を鷲掴みにされた。更生や社会復帰は創造的なプロセスであり、その力強さが伝わった」と語った。
NPO法人日本ファンドレイジング協会の小川愛氏は「更生を信じたいという気持ちが溢れていた。伝統ある産業から協力を得て丁寧に進めていることが印象的」と評価。
さらにandu ametの鮫島弘子CEOは「刑務所で作ったものを価値あるブランドにすることは大きい。他施設にも波及するだろう」と期待を寄せた。
海外に学ぶ更生のかたち
更生を社会につなげる発想は海外でも成熟している。米国では、受刑者にデジタル技能や就労準備を提供する「The Last Mile(TLM)」が複数州の刑務所で展開されており、教育とキャリア訓練が再犯低減と就業機会の拡大に資するという立脚点を明確にしている。
TLM自身も、教育・職業訓練が再犯抑止と雇用機会に正の影響を与える旨を示す研究蓄積を根拠に、民間パートナーと連携するモデルを採る。数値の断定には慎重を期すべきだが、教育投資が更生の質を押し上げるという方向性は広く共有されている。
シンガポールでは、社会全体で元受刑者の受け入れを促す「Yellow Ribbon Project」が官民連携で進む。内務省系の刊行物やシンガポール矯正庁(SPS)の公表情報では、雇用支援(YRSG)への参加が就業や再犯に有意な改善をもたらす分析が示され、2年再犯率は2019年釈放コホートで20%と、20年前の約44%から大きく低下したとされる。社会のまなざしを変え、就労への橋を架ける取り組みが定着していることがうかがえる。
豪州でも、拘禁中の職業教育・訓練(VET)と釈放後の再犯・就業の関係を検証する研究が重ねられてきた。地域や設計の違いにより効果幅は異なるものの、VET受講が再入所リスクを下げうることや、教育介入が福祉依存の軽減・就業改善に結びつくというエビデンスが蓄積している。
京都刑務所とICHIの取り組みは、こうした海外事例と同様に「スキルの提供」と「社会との接続」を重視するが、日本独自の伝統産業や地域企業を組み込む点にオリジナリティがある。
所長と代表が語る未来
京都刑務所の櫛引唯一郎所長は「最初は更生を信じていないところから始まったが、多くの協力者との議論を通じて希望へと変わった。京都刑務所を社会とつながる場所に進化させたい」と語る。
ICHIの中馬代表も「虐待や家庭内暴力などにより犯罪に追い込まれた子どもたちに選択肢を与えたい。社会の構造を変える挑戦を、多くの仲間と広げていく」と力を込めた。
——刑務所が抱える“更生を信じられない”現実に、京都から挑む若い企業と矯正現場。国内外の成功例とも響き合うこの試みは、社会全体の視線を大きく変える可能性を秘めている。
もともと、刑務所のなかでは勉学もできる環境であり、なかには簿記の資格などを取り、のちに税理士や弁護士などの侍業に入ったものや企業経営者となった者も多い。それでも、こうした例は自らの強い意志と手を差し伸べてくれ見守ってくれる家族がいる者であるケースが多い。
刑務所がきつい環境であることは当たり前のことだが、そのなかでたとえ社会と孤立している者でも願えば、誰もがやり直せるような環境が醸成されているとはいいがたい。
長らく、触法行為を犯した人間は罰としての懲役の意味合いが強く、更生は言葉こそ謳われど現実の運用では重きは置かれてこなかった。それを社会もよしとしたし、多くの見方はいまも変わらないだろう。ただ、やり直しのしやすい社会包摂の効いた社会の方が巡り巡って、再犯率も下がり、誰もが生きやすい社会になるということが、今回を契機に広く伝播していくことにつながればと切に期待している。