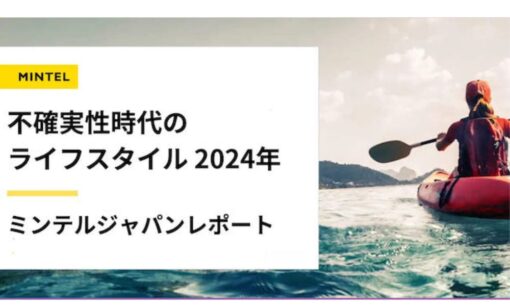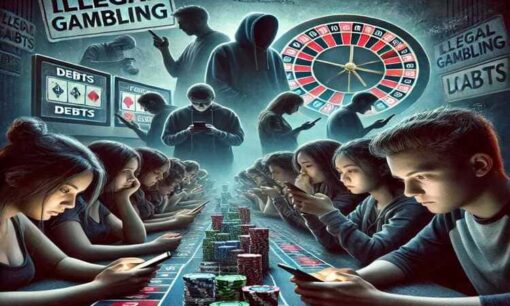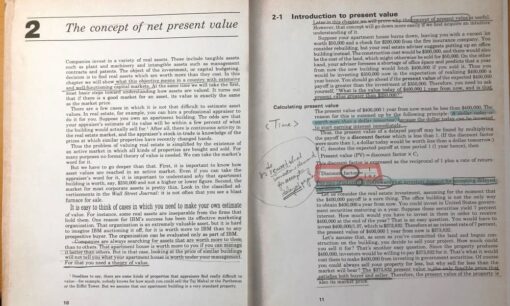アフリカで感染拡大が続くエムポックスの重症型「クレード1」が、日本国内で初めて確認された。厚生労働省によると、アフリカに渡航歴のある20代女性が発疹や発熱の症状を訴え、今月12日に医療機関を受診。
検査の結果、重症化しやすい「クレード1」への感染が確認された。女性の容体は安定しているという。かつて「サル痘」と呼ばれたこの感染症は、天然痘に似た症状を示すことから世界保健機関(WHO)が監視を強めており、国内での初確認は大きな注目を集めている。
厚労省「クレード1」感染を初確認
厚労省によれば、感染が確認されたのは20代女性。アフリカ滞在歴があり、帰国後に発疹や発熱が現れた。症状を訴え医療機関を受診したところ、検査で「エムポックス クレード1」の感染が確認された。
これまで国内で確認されてきた感染は、比較的軽症例が多い「クレード2」であり、クレード1が報告されたのは今回が初めて。厚労省は「現時点で国内の市中感染リスクは高くない」と説明するが、警戒感は広がっている。
エムポックスとはどのような感染症か
エムポックスはポックスウイルス科に属するウイルスが引き起こす人獣共通感染症で、1958年に研究用サルで発見されたことから「サル痘」と名付けられた。しかし主な宿主はげっ歯類で、人への感染は濃厚接触や飛沫、体液との接触を通じて起きる。
潜伏期間は1〜2週間とされ、その後、発熱や頭痛、リンパ節の腫れに続いて発疹が顔や体に広がる。発疹は水ぶくれや膿疱に変化し、かさぶたを経て数週間で治癒することが多い。
WHOは2022年、「サル痘」という名称が差別的と受け止められる可能性を指摘し、現在は「エムポックス」と呼称。日本国内でもこの新名称が用いられている。
クレード1とクレード2の違い
エムポックスには大きく分けて「クレード1」と「クレード2」がある。
「クレード2」は2022年以降に欧米で広がった流行で見られたタイプで、致死率は1%未満。
多くの感染者が軽症で回復した。一方で「クレード1」は病原性が強く、致死率が10%を超える地域も報告されている。コンゴ盆地などで過去に流行した際には、子どもや免疫不全の患者を中心に重症化例が多く見られた。
国立感染症研究所によると、「クレード1」は呼吸器症状や肺炎を併発するケースもあり、稀に脳炎を引き起こす例もあるという。今回、日本でこのタイプが確認されたことは、単なる輸入感染にとどまらず、国内の感染症監視体制を試すことになる。
世界で広がる警戒とワクチン対応
エムポックスは2022年以降、欧米を中心に「クレード2」が拡大した。人から人への持続的な感染が確認され、WHOは国際的な公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)に指定。2023年には指定解除されたが、感染症としての警戒は続いている。
一方、アフリカで猛威を振るっているのは「クレード1」である。現地では医療体制の脆弱さも相まって感染拡大が止まらず、国際社会は危機感を強めている。
予防には天然痘ワクチンが有効とされ、日本でも一部の医療従事者などを対象に接種が始まっている。WHOは「接触者追跡や迅速な診断と隔離が感染拡大防止の鍵」と強調している。
国内のリスクと社会の備え
厚労省は「市中感染のリスクは低い」とする一方、空港検疫や医療機関への注意喚起を強化。発疹や発熱がある患者には、必ず海外渡航歴を確認するよう求めている。
感染症専門家は「新型コロナで学んだ最大の教訓は、初期対応の遅れが拡大を招くことだ。小規模の輸入例であっても情報共有を怠ってはならない」と警告する。
市民にとっては、過度な不安を抱かず、冷静に情報を得る姿勢が重要だ。症状がある場合は自己判断せず医療機関に相談すること、また誤情報や差別的な言説に惑わされないことが求められる。
感染症は国境を越える
新型コロナウイルスの世界的流行からまだ数年。今度はエムポックスの重症型が日本に持ち込まれた。航空路線が発達した現代では、感染症は瞬く間に国境を越える。
今回の事例は、国際社会が一体となって感染症に立ち向かう必要性を改めて突きつけている。国内での感染拡大を防ぐことはもちろん、アフリカでの流行抑制に協力することも日本の課題だ。
国民にとっては遠い国の出来事のように思える感染症も、いつの日か国内の脅威となり得る。エムポックス「クレード1」の初確認は、その現実を如実に示している。