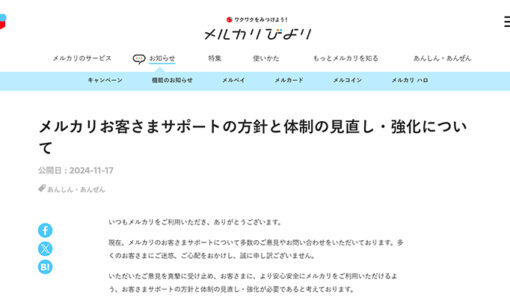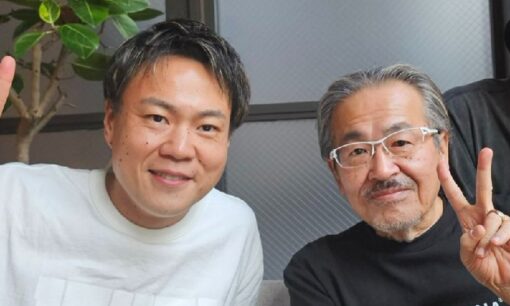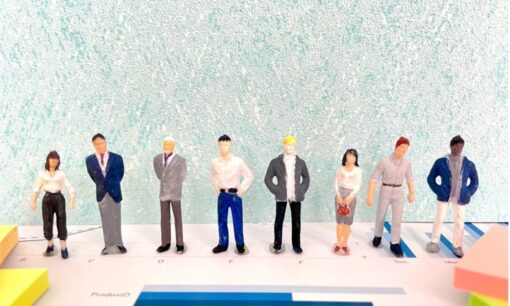バレーボール男子日本代表が、フィリピン・マニラで行われた世界選手権でまさかの1次リーグ敗退を喫した。世界ランキング7位の日本は、格下とされたトルコ、そしてカナダに連続ストレート負け。51年ぶりのメダルを目指した挑戦は、わずか2戦で終止符が打たれた。石川祐希主将が「力がないチーム」と言葉を絞り出したように、衝撃の敗戦は今後の強化方針に大きな課題を突きつけた。
トルコ戦から崩れた歯車
大会初戦、日本はランキング下位のトルコと対戦した。下馬評では有利と見られていたが、結果は0-3の完敗。サーブレシーブを崩され、攻撃の形を作れないまま失点が重なった。石川や高橋藍といった主力も決定率が低迷し、反撃の糸口をつかめない。崩れた流れを修正できず、第1戦で大きなダメージを受けた。
選手たちは「切り替えられなかった」と語ったが、精神面の立て直しが不十分なまま次戦へ臨んだことが、その後の敗退を決定づけることになった。
カナダ戦、連続失点で崩壊
崖っぷちで迎えたカナダ戦。勝利すれば望みがつながる一戦だったが、日本は序盤からサーブに押され、6連続失点を喫する苦しい展開に。第1、第2セットを立て続けに落とし、第3セットで大幅にメンバーを入れ替えるも、最後は22-25で力尽きた。
ティリ監督は試合後、「スパイクが良くなかった。サーブに対応できず、安定感を高めなければならない」と振り返った。だが単なる技術の問題だけではなく、全体の連動性の欠如や試合運びの未熟さが浮き彫りとなった。
セッター不在が生んだ歪み
敗因として最も大きく指摘されるのが、司令塔・関田誠大の不在だ。パリ五輪でも正セッターを務めた関田は、右足の手術で今大会を欠場。代わって起用された大宅真樹と永露元稀は奮闘したものの、エースを生かすトスワークには課題が残った。
「セッターはチームの指揮者。誰をどう使うかで勝敗が決まる」と専門家は語る。特に永露のトスは読まれやすく、相手にブロックを完成させられる場面が目立った。関田のような多彩で速い展開を欠いたことで、石川や高橋といった主力が封じ込まれた。
エース依存と疲労の影
攻撃陣にも陰りが見えた。石川はカナダ戦でわずか5得点に終わり、「何もできずに終わった」と肩を落とした。高橋はチーム最多の11得点を記録したものの、要所で決定力を欠いた。宮浦健人もサーブミスが重なり、チームを勢いづけられなかった。
背景にはシーズンを通しての疲労がある。特に宮浦はネーションズリーグ開幕から出ずっぱりで疲労の色が濃く、石川もクラブシーズンを経て調子が上がらないまま代表戦に臨んでいた。ダブルエースに依存する構造が、彼らが不調に陥った瞬間に一気に崩れるリスクを露呈した。
監督交代論と再建への道
SNSやファンの間では、ティリ監督への批判が噴出している。「ブラン監督に戻してほしい」という声が相次ぎ、昨夏のパリ五輪で日本をベスト8に導いたフィリップ・ブラン前監督の復帰を望む意見も多い。
ただし、指揮官の交代だけで問題が解決するわけではない。欧州クラブへの挑戦を通じて選手層を厚くすること、若手セッターを育成しチーム戦術の幅を広げることが不可欠だ。石川が精神的支柱として背負い続ける構造を見直し、全員で得点を重ねられる体制づくりが求められる。
「マニラの惨劇」を未来の糧に
わずか2戦で幕を閉じた世界バレーの挑戦は、日本男子にとって「マニラの惨劇」として記憶されるだろう。だが石川は「反省とともに、次に向けて進みたい」と前を向いた。来季にはアジア選手権、そしてロサンゼルス五輪予選が控える。今回の失敗を「力がなかった」と総括するだけでは何も変わらない。敗北の理由を突き詰め、再建の道筋を描けるかどうかが、日本バレーの未来を決定づける。