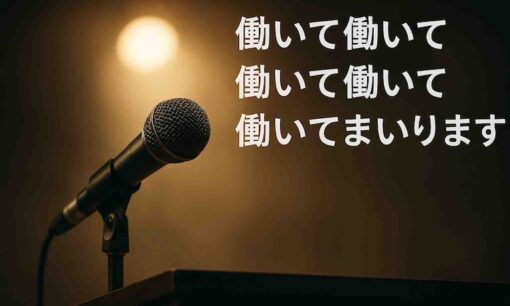広島・長崎への原爆投下から80年。米ピュー・リサーチ・センターが行った最新調査では、若い世代の間で「原爆投下は正当化できない」と考える人が多数派になっている。だがその一方で、「なぜそう思うのか」と問われたとき、明確に答えられない若者も多い。感情、知識、歴史。揺れる世論の背景には、複雑なアメリカの現在地がある。
若者が示した「NO」。変わり始めたアメリカの世論
2025年、米調査機関ピュー・リサーチ・センターが、原爆投下から80年を機に実施した世論調査。その結果は、かつてのアメリカでは考えられなかったような内容だった。
「正当化できる」と答えた人は35%。一方で「正当化できない」は31%、「わからない」が33%。これまで圧倒的に優勢だった「正当化支持派」との差は、ほとんどなくなっている。1945年、原爆投下直後にギャラップ社が行った調査では、実に85%が「支持する」と答えていた。それが今や、過半数すら割っている。
なかでも注目すべきは、18~29歳の若者たちの回答だ。「正当化できない」は44%に達し、「正当化できる」の27%を大きく上回った。つまり、若年層ではNOが多数派になっているのだ。
「白か黒かではなく、正当化できるかどうか判断できない、という気持ちが、若い人たちにはあるのだと思います」
そう語るのは、核倫理を専門とするアメリカ国内の識者だ。戦争を知らない世代が、戦争の決断を再考し始めている。
変わらない知識のなか、芽生えた“問い直し”の姿勢
とはいえ、こうした若者の反応を手放しで歓迎できるかというと、そこにもまた疑問が残る。
同じ識者はこうも続ける。
「原爆の実態を理解した上で“正当化できない”と考えている若者は、決して多くないと思います。原爆投下の経緯や被害の詳細についての知識は、20年前と比べてもそれほど変化していません」
つまり、「違和感」はあるが、「根拠」はまだ希薄なまま。SNSや学校教育、ニュースの断片などから、なんとなく正当化に違和感を抱いているに過ぎない可能性もある。
それでも、「わからない」と答えた33%の存在も含め、アメリカ社会に「考えようとする気配」が生まれていることは確かだ。正当化を当然としてきた時代から、「本当にそうなのか?」と問い直すフェーズに入ったとも言える。
核の正義と抑止論。米国内に残る二重構造
今回の調査では、核兵器について「世界をより危険にした」と答えた人は69%と多数を占めた。一方、「米国をより安全にした」との回答も26%に達している。
このねじれは何を意味するのか。ひとつには、アメリカの中で核兵器が「抑止力」として広く浸透してきたことが挙げられる。冷戦以降の「核による均衡」が平和を保ってきたという論理は、いまなお政治の中枢に根を張っている。
さらに、アメリカ国内での核実験による健康被害や環境汚染についての情報が一般市民にあまり届いていないことも、この構図を支えている。1030回に及ぶ核実験の痕跡は、議論の場に上がることはほとんどない。
原爆が「世界を危険にした」という認識と、「アメリカを守った」という神話。その二重構造が、若い世代のなかでも混在しているのが、今のアメリカなのかもしれない。
問い続ける力が歴史と向き合うための一歩に
今回の調査結果は、数字だけ見れば小さな変化に映るかもしれない。しかし、80年という年月を経た今も、原爆を「正当化できない」と答える人が増えていることには確かな意味がある。
たとえ知識が十分でなくとも、「違和感」から問いが始まることがある。その問いはやがて学びへとつながり、歴史の重みと向き合うきっかけになる。
日本にとって原爆は「過去の記憶」でありながら、アメリカにとっては「今も揺れる価値観」なのかもしれない。だからこそ、今後も私たちは問い続けていくべきなのだろう。