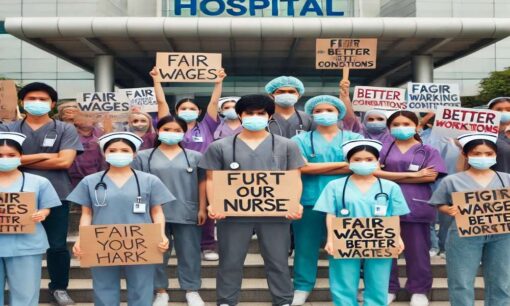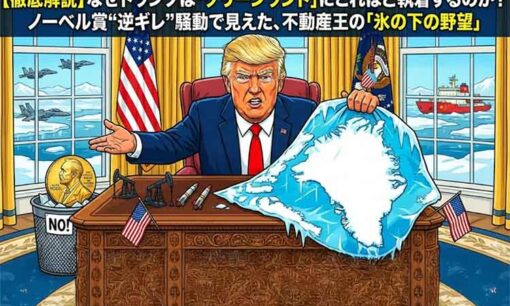東洋大学卒をめぐる怪文書で揺れる市政

静岡県伊東市の田久保眞紀市長(55)が、自身の学歴をめぐる“怪文書”の標的となり、就任からわずか2カ月で政治的な逆風にさらされている。問題の発端は6月上旬、市議らのもとに届いた匿名の文書だった。「東洋大学卒ってなんだ。中退どころか除籍だったと記憶している」と書かれており、田久保氏の経歴に疑問を投げかける内容だった。
この文書の影響は瞬く間に市議会にも波及し、6月25日の定例会では学歴について市民からの質問が取り上げられた。これに対して田久保氏は、「この件については代理人弁護士に任せている。私から個人的に発言することは控える」と述べ、明確な説明を避けた。この姿勢が一層の不信を招き、SNS上では「証明書を出せば一発で解決するはず」といった声が噴出している。
“卒業証明書で即解決”のはずが…説明を避ける姿勢が疑念に拍車
公人が学歴詐称を問われる場面は過去にもたびたび報じられてきた。2010年には民主党の国会議員が「慶應義塾大学卒」としていた学歴が実際には中退であったことが発覚し、辞職に追い込まれた。経歴の虚偽記載は、公職選挙法に抵触する可能性があるだけでなく、有権者の信頼を著しく損なう行為である。
今回、田久保氏に突きつけられた疑念も、法的な問題以上に“誠実さ”や“説明責任”の欠如として捉えられている。NEWSポストセブンの40代記者が、6月30日に母校・東洋大学を訪れ、卒業証明書の発行手続きを試みたところ、申請からわずか30分で受け取れたという。しかもこの証明書は、本人でなくても代理人による申請が可能であり、手続きのハードルは極めて低いことが確認された。
そのため、「忙しい」「弁護士に任せている」といった田久保氏の説明が、むしろ「出せない事情があるのではないか」という市民の疑念を呼ぶ結果になっている。手続きが極めて容易であることが明らかになった今、証明書の未提示は政治的なダメージを拡大させつつある。
怪文書という政治的攻撃の構図 地方選挙で繰り返される“文書戦”
今回の匿名文書について、田久保氏はX(旧Twitter)で「大変不本意ではありますが、法的手続きに入ることと致しました」と述べ、「怪文書のような匿名の誹謗中傷には毅然と対応する」と表明した。だがこの“怪文書”という存在そのものが、日本の地方政治に根深く残る「文書戦」の文化を映し出している。
過去にも、都知事選を前に猪瀬直樹氏にまつわるスキャンダルが“怪文書”という形で出回ったケースや、地方議員選での匿名中傷文書の配布など、政治的な攻撃手段としての“文書”はたびたび登場している。文書の信ぴょう性は別として、そのタイミングと内容が極めて選挙戦略的であることも少なくない。
今回のケースでも、田久保氏が現職市長を破って初当選したばかりである点、また伊東市初の女性市長という立場にあることが、政敵からの反感を集めていた可能性は否定できない。市政関係者の一部からは、「文面の言い回しに内部事情に通じた者の手口が感じられる」という声もあり、単なる匿名の誹謗ではなく、意図的なリークとしての可能性も指摘されている。
情報公開の壁と、市民の知る権利
伊東市の情報公開条例では、原則として市が保有する文書や情報は開示請求が可能とされているが、市長の卒業証明書のように「個人が保有する資料」は対象外である。選挙時に提出された経歴情報も、実際には“申告ベース”であり、選挙管理委員会が裏付けを取ることはない。
つまり、「卒業証明書を提出するかどうか」は、あくまで本人の判断に委ねられており、それゆえにこそ“提示しない理由”が政治的に大きな意味を持ってしまう。市民が事実を確認しようとしても、制度的な壁に阻まれる以上、政治家本人の誠意と説明姿勢にすべてがかかっているという構図は変わらない。
SNSの分断と、政治的リアリズムの問い
SNS上では、「卒業証明書を出せば終わる話」「なぜ市長が出さないのか」といった批判の声が高まる一方で、「怪文書に反応する必要はない」「女性市長へのバッシングだ」とする擁護の声も見られる。特に、田久保氏が掲げていた“クリーンな市政改革”に期待を寄せる若い世代の一部からは、今回の疑惑そのものに「仕組まれた匂いがする」と警戒する意見もあがっている。
一方、無党派層や市政に関心を持つ市民の中には、「政治家として“誠実な対応”を見せてほしい」とする現実的な声が少なくない。証明書の提示は、法的な義務ではないとしても、信頼を回復する最も簡潔で確実な手段である。あえてそれを避ける選択が、市民との距離を広げていることは否めない。
誠実さこそが信頼を守る唯一の方法
市長という公人の立場にある以上、経歴に対する疑問には真摯に向き合う姿勢が求められる。卒業証明書を提出すれば即座に終結するはずの騒動が、ここまで長引いていること自体が市民に不信感を与えている。