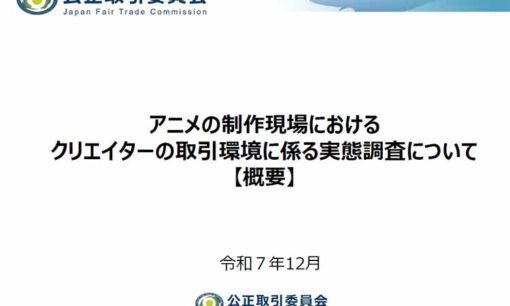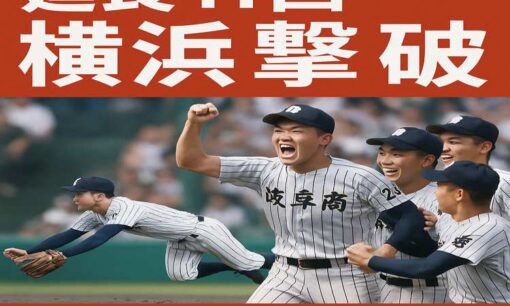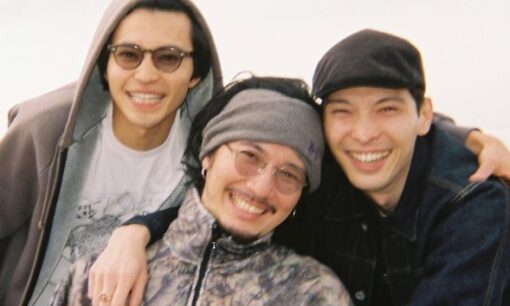新年度の始まりとともに、多くの新小学1年生が新たな学校生活を迎える。しかし、期待に胸を膨らませる子どもたちにとって、学校のトイレ環境が大きな課題となることがある。文部科学省の調査によれば、全国の公立小中学校にある便器の約3割は依然として和式であり、多くの子どもたちが使いづらさを感じているという。家庭や商業施設では洋式トイレが一般的になったことで、学校の和式便器に対する戸惑いが広がっている。
NPO法人日本トイレ研究所の加藤篤代表理事は、「家や商業施設ではほとんどが洋式であることを考えると、学校にある和式の割合は多い。家庭とのギャップが子どもたちにとってストレスになることもある」と時事通信の報道で指摘。同研究所が2022年に全国の小学生1000人を対象に行った調査では、和式便器を「抵抗なく使用できる」と答えたのは22.4%にとどまり、「使用できない」との回答が26.7%に上った。4人に1人が和式便器を使えないという結果は、学校のトイレ環境の課題を浮き彫りにしている。
また、トイレに行くのを我慢する理由として「友達に知られたくない」という回答が多く見られる一方で、「和式便器が使いづらい」との声もあった。加藤氏は「トイレを我慢すれば体調不良につながるだけでなく、授業にも集中できなくなる可能性がある」と警鐘を鳴らす。さらに、災害時やキャンプなどの場面では和式便器しかない状況も考えられることから、「入学前に、和式・洋式どちらにも対応できるようにしておくことが安心につながる」と語った。
SNSでも賛否が分かれる
この問題について、SNS上でもさまざまな意見が交わされている。
和式便器の必要性を疑問視する声は少なくない。
「家に和式なんてないのに、学校だけ和式って意味がわからない」
「洋式化が進んでいるのに、子どもだけ和式に適応させるのはナンセンス」
「学校も早く洋式に切り替えればいいのに、なぜ変わらないのか」
一方で、防災や海外事情を考慮すると、和式便器の使い方を知っておくことは重要だとする意見もある。
「地震のときに避難所のトイレが和式しかなかったらどうするのか」
「アジア圏ではまだまだ和式が多い。海外に行ったときに困らないように慣れておいた方がいい」
「災害時の備えとして、最低限の知識は必要」
こうした意見の違いは、世代間の経験の違いにも起因している。和式便器を使う機会が多かった世代にとっては「慣れておくべき」と考えやすく、一方で現代の子どもたちにとっては「和式を使う必要がそもそもない」と映ることが多い。
学校の対応と今後の課題
文部科学省は学校施設の老朽化対策の一環としてトイレの洋式化を進めているが、予算の問題からすぐにすべての和式便器を撤去するのは難しい状況だ。そのため、一部の自治体では、新1年生向けのトイレ使用ガイダンスを実施し、和式便器の使い方を指導する取り組みも始まっている。
ある公立小学校の校長は「和式トイレは今後減らしていく方針だが、現在も残っている学校は多い。和式便器を使う場面があることを考慮し、保護者には事前に使い方を教えておくようお願いしている」と話す。
和式便器の存続をめぐる議論は今後も続きそうだ。洋式化を進めるべきとの声がある一方で、**「いざというときに使えなくて困る」**という意見も根強い。子どもたちがストレスなく学校生活を送れる環境づくりのために、学校側と保護者の間でより具体的な対策が求められている。