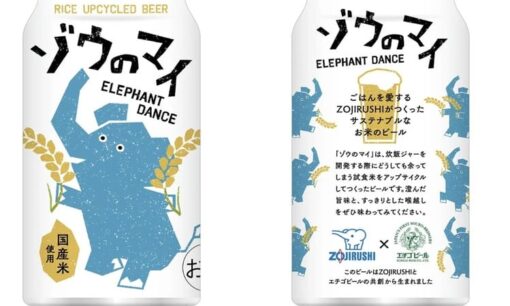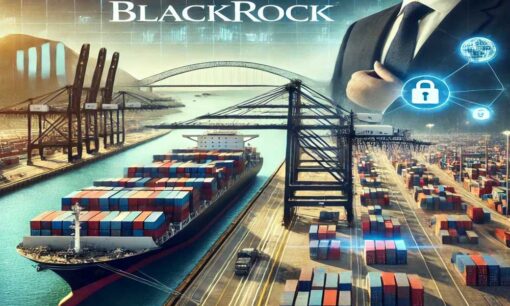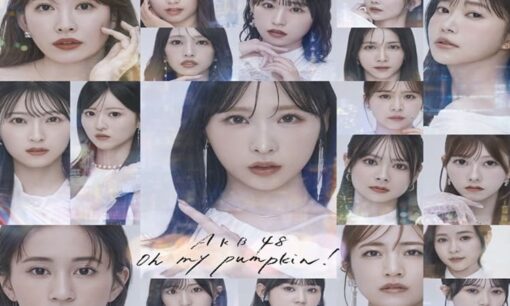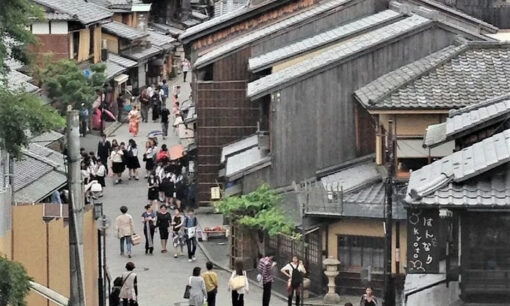ある日、突然届いた6500万円超の請求書。 それは、ある疑惑の扉を開く決定的な鍵だった。
名古屋に本社を置く、産業機器や電子部品の専門商社の株式会社ナ・デックス(東証スタンダード:7435)が2月14日に公表した特別調査委員会の報告書には、驚くべき取引の実態が記されている。架空の商品を売買する「循環取引」、実態のない在庫の発生、さらには不正に関わった可能性のある関係者の証言――企業の信頼を揺るがす事態の詳細が明らかになった。
ナ・デックスは何が起こったのか。
どのようにして発覚し、今後の対応はどうなるのか。
その全容を報告書をもとに解説する。
突如発覚した6500万円超の「架空取引」疑惑
発端は、2024年11月。
ナ・デックス北九州営業所に、仕入先のC社から「合計6517万円200円の売掛金を支払ってほしい」との請求が届いた。だが、営業所長が確認したところ、請求された商品が取引先に届いた形跡がない。さらに、他の仕入先との取引を調査すると、同様に実態のない取引がいくつも浮かび上がった。
「何かがおかしい」――そう判断したナ・デックスは、外部の弁護士と公認会計士を含む5名の特別調査委員会を立ち上げ、徹底調査に乗り出した。すると、驚くべき事実が明らかになった。
元業務委託社員Xが主導していた「循環取引」のカラクリ
報告書によると、不正の中心にいたのは、北九州営業所に勤務していた元業務委託社員のX氏。彼が関与していた取引は、通常の売買とは異なり、「架空の仕入れ」と「虚偽の売上」が繰り返されていた。
まず、X氏は仕入先のC社やD社、B社などから商品を購入したことにし、実際には存在しない商品を帳簿上に計上していた。そして、その商品をA社や他の企業に販売したように装い、伝票を操作して架空の売上を計上していた。さらに、A社を起点にE社やH社、G社を経由し、最終的にC社やD社、B社へと戻るという形で、取引が循環しているように見せかけていた。この過程で、実際には商品は動いておらず、取引のたびに利益が上乗せされる仕組みとなっていた。
そして、最終的には実際に存在しない商品がナ・デックスの倉庫にあるかのように計上され、「預け在庫」として処理されていた。
X氏は、これらの取引を巧妙に操りながら、発覚を遅らせるために関係者と口裏を合わせたり、帳簿を操作したりしていた。報告書によると、2020年から2024年10月までの間に、循環取引に関わった総額は約1億2000万円超にのぼるという。
巧妙な手口――架空取引だけでなく「領得行為」も
X氏が行っていた不正は、循環取引だけではなかった。B社からPCや電動工具(インパクトドライバーなど)を「仕入れた」ことにし、それを実際には受け取って転売し、得た現金を私的に流用していたことも明らかになった。
2020年以降、B社からナ・デックスへ納品されたとされるPC等の取引件数は120件にのぼり、仕入額は約1億4867万円だった。報告書によれば、X氏が得た不正利益は少なくとも1億円規模と推定されている。さらに、この不正にはB社やA社の関係者も一部関与していた可能性が高いとされ、X氏はB社の協力を得て、納品書を実態と異なる内容に書き換えさせ、ナ・デックスに虚偽の書類を提出していた。
ナ・デックスの今後――信頼回復に向けた再発防止策
この報告書の公表を受け、ナ・デックスはいくつかの対応策を発表した。まず、不正による影響を精査し、有価証券報告書や決算短信の修正を実施する。また、取引の透明性を高めるために社内監査を強化し、取引先管理の厳格化を進める方針を示した。さらに、特別調査委員会の提言に基づき、コンプライアンス教育の強化や、内部監査の仕組みを見直すとしている。
また、今回の問題の責任を明確にするため、経営陣の報酬減額を実施する。代表取締役社長は月額報酬の20%を2か月間減額し、常務取締役も月額報酬の10%を2か月間減額することを決定した。
ナ・デックスは、今回の不正を真摯に受け止め、ガバナンスの強化を通じて信頼回復を図る考えだ。
今後のナ・デックスの対応が、投資家や取引先からどのように評価されるのか。企業が不正を乗り越え、再び成長へと舵を切るためには、透明性と誠実な対応が求められる。