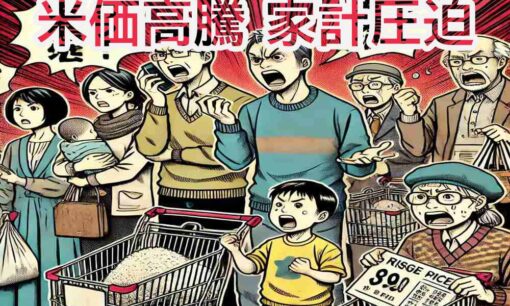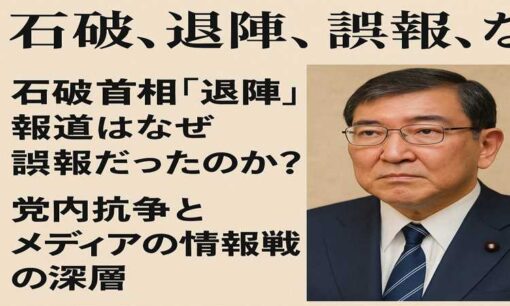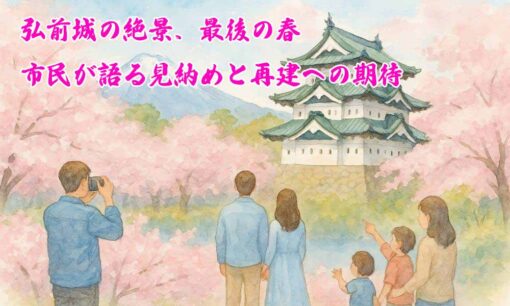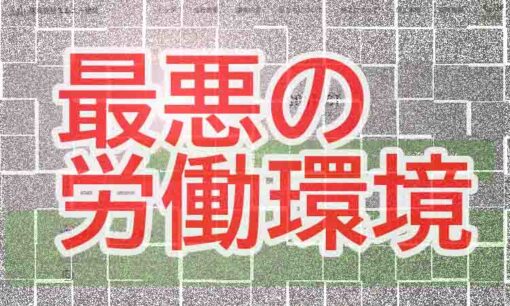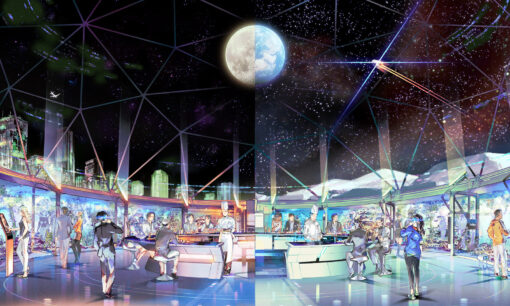米価の高騰が続く中、政府は備蓄米21万トンを市場に放出することを決定した。これは流通の停滞を解消し、価格安定を図るための異例の措置である。備蓄米とは何か、放出の背景や価格への影響、制度の仕組みをわかりやすく解説する。
米価高騰で政府が異例の決断 備蓄米21万トン放出へ
政府は米価の高騰を受け、備蓄米21万トンを市場に放出する方針を決定した。農林水産省によると、放出は2024年3月中旬を予定しており、まず15万トンを供給し、流通状況を見て追加の放出を検討するという。米価の安定を目的とした備蓄米の放出は初めてのことで、消費者や市場関係者の注目を集めている。
背景には、昨年夏に起きた「令和の米騒動」がある。南海トラフ地震の臨時情報をきっかけに消費者が米を買いだめし、全国の店頭から米が姿を消した。農水省は当初「新米が出回れば落ち着く」と静観していたが、米価の高騰が続いたため、今回の方針転換に踏み切った。
備蓄米とは?制度の歴史と役割を解説
備蓄米は、食料の安定供給と価格調整を目的に政府が保管している米である。その歴史は1993年の「平成の米騒動」にさかのぼる。この年、日本は記録的な冷夏に見舞われ、米の収穫量が激減。スーパーには米を求める消費者が殺到し、社会的混乱が発生した。この経験を教訓に、1995年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)に基づき、備蓄米制度が開始された。
農水省によると、備蓄米は常に約100万トンを全国の民間倉庫約300カ所に分散保管している。これは「10年に1度の不作」や「2年連続の不作」に対応できる量で、必要に応じて市場に放出される仕組みだ。
備蓄米の管理と活用の仕組み
備蓄米は以下の流れで管理されている。
- 買い入れ:毎年1月から、秋に収穫される米を20万トン程度買い入れる。
- 管理:温度15度以下に保つなど品質を厳格管理
- 放出:不作や災害時、または流通停滞時に放出される。
- 活用:保存期限5年を迎えた備蓄米は飼料用や学校給食、子ども食堂などに無償提供される。
農水省によると、備蓄米の年間維持費は約478億円にのぼる。
この費用には保管料の約142億円や、売却時の価格下落による損失が含まれる。
米価高騰の背景 「令和の米騒動」と流通の停滞
米価高騰の直接的な要因は、2023年夏に発生した「令和の米騒動」だ。南海トラフ地震の臨時情報により、消費者が米を買いだめし、店頭から米が消えた。農水省は当初「新米が市場に出れば価格は落ち着く」として静観していたが、需要が高まり価格は上昇を続けた。
さらに、米の流通構造にも問題があった。2024年産米の収穫量は前年を18万トン上回る見込みだが、全国農業協同組合連合会(JA全農)など主要業者の集荷量は21万トン減少している。農水省はこの「流通の目詰まり」を解消するため、備蓄米の放出を決定した。
異例の放出 「1年以内の買い戻し」条件付き販売
今回の備蓄米放出は、1年以内に同じ業者から同量を買い戻すことを条件としている。政府が価格調整のため市場に米を投入する一方で、過度な価格下落を防ぐ狙いがある。
農水省によると、放出対象は年間5,000トン以上の玄米を取り扱う集荷業者。
入札を経て備蓄米が供給されるため、流通の効率化が期待される。
消費者への影響 米価の安定に期待
今回の備蓄米放出により、米価の高騰が落ち着く可能性がある。市場への供給量が増加することで、需要と供給のバランスが整い、価格安定につながると期待されている。
ただし、価格がどの程度下がるかは未知数だ。米を取り巻く市場は、消費動向や輸入状況など多様な要因で変動する。消費者にとっては、日々の食卓に欠かせない米が安定的に供給されることが最も重要であり、政府の今後の動向が注目される。
まとめ 安心を支える備蓄米制度の意義
米は日本人にとって、文化的にも生活面でも重要な存在である。備蓄米制度は、万一の事態に備えた「食の安全保障」の要であり、価格安定の役割も担っている。今回の放出を機に、消費者の関心が備蓄米に向かい、制度の意義が再認識されることが期待される。政府は米価安定を目指す中、備蓄米の適切な管理と放出基準のさらなる整備が求められている。
【この記事に関連する記事】