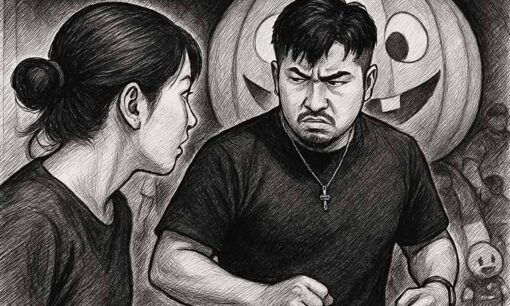2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにする――。 2019年、G20大阪サミットで世界が交わした約束「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」から7年。時計の針は確実に進んでいるが、果たして人類はプラスチックの奔流を止められているのか。
2026年2月13日、その答え合わせとも言える重要文書が公開された。「第7次G20海洋プラスチックごみ対策報告書」である。日本の環境省が全面的にバックアップし、議長国である南アフリカ共和国が主導して取りまとめたこの報告書には、G20メンバーを含む23か国と9つの国際機関が直面する「現実」が生々しく刻まれている。
そこに見えてきたのは、法整備という初期段階を終えた世界が突き当たった「リサイクルの限界」と、それを突破するために企業へと突きつけられる「新たな責任」の姿だった。
「法整備」は終わった。次なる壁は「システムの限界」
報告書を読み解くと、世界の「脱プラ」に向けた法的な包囲網はすでに完成しつつあることがわかる。回答した23か国すべてが、何らかの形でプラスチック規制や循環経済に関する法律を整備しており、83%(19か国)が国家レベルの行動計画を策定済みだ。レジ袋の有料化やストローの禁止といった施策は、もはや先進国だけの専売特許ではなく、世界の共通言語となったと言っていい。
だが、法律を作れば海が守れるほど、現実は甘くない。報告書が浮き彫りにしたのは、多くの国が直面している「リサイクルの質」という壁だ。
単にごみを回収箱に入れるだけでは意味がない。複合素材で作られたパッケージや、汚れの落ちない容器など、現代の製品はあまりにリサイクルしにくい。報告書では、カナダやタイなどが「製品設計の段階でリサイクル性が考慮されていない」ことを主要な課題として挙げている。
さらに、原油価格の変動により新品のプラスチック(バージン素材)の方が安価で手に入るという経済合理性の壁が、再生材の市場拡大を阻んでいる。
「作って、使って、燃やす(あるいは埋める)」という一方通行の経済から、「回す」経済へ。その移行期において、既存のリサイクルインフラと技術が悲鳴を上げているのが今の世界の現在地なのだ。
「捨てたもん勝ち」は終わりへ。世界で加速するEPR(拡大生産者責任)
リサイクルの限界を突破するために、世界が選んだ次なる一手。それは、「プラスチックを作って売る企業が、その最期まで面倒を見る」というルールの厳格化だ。これを専門用語で「拡大生産者責任(EPR)」と呼ぶが、報告書はこのEPRがもはや努力目標ではなく、企業の財務諸表を直撃する「コスト」になりつつあることを示している。
報告書から、世界のEPR最前線を読み解いてみよう。
まず注目すべきはフィリピンの事例だ。同国では2022年に「EPR法」が施行され、企業に対してプラスチック包装の回収を義務付けた。その目標は極めて野心的で、2028年までに市場に出したプラスチックの「80%」を回収させるというものだ。達成できなければ罰則が待っている。これは途上国・新興国においても、企業責任が回避できないものになったことを象徴している。
欧州に目を向ければ、その仕組みはより精緻かつシビアになる。ドイツでは「使い捨てプラスチック基金」が設立された。これは、タバコのフィルターやテイクアウト容器、風船などを製造するメーカーから賦課金を徴収し、それを原資として自治体が行う公園や道路の清掃費用、廃棄物処理費用を賄うという仕組みだ。「ポイ捨てされたごみの後始末代」までメーカーが支払う時代が到来したのである。
イギリスの事例もビジネスパーソンには見逃せない。2022年から導入された「プラスチック包装税」は、再生プラスチックの使用率が30%未満の包装材に対して課税するという直球の施策だ。リサイクル材を使わなければ税金を取られる。ならば、多少コストがかかっても再生材を使おう――という強力な経済的インセンティブが働いている。
これらの事例が示すのは、環境対策が企業の善意に依存するフェーズから、明確な義務とコストとして経営に組み込まれるフェーズへ移行したという事実だ。「売った後は知りません」というビジネスモデルは、もはや世界では通用しなくなっている。
ストローだけではない。海の沈黙を破る「ゴーストギア」への挑戦
そしてもう一つ、今回の報告書で光が当てられた重要なテーマがある。それが「ゴーストギア(遺棄漁具)」の問題だ。
プラスチックごみというと、私たちはつい海岸に漂着したペットボトルやレジ袋を想像しがちだ。しかし、海洋ごみの重量ベースで大きな割合を占め、海洋生物にとって最も直接的な脅威となっているのは、漁業活動によって海に流出・投棄された網やロープなどの漁具である。これらは海中を漂い続け、魚やウミガメを無差別に絡め取り殺し続けることから「幽霊漁具(ゴーストギア)」と呼ばれ恐れられている。
報告書によれば、これまで「見えないごみ」として放置されがちだったこの問題に対し、各国が本腰を入れ始めている。
カナダの動きは素早い。2027年までの完了を目指して「ゴーストギア・アクションプラン」を策定中であり、漁具の回収プログラムに政府が直接資金を投入している。さらに、漁業ライセンスの条件として、紛失した漁具の報告を義務付けるという強硬策も講じている。
漁業大国ノルウェーの取り組みはさらに歴史が深い。1980年代から毎年のように海底の遺棄漁具回収調査を実施しており、漁師が漁具を失った際に即座に報告できるアプリの導入も進めている。失った場所がわかれば、回収できる確率も上がるからだ。
トルコでは「ゴーストネットプロジェクト」が進行中だ。これは単に海底から網を引き上げるだけでなく、回収した網をアップサイクル(再製品化)して新たな価値を生み出そうという試みである。
これらの取り組みは、海洋ごみ問題が単なる「消費者のマナー問題」ではなく、「産業廃棄物処理の問題」であることを如実に物語っている。漁業という産業活動に伴う環境負荷をどう減らすか。ここにもまた、技術と管理、そして責任の明確化が求められている。
日本が示す「科学とデータ」という羅針盤
こうした世界の潮流の中で、日本はどのような役割を果たしているのか。
今回の報告書取りまとめにおいて、日本は環境省が南アフリカ共和国を全面的に支援し、共同でドラフティングを行うなどリーダーシップを発揮した。だが、日本の貢献は外交的な汗をかくことだけにとどまらない。
特筆すべきは「科学とデータ」による貢献だ。対策を進める上で最大の障壁となっているのが「データの欠如と不統一」であることは、多くの国が認めるところだ。海ごみの量はどれくらいか、どこから来ているのか、その測定方法がバラバラでは対策の打ちようがない。
日本は、海洋マイクロプラスチックのモニタリングデータを集約した世界規模のデータベース「AOMI(Atlas of Ocean Microplastics)」を2024年5月に立ち上げた。世界中のデータを統一基準で比較可能にしようというこの試みは、感情論ではなくエビデンスに基づいて対策を進めるための重要なインフラとなる。さらに、広大な海を効率的に監視するために、ドローンやリモートセンシング技術を活用したガイドライン策定も主導している。
2050年への分岐点
第7次報告書が突きつけたのは、法規制という「枠組み作り」の時代が終わり、実効性のあるシステムをどう動かすかという「実行」の時代に入ったという現実だ。
リサイクルの質をどう上げるか。EPRによって企業の責任をどこまで拡大するか。そして、見えない海底のごみをどう回収するか。
報告書に記された23か国の苦闘と挑戦の記録は、そのままこれからの企業経営におけるリスクとチャンスのリストでもある。サステナビリティはもはやスローガンではない。生き残るための条件なのだ。日本、そして世界の企業は今、その本気度を試されている。