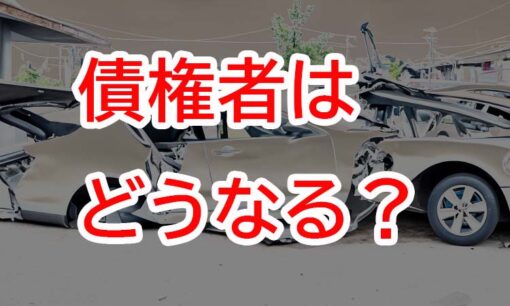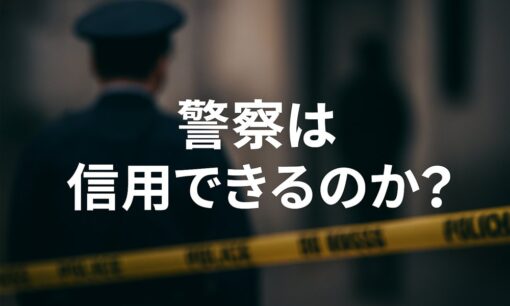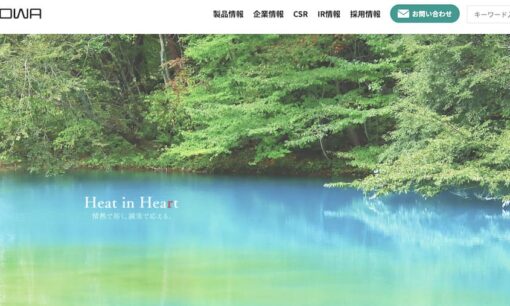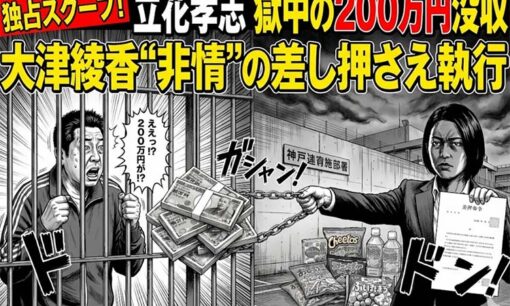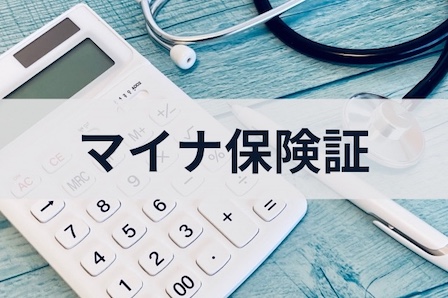
病院の外来フロアでは、診察券やカードを手にした患者が列をつくり、顔認証付きカードリーダーの前では操作に戸惑う高齢者の姿が見られる。画面の指示が分かりづらく、読み取りに失敗するたびに操作が止まり、職員が横から手助けする場面も珍しくない。
マイナ保険証の導入が進む一方、現場の負担と患者側の不安がなお続いている。
受付で生じる小さなつまずき
都内の病院では、70代の男性がカードを端末にかざしていたが、顔認証がうまくいかず、画面の前で身じろぎを繰り返していた。認証が何度も失敗し、最後はカード差し込みに切り替えたものの、暗証番号の入力がうまくいかず、スタッフが駆け寄るまで操作は進まなかった。
こうした状況は、オンライン上の声からも確認される。高齢者がマイナンバーカードで受診した際に、薬剤情報や通院歴が確認できなかったという報告や、顔認証の難しさ、カードの読み取り不良を訴える投稿が目立つ。結果として受付の列が伸び、医療機関側の対応も増えている。
制度が示す利点と現場の温度差
国はマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みを推進し、2025年9月時点で登録率は8割を超えている。しかし、医療機関での実際の利用率は4割に満たず、制度の浸透には温度差がある。
背景には操作の難しさや機器の使いにくさがある。暗証番号の失念や顔認証の失敗、カード読み取りのエラーなど、利用者自身がスムーズに扱えないまま来院するケースは少なくない。制度が持つ利点は多い。薬剤情報の共有や高額療養費の手続き簡素化、救急時の迅速な情報確認は、医療の質向上につながる。しかし、その利点が患者自身に実感される前に、操作上のハードルが立ちふさがっている。
資格確認書が支える“移行期”の受診
従来の健康保険証は、有効期限内であれば利用できるが、その期限は最長でも2025年12月2日までと定められている。2024年12月2日以降は新規発行が停止され、保険証としての機能はマイナ保険証へ移行している。2026年3月末まで使用できる特例措置もあるが、紙の保険証は制度の中で役割を終えつつある。
後期高齢者医療制度に加入している人の保険証は、2025年7月31日が有効期限となる。すでに紙の保険証を使えないケースもあり、制度変更の影響が最も強く現れる層でもある。
こうした状況への不安に対応するため、資格確認書が無償で交付されている。申請不要で、有効期限前に自動的に送付される仕組みだ。形式は保険者ごとに異なるものの、有効期限は最長5年の範囲で設定される。後期高齢者医療制度では2026年7月31日まで一律で交付され、マイナ保険証を持たない人も自己負担額のみで受診できる環境が維持されている。制度全体を捉えると、資格確認書は移行期を支える安全網として位置づけられている。
スマートフォンで受診できる未来と残る課題
2025年秋からはスマートフォンを保険証として利用できる仕組みが始まった。カードを持ち歩かずに受診できる点は便利だが、この機能を使いこなせるのは登録作業に慣れた人に限られる。アプリの操作や設定が難しい高齢者は依然としてカードを中心に利用するため、暗証番号や顔認証の問題は解消されていない。
医療機関の受付では、スマートフォン利用者とカード利用者が混在し、スタッフは従来以上に幅広い対応を求められている。技術の進歩と利用者の能力との間に、明確な溝が残されたままだ。
制度を定着させるために必要なもの
利用率の向上と現場の負担軽減を両立させるには、機器の改善だけでなく、操作に不慣れな人に寄り添う体制が欠かせない。端末の台数不足や読み取り不良は列を長引かせ、スタッフの業務を圧迫する。制度が普及すればするほど、こうした課題は表面化する。
デジタル化が進むなかで、誰もが同じ速度で新しい仕組みに順応できるわけではない。制度を継続的に運用していくためには、技術と現場をつなぐサポートをどれだけ整えられるかが鍵になる。