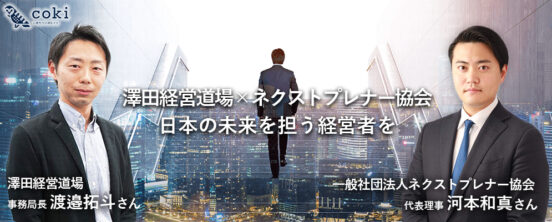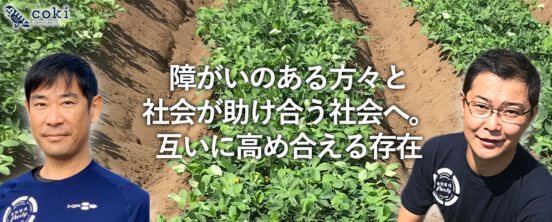銀座英國屋が、役目を終えたスーツを資源として循環させる取り組みを継続している。BRINGと連携し、年間200着規模での回収を安定させながら、顧客の“捨てられない想い”と職人技を未来へつなぐ独自の循環モデルが広がっている。
スーツ回収10年、資源循環の取り組みが定着
老舗オーダースーツ店の銀座英國屋が、JEPLAN(BRING)と進める衣料品リサイクル活動が10年を迎えた。同社は2015年から役目を終えたスーツの回収に取り組み、直近半年(2024年12月〜2025年6月)だけで100着、年間換算で約200着を安定的に維持する。
これは単なる数量の実績ではなく、顧客が抱く「思い出の一着を捨てたくない」という感情に寄り添い続けた結果でもある。BRINGが持つ反毛技術により、ウールスーツは自動車の内装材などへと再資源化され、服が新たな用途へと受け継がれていく。
“捨てられない一着”を循環に変える独自モデル
銀座英國屋では、長年にわたり「大切にしてきたスーツを処分できない」という相談が寄せられてきた。
「このスーツを着て商談を成功させた」「家族の形見で手放せない」――。顧客が抱える物語と向き合う姿勢が、2015年にBRINGと出会い、循環への仕組みづくりへとつながった。
オーダースーツ店としての専門性もこの循環モデルを支える。スタイリストとフィッティング専任技術者を分業する体制により、顧客の体型を基点にゼロから図面を起こすフルオーダーを実現。若手育成が進む工房が図面を形にし、納品後もスーツが長寿命で使われ続ける。
衣料品ロスが課題となる業界において、同社の製品廃棄率は0.1%以下と極めて低い水準にある。
「人的サステナブル」で技術と働きがいを未来へつなぐ

三代目社長の小林英毅氏は、循環型社会の実現には「人」に対する視点が不可欠だと語る。同社が掲げる「人的サステナブル」とは、社員一人ひとりが働きがいを感じ、技術を磨き続けられる現場を維持する考え方だ。
平均年収525万円(アパレル平均比130.9%)、平均勤続年数23年、入社3年未満離職率ゼロ――。数字の裏側にあるのは、職人技を未来へ継承するための土台づくりである。
一対一のミーティングを重ね、評価制度の改良を進めるなど、社員が成長できる環境整備を続けてきた。顧客のスーツに宿る想いを循環させるには、まず現場の技術と働きがいを守ることが欠かせないという理念が貫かれている。
服と人の循環を両輪で回す新しいサステナブル像
銀座英國屋の取り組みは、資源循環と人的サステナブルを同時に回すことで、企業の持続可能性を高められることを示している。
BRINGとの連携によるスーツの再資源化に加え、職人技の継承と長期的な雇用・成長環境を重ね合わせることで、服も人も循環する独自のモデルが成立している。
成熟した紳士服市場においても、顧客の“想い”を資源として捉える新しい価値が生まれつつある。今後も同社の取り組みは、サーキュラーエコノミーの実装例としてより注目を集めそうだ。