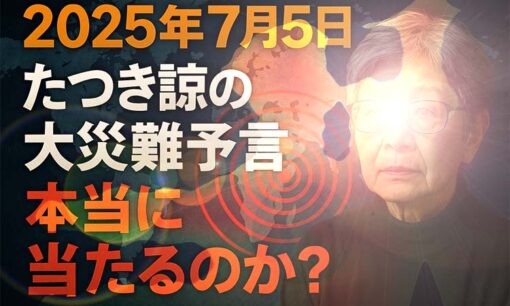静まり返った永田町の会見室に、張りつめた空気が一瞬走った。「一生、つきません」。
安倍晋三元首相の銃撃事件をめぐる所管外の質問に対し、小野田紀美経済安全保障担当相が放った一言だった。
事件から3年半が過ぎてもなお癒えない痛みと、テロ行為に対する強い拒絶。それらが凝縮された言葉は、会見の場だけでなく、社会全体に波紋を広げている。安倍氏との深い縁、国際的にも通じる毅然とした姿勢、そして政治家としての存在感。
今回のやりとりは、小野田氏という人物を改めて浮かび上がらせた。
静まり返る会見室で響いた一言
11月11日午前の永田町。淡い光が差し込む会見室に、記者たちのノートパソコンのキーボード音がかすかに混ざる。いつも通りの定例会見の空気は、小野田紀美経済安全保障担当相が所管事項の説明を淡々と終えた瞬間まで、確かに穏やかだった。
その静けさを破ったのは、安倍晋三元首相銃撃事件の裁判を取材しているフリー記者の質問だった。「事件前日、小野田さんの演説会場にも被告が近づいていたことをどう受け止める」。会見室の空気が一瞬停滞し、周囲の視線がわずかに動いた。
小野田氏は「裁判のことに関して私がコメントすることはございません」と静かに返す。しかし記者はさらに踏み込み、「お気持ちの整理はついたのか」と尋ねた。小野田氏は真正面を見据え、短く、しかし深く言い放つ。
「一生、つきません。以上です」
その言葉は、静かな怒りと喪失の深さを包み隠さず、会見室の空気を一変させた。
質問者は「……すみませんでした」と声を落とし、室内にはしばし沈黙が広がった。
「テロリストには何も与えない」明確な一線
続く別の記者は、旧統一教会と政治との関係に触れながら事件背景を尋ねたが、小野田氏は即座に「所管外だと思います」と前置きしたうえで、「『テロリストには何も与えない。名前もだ』という言葉があります。テロリストに対し、私から申し上げることはございません」と語り、質問を突き放した。
その姿勢は国際的にも通じる。ニュージーランドでは2019年の銃乱射事件後、アーダーン首相(当時)が「私は犯人の名を口にしない」と宣言して注目を集めた。米国でも“No Notoriety”運動が広まり、メディアが犯人の情報を過度に扱うことが事件の再生産につながるとの考え方が浸透しつつある。
日本の政治家が同様の姿勢を明確に示すのは珍しく、小野田氏のコメントは「テロ行為を社会がどう扱うべきか」という本質的な議論を突きつける発言でもあった。
安倍晋三氏との最後の日。信念を支えた絆
小野田紀美という政治家を語るうえで、安倍晋三氏との関係は欠かせない。2022年の参院選、小野田氏は「信念として公明党の推薦を受けない」と宣言し、党内でも異例の独立姿勢を貫いた。孤独な戦いに見えたその状況で、岡山まで応援に駆けつけたのが安倍氏だった。
安倍氏はX(旧ツイッター)に「日本を守り抜く小野田紀美候補に力を!」と投稿する。その投稿は、安倍氏の生前最後の発信となった。その翌日、奈良で銃撃事件が起きた。
小野田氏の胸中には、あの日の記憶が今も鮮やかに残っているのだろう。「一生つきません」という言葉には、単なる政治的な発言ではなく、恩人を突然奪われた深い悲しみがにじむ。政治家としての歩みを支えてきた存在を失った衝撃は、時間が経っても消えるものではない。
会見文化と“場違い質問”の波紋
今回の質疑応答は、政治家と記者の関係、そして日本の記者会見文化そのものを浮き彫りにした。フリー記者が被告を「山上さん」と“さん付け”で呼んだことには、会見動画のコメント欄やSNSでも強い反発が寄せられた。事件をめぐる背景を伝える立場にある記者が、犯人の立場に寄り添うような口調を用いるべきかどうかという問題も提起された。
政治家に厳しい質問を投げることは民主主義の要だが、失言を誘うような問いかけや、事件の重さを軽視するかのような言動は、ジャーナリズムの信頼を損ねかねない。
大臣の所管外の質問で会見が占有されれば、本来の議論すべき政策の場が失われる。今回の一連のやりとりは、政治とメディアの関係に長年存在してきた課題を、改めて可視化する形になった。
小野田紀美という政治家の存在感
今回の会見をきっかけに、小野田氏の言葉や姿勢に魅力を感じる層がさらに広がった。強い言葉を淡々と発しながらも、感情が暴走することなく、あくまで理性と信念を基盤に語る姿は、他の政治家にはない説得力を持つ。
SNSでは、政策説明を積極的に行いながらも、過剰なパフォーマンスに頼らない“素の姿”が好意的に受け止められている。
国会質疑ではユーモアを交えながらも本質を射抜く質問を重ね、若い層からの支持も厚い。今回のような緊張感ある場面でも、感情的ではなく、しかし冷たくもない“静かな強さ”を見せることで、小野田紀美という政治家の人物像は、より鮮明になった。
テロに何を与えるのか? 日本社会への問い
銃撃事件には旧統一教会の問題が絡み、献金や宗教と政治、被害者救済といった複雑な論点がある。しかし、どれほど事情があったとしても、暴力が主張を通す手段として認められる社会は健全とは言えない。犯人の動機を物語化する報道が続けば、結果的に暴力に正当性を与えてしまう危険がある。
小野田氏の「テロリストに何も与えない」という言葉は、政治家の個人感情の表明にとどまらず、社会全体に向けた警鐘でもある。事件をどう扱い、暴力とどう対峙するのか。その基準をどこに置くべきかを、私たちは改めて問い直さなくてはならない。