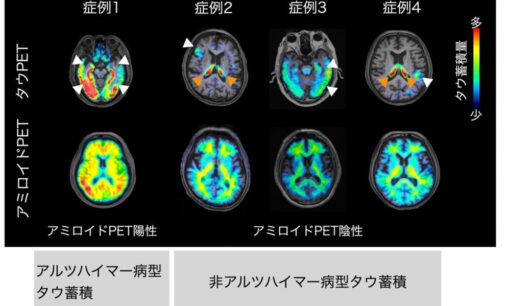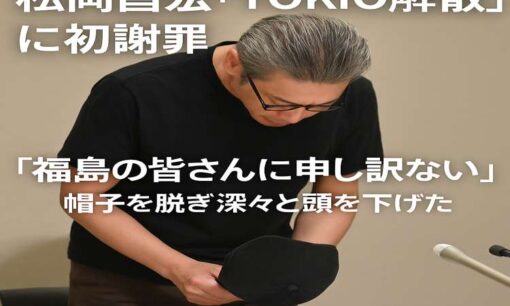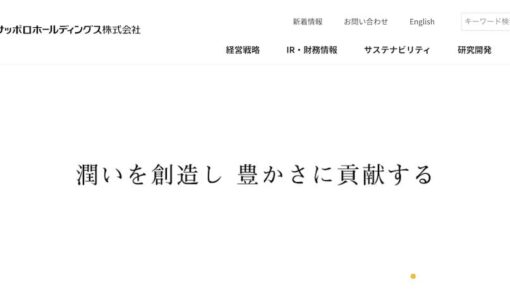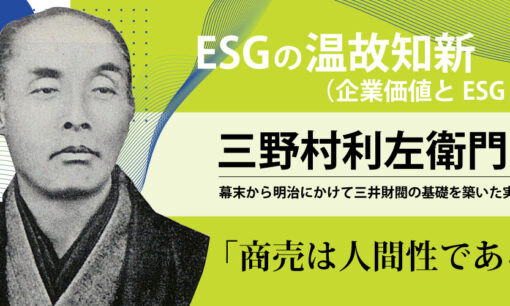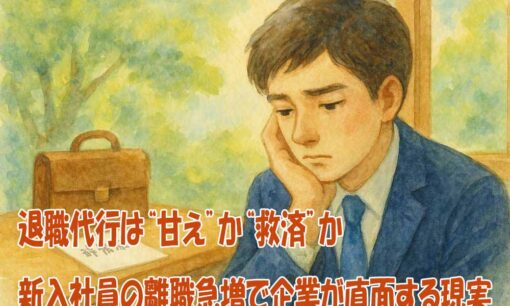冷たい風が吹き始めたこの時期、山も街も“静かな恐怖”に包まれている。
クマの出没が社会問題化する一方で、もうひとつの脅威が人々を脅かしているのがスズメバチだ。
東京・青梅市では小学生22人が刺され、広島県廿日市市でも児童19人が被害に遭った。さらに茨城県の住宅地では、軒先に約1500匹が生息する巨大巣が見つかった。ハンターたちが挑んだのは、命を賭した“1時間の攻防戦”だった。
各地で集団刺傷 「どこで起きてもおかしくない」
10月下旬、東京都青梅市。朝の空気が澄む校庭で、児童たちは落ち葉を拾っていた。
その足元の土の中から、突然黒い影が飛び立つ。
クロスズメバチは、地中に巣を作る性質を持つハチだ。
数秒のうちに悲鳴が上がり、児童20人と教員2人が次々と刺された。現場は一時騒然となり、22人全員が救急搬送された。
「まさか学校で、とは思わなかった」近隣住民は青ざめた表情で語る。
同じ頃、広島県廿日市市の登山道でも、校外学習中の小学生19人がハチに襲われた。秋の遠足が、恐怖の時間に一変した。
住宅地に“1500匹”の巨大巣 スズメバチハンターの死闘
11月上旬、茨城県守谷市の静かな住宅街。軒先から“ぶうん”という低い羽音が響いていた。
依頼を受けて駆けつけたのは、ベテラン駆除士・松原暢明さん。巣の直径は約60センチ、推定個体数は1500匹。
松原さんは改造バキュームで吸引を開始。
「作戦はひたすら吸い込むしかない」
だが、巣の中から次々と飛び出すハチがゴーグルを叩く。20分の予定が、終わったのは倍の40分後。
巣は5.2キロの重量を誇り、撤去後に住民は「頼んでよかった」と胸をなで下ろした。
同じ取材で、オオスズメバチの巣を掘り出す現場にも密着した。巣の直径は45センチ、出入り口をふさぐ“おっかぶせ”という金網を使って駆除する。
「オオスズメバチは執着心が強い。1匹が襲えば、群れ全体が攻撃してくる」
汗を流しながら語るハンターの声には、経験者だけが知る緊張感がにじむ。
「なぜ秋が最も危険なのか」 猛暑が延ばした“活動期限”
専門家によると、秋はスズメバチの最も攻撃的な時期だという。
繁殖を控えた女王バチを守るため、働きバチが巣の防衛に過敏になる。
さらに今年は猛暑の影響で気温の高い日が続き、巣が“終わる時期”が1〜2週間遅れている。
「例年なら10月末で静まるが、今年は11月もピーク」と松原さんは語る。
オオスズメバチが他のハチの巣を襲うこともあり、地域全体が“警戒モード”に入る。
まさに今が、一年で最も危険な季節だ。
「頭だけでも動く」恐るべき生命力 刺された時の正しい対処
福岡県では、建設作業中にキイロスズメバチに刺された男性がSNSに動画を投稿した。
頭と胴が切り離されても動き続けるハチの姿に、コメント欄は「ヒィィィ」「病院行って」と騒然となった。
東京大学の「ハチ刺され災害防止ガイドライン」によれば、刺された場合はすぐに洗浄・冷却し、全身症状が出たら119番通報を。
「一刻を争う」との注意書きがある。
クマ、マダニ、スズメバチ… 人と自然の境界が崩れている
今秋はクマによる死者が12人と過去最多を更新(環境省調べ)。マダニが媒介する感染症「SFTS」も全国で拡大している。
科学ジャーナリスト・石田雅彦氏はこう警告する。
「気候変動や里山の放棄で、自然と人の距離が近づきすぎている。野生動物や毒を持つ生物が、人の生活圏に踏み込んでいる」
つまり、クマもスズメバチも同じ根から生まれた危機だ。
温暖化による季節のずれ、食料や生息地の変化。それらが、野生と人間の境界を曖昧にしている。
身を守るために “野生と共に生きる”時代へ
スズメバチの巣を見つけたら、まず何よりも近づかないことが鉄則だ。巣の出入口や飛行ルートを刺激すれば、一瞬で数十匹が襲いかかることもある。自力での駆除は絶対に避け、すぐに自治体や専門の駆除業者へ連絡する必要がある。
また、ハチは黒や濃紺などの暗い色を敵と認識しやすく、香水や整髪料などの強い匂いにも敏感に反応する。外出時は白やベージュなど明るい服装を選び、帽子をかぶるのが望ましい。山や公園でハチを見かけたときは、慌てて手で払ったり走って逃げたりせず、ゆっくりと後退して距離を取ることが大切だ。
もし刺されてしまった場合は、速やかに安全な場所へ退避し、患部を水で洗い流して冷却する。痛みや腫れがひどい場合、また息苦しさやめまい、吐き気などの全身症状が出た場合は、ためらわず119番通報する。過去に刺された経験のある人は、重いアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を起こす危険性が高いため、医師の指示に従ってエピペンを携帯しておくことが望ましい。
そして今、私たちが直面しているのは、単なるハチの問題ではない。クマ、マダニ、そしてスズメバチ。そのすべてが、人と自然の距離がかつてないほど近づいた結果として現れている。
気候変動によって季節のリズムが崩れ、山の恵みや里山の環境が変化する中で、野生生物は生き延びるために人の暮らしのすぐそばにまでやって来ているのだ。
人と自然の共存が問われる時代。
「気をつける」だけでなく、「知り、備える」ことこそが、自分と家族を守る最初の一歩になる。