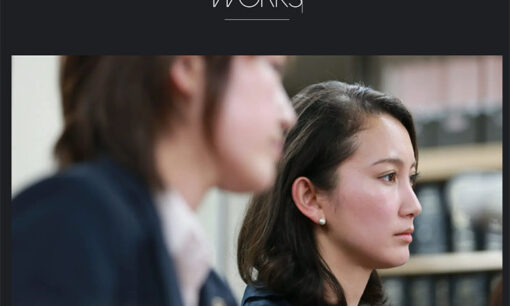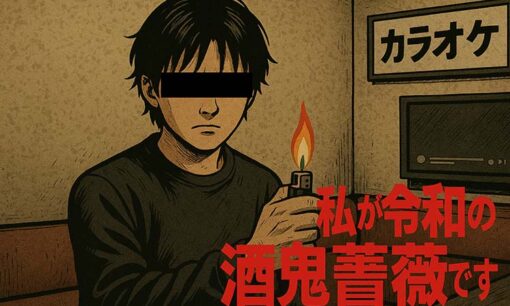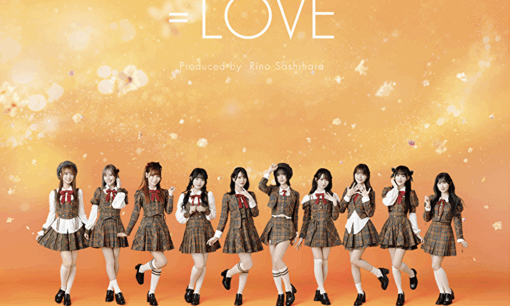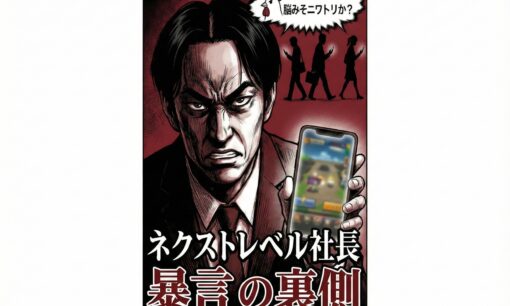全国でクマ被害が深刻化し、今年の死者は過去最悪を更新。
そんな中、青森県のイベントで提供された「ツキノワグマ串」がSNSで1300万超の閲覧を記録した。
“食べて駆除”は解決策になるのか。
白神山地のふもとにある小さな村で、山と共に生きてきた人々の声をたどると、そこには単純な賛否を超えた現実があった。
“山の味”がバズった日
10月下旬、青森の道の駅イベントで提供された「ツキノワグマの串焼き」がSNSで話題になった。
焦げた脂が滴る豪快な見た目と「臭みがなくホロホロ」「羊肉のよう」といった意外な感想が相まって、閲覧数は1300万を超えた。
コメント欄には「熊肉が普及すれば駆除が進むのでは」「食べて減らせば被害も防げる」といった声が並び、話題は一気に被害対策の議論へと広がった。
だがその裏で、実際に熊肉を扱う現場は、もっと複雑な事情を抱えている。
廃棄されていた命を活かす
熊串を販売したのは、青森県・西目屋村にある地域団体。
村は世界自然遺産・白神山地の玄関口に位置し、ブナ林と清流に囲まれた人口約1200人の集落だ。
かつてこの地では、罠にかかったクマをすべて廃棄していた。
しかし「山からの授かりものを無駄にしたくない」という声が広がり、2020年、村に食肉処理施設が誕生。
ここで安全基準を満たした熊肉を「白神ジビエ」として加工・販売する仕組みが整えられた。
串焼きや熊鍋、カレーなどの料理がイベントで提供され、地域の観光資源として注目を集めている。
ただし扱うのは、村の箱罠にかかった個体のみ。
“狩るための捕獲”ではなく、“生活を守るための対応”という立場を崩していない。
「食べて駆除」には限界がある
熊肉は、処理のわずかな違いで臭みや硬さが変わる繊細な食材だ。
衛生基準も厳しく、許可施設での解体と十分な加熱が義務づけられている。
さらに捕獲数は年によって大きく変動し、安定供給は難しい。
熊肉を商品として普及させるには、コスト、労力、技術が求められる。
つまり「食べて駆除」という構図は、現実的に成り立ちにくい。
それでも、廃棄されていた命を活かし、地域の経済や文化を支える試みには意義がある。
熊を単なる“害獣”とするのではなく、山の一部として見つめ直すきっかけになっている。
人の暮らしが山を変えた
被害が増えている背景には、人間の環境変化がある。
耕作放棄地の拡大、里山の荒廃、メガソーラー建設による森林の分断。
ドングリなどの餌が減った年には、クマが山を下りる。
つまり、問題の根は“クマが増えた”のではなく、“人が山を変えた”ことにある。
駆除や捕獲だけでは、被害の連鎖は止まらない。
境界をどう保ち直すかが問われている。
共存という知恵をつなぐ
白神の村の取り組みは、単なるジビエ事業ではない。
「必要以上に捕らない」「無駄にしない」というマタギ文化の精神を継ぎ、現代の課題に合わせて形を変えたものだ。
串焼きのバズは一瞬だったかもしれない。
だがその裏にあるのは、人と自然が共に生きるための知恵の積み重ねだ。
食べることで山を思い出す。
その感覚を持ち続けることこそが、クマ被害の根底にある問題を解く鍵になるのかもしれない。