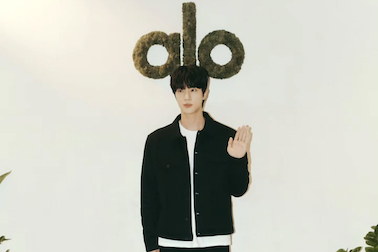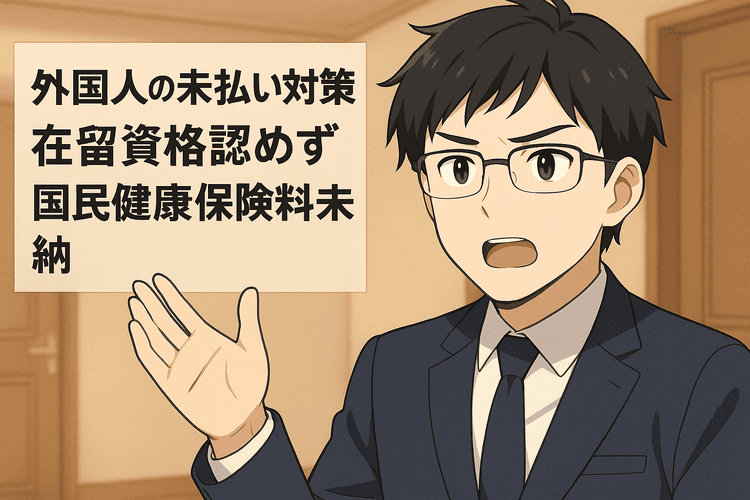
窓口の番号札が鳴るたび、役所の空気が少しだけ動いた。
書類を抱えた外国人男性が立ち上がる。国民健康保険の手続きを終えたばかりの彼は、不安げに職員へ尋ねた。
「もし払えなかったら、ビザは更新できないんですか?」
その問いに、職員は一瞬言葉を探した。
厚生労働省が打ち出した新制度――それは、こうした現場のささやきが政策の焦点に浮かび上がったことを象徴している。
外国人の国保未納、在留資格更新に反映へ
── 厚労省が2027年6月から制度改正を実施
厚労省は、外国人による国民健康保険料(国保)の未納や医療費の不払いが増えている現状を受け、出入国在留管理庁と連携した制度改正に踏み切る。
2027年6月から、保険料を長期間滞納した外国人については、原則として在留資格の更新や変更を認めない仕組みを導入する方針だ。
国保加入者の納付データを入管の審査システムと連携させ、滞納履歴を自動的に反映する。2026年度中に全国の自治体システムを改修し、翌年度から本格運用を始める予定である。
医療費の不払いに関しても、医療機関からの情報を入管が共有する体制を整備し、短期滞在者だけでなく中長期の在留者にも対象を拡大する。
上野賢一郎厚生労働相は記者会見で、「日本人と外国人が互いに尊重し、安心して暮らせる共生社会を実現するため、社会保障制度の適正な運用を進めたい」と述べた(共同通信による)。
国民健康保険の未納が在留資格に影響する仕組み
── 入管データと保険情報を連携、医療費不払いにも対応
新制度では、国保の納付履歴を出入国在留管理庁のデータベースと連携させ、滞納がある場合には自動的に警告が表示される。
滞納期間や基準の詳細は今後省令で定められるが、未納のまま放置した場合、在留資格の更新が難しくなる可能性がある。
これまで国保と在留管理は別の制度として運用されてきた。
しかし今後は「生活の実態」と「制度の履行」を一体で評価する仕組みへと変わる。
この転換が、日本の社会保障行政における大きな節目となる。
なぜ外国人の国民健康保険未納が問題化しているのか
── 納付率63%、背景に制度理解の壁と生活の不安定さ
厚労省の調査によれば、2023年度末時点で国保に加入している外国人は約97万人。全体の4%を占める。
しかし納付率は63%にとどまり、日本人を含む全体の93%を大きく下回る。
大阪のある自治体では、外国人世帯宛ての督促状が山のように積まれている。
封筒には「転出先不明」「帰国済み」と赤字で記されていた。
担当職員は「悪意ではなく、制度を理解できずに支払いが遅れているだけ」と語る。
言語の壁、複雑な手続き、短期雇用による不安定な収入――こうした複合的な要因が未納を生んでいる。
だが未納が続けば、自治体財政への影響は避けられない。
制度の公平性を保つため、国は「支払い能力の有無ではなく、制度参加の責任」を問う方向へかじを切った。
厚労省の狙いと新制度のポイント
── 公平な社会保障制度へ、納付意識の定着を促す
厚労省が掲げる狙いは明快だ。
保険料を適切に納める外国人が不利益を受けないようにし、制度全体の信頼を高める。
医療費の不払いを減らすことで、地域医療の安定にもつなげたい考えだ。
しかし、在留資格と納付状況を結びつけることには慎重論もある。
「支払い能力の問題と制度理解の不足は区別して扱うべきだ」と専門家は指摘する。
制度の厳格化が、支援の後退を意味してはならない――。
そのバランスをどう取るかが、制度設計の最大の焦点となる。
なぜ制度導入は2027年度なのか
── 政治・技術・行政、それぞれの「待たざるを得ない事情」
厚労省が制度導入を2027年度とした背景には、三つの事情がある。
一つは技術的な限界。国民健康保険の納付データは全国約1700の自治体が独立して管理しており、入管の在留資格データと照合する共通基盤が存在しない。
国は2026年度までにマイナンバー制度と連携させる形でシステムを改修し、セキュリティ認証を整える予定だ。
もう一つは行政現場の準備期間である。
自治体職員への研修、説明会、多言語対応の強化など、現場運用に必要な手順を整えるには時間がかかる。
特に地方自治体では、制度変更に伴う事務負担の増加を懸念する声が多く、丁寧な説明が不可欠とされている。
そして三つめは政治的配慮だ。
外国人の在留資格に関わる制度改正は国際的にも敏感なテーマであり、拙速に進めれば「排外的政策」との批判を招きかねない。
2027年度という設定は、国内世論を慣らし、地方自治体や企業側の理解を得ながら段階的に導入するための“冷却期間”でもある。
厚労省関係者は「この改革は技術でも政治でも、ひとつの『信頼のインフラ』を築く作業だ」と語った。
制度改正の本質は、単なる監視強化ではなく、データ・制度・人をどうつなぐかという行政の挑戦にある。
現場で聞く外国人の声 「書類が難しい」「制度がわからない」
── 厳格化と支援の両立が課題に
東京・新宿の外国人相談窓口では、制度改正に不安を抱える声が相次ぐ。
ベトナムから来た技能実習生の青年は、「毎月払っているが、もし遅れたら更新が止まるのか」と心配そうに語る。
隣で待つフィリピン出身の女性は「日本語の書類が難しく、どこに支払えばよいのかも分からない」と肩を落とした。
多言語での案内や納付サポート体制の充実――それらがなければ、制度は“公平”であっても“優しくない”。
国が目指す「共生社会」を支えるためには、支援の仕組みを並行して整えることが欠かせない。
SNSで広がる賛否の声
── 「公平性の確保」か「人権の侵害」か、議論は拡大
SNS上では、「日本で暮らすなら義務を果たすのは当然」「税金を納めている人の負担を軽くすべき」と賛同する声がある一方、
「在留資格を人質にする制度だ」「支援が先にあるべき」との反対意見も多い。
「制度改正だけでなく、外国人が理解しやすい仕組みを整えるべきだ」といった中間的な意見も目立つ。
賛否を超えて、“共に暮らす社会”の形をどう築くか――議論は今も広がっている。
2027年施行の新制度で企業・自治体・外国人が備えるべきこと
── 共生社会の実現へ、支援と理解をどう両立させるか
政府は2026年度中に準備を終え、2027年6月から制度を本格的に稼働させる。
影響は在留資格の更新時期に応じて現れ、外国人労働者を抱える企業にも波及する見通しだ。
企業は従業員の国保加入状況を管理し、納付漏れが在留更新に影響しないようチェック体制を整える必要がある。
自治体は、窓口での多言語対応を強化し、相談のハードルを下げる取り組みを急がねばならない。
制度の厳格化は避けられない流れだが、その中で“支える力”をどう育むか。
新制度は、単なるルールの改正ではなく、日本社会が「管理」から「信頼」へと進化できるかを試す転換点である。
結論:国保未納問題は「外国人だけの課題」ではない
── 公平性と包摂性を両立できる社会へ
国民健康保険の未納問題は、外国人だけに限らない。
制度の信頼を支えるのは、社会全体の理解と協力である。
2027年の改正は、単なる行政改革ではなく、誰もが安心して暮らせる社会の「基礎体温」を整える試みだ。
支払いの義務と支援の権利。その両輪がかみ合う時、日本の共生社会はようやく現実のものとなるだろう。